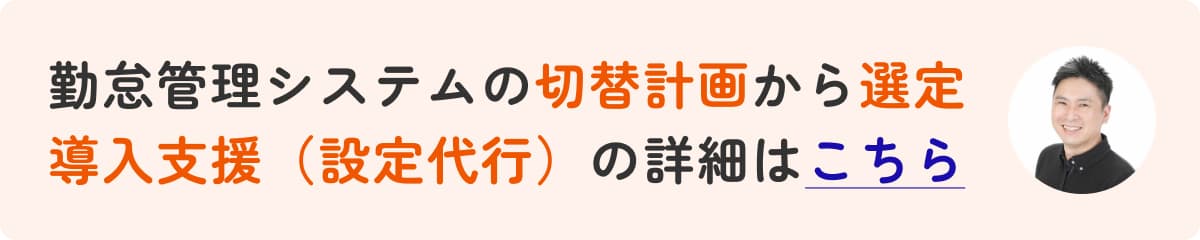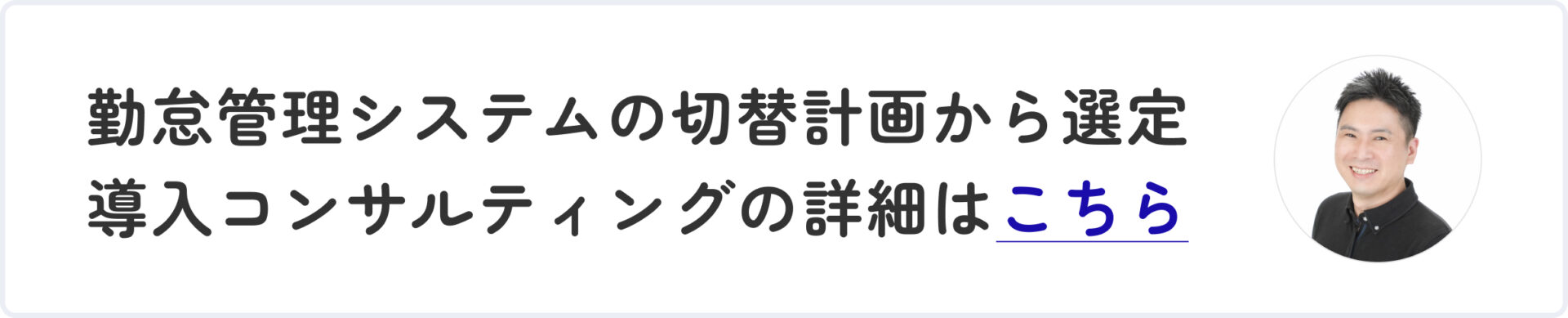大企業の人事労務厚生の担当者が「大企業向けの勤怠管理システム」を探していらっしゃるということは、現状のシステムに課題がある状況と思います。
現行の勤怠管理システムは十数年前に導入し、2019年の働き方改革関連法の対応やコロナ中のテレワーク対応など現行システムの改修や手運用でなんとか乗り切っている企業が多いことでしょう。
現行システムが古い画面やUI(ユーザーインターフェース)、使い勝手の悪さから、問い合わせ対応の件数が減らない。労働時間や回数を集計して、部署毎にExcel資料を配布する作業が毎月ある。また、従業員本人や管理監督者に対してより労務管理意識を持ってもらいたい、健康管理経営に力を入れていきたいなどの課題もあるかと思います。
本記事では、大企業が勤怠管理システムを切替(リプレイス)する際に、注意すべき事項や入れ替えによる具体的なメリット、そして失敗しないための選び方までをわかりやすく解説します。
大企業における勤怠管理システムの重要性
大企業にとって、勤怠管理システムは単なる業務の効率化ツールではありません。それは、企業の信頼性、法的リスクの管理、そして多様な人材の活用といった経営基盤そのものを支える、現代において不可欠な経営インフラです。
昨今の働き方改革関連法の施行により、すべての企業には労働時間の客観的な把握が厳しく義務付けられました。特に従業員数が多く、複数の拠点や多様な勤務形態(テレワーク、フレックスタイム制など)が混在する大企業において、多様な働き方を認めつつ、正確な勤怠管理をしていかないといけない状況です。
コンプライアンス違反が発生すれば、是正勧告や追徴金の支払いといった直接的なダメージだけでなく、企業名が報道されることによる社会的信用の失墜、優秀な人材の採用難など、計り知れない損失につながるリスクがあります。
勤怠管理システムとは
勤怠管理システムとは、従業員の出退勤時刻、休憩時間、残業、休暇取得状況といった勤怠データを、PCやスマートフォン、ICカードなどを通じて一元的に記録・管理し、給与計算に必要な労働時間を自動で集計するITシステムのことです。
厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、タイムカードやICカード、PCの使用時間の記録といった「客観的な記録」を基礎として労働時間を把握・記録することを求めています。
勤怠管理システムは、この「客観的な記録」を最も効率的かつ正確に実現する代表的な方法と言えます。また、勤怠管理システムには企業の課題を解決するための多様な機能が搭載されています。
| 機能分類 | 具体的な機能内容 |
| 打刻機能 | ・PC、スマホ(GPS連携)、ICカード、生体認証(指静脈など)といった多彩な打刻方法への対応 ・直行直帰やテレワーク中の打刻も可能 |
| 自動集計機能 | ・残業時間(法定内・法定外)、深夜労働、休日出勤などを就業規則に基づいた自動計算 ・年休の自動付与や有給休暇の取得状況、残日数の自動管理 |
| 申請・承認機能 | ・打刻修正や残業申請、各休暇取得申請などの申請承認フロー |
| アラート機能 | ・打刻漏れ、申請漏れ、締め遅れなどの入力漏れへの通知 ・長時間労働のリスクがある従業員やその管理者への自動アラート通知 |
| データ連携機能 | ・人事システムで管理されている人事情報(所属、役職)の連携 ・給与計算システムへの勤怠集計データの連携 ・シフト管理が別システムの場合はシフト情報の連携 |
なぜ大企業には勤怠管理システムが必要なのか
大企業では、数千人規模の従業員、多様な雇用・勤務形態、全国に散らばる拠点といった複雑な要因が絡み合うため、全社で統一されたルールに基づき、リアルタイムで正確な勤怠状況を把握できる勤怠管理システムの導入が不可欠です。
その理由は、中小企業とは比較にならないほどの「複雑性」にあります。
- 規模の複雑性: 従業員数が数千、数万の規模になると、Excelやタイムカードでの管理は物理的に不可能です。毎月の集計作業にかかる手間は膨大になり、ヒューマンエラーによる計算ミスや不正のリスクが飛躍的に増大します。
- 働き方の多様性: 本社、支社、工場、店舗といった複数の拠点ごとに異なる就業規則やシフトが存在します。さらに、テレワーク、リモートワーク、フレックスタイム制、時短勤務など、従業員一人ひとりの働き方も多様化しており、これらすべてを正確に管理するにはシステムの力が必要です。
- コンプライアンスの厳格化: 大企業は社会的責任が重く、労働基準法第36条で定められた時間外労働の上限規制の遵守を全社で徹底するには、システムによる客観的な労働時間管理と、超過しそうな従業員を早期に把握する体制が必須です。
- ガバナンス(企業統治)の要請: 上場企業には、内部統制報告制度(J-SOX)への対応が求められます。業務プロセスの標準化と透明性を確保する上で、勤怠管理はその根幹をなす要素であり、システム化による記録の適正化は重要な課題となります。
例えば、M&A(合併・買収)が多い大企業では、異なる人事制度や就業規則を自社の勤怠管理に統合していく必要があります。このような複雑な制度変更にも、カスタマイズ性の高い勤怠管理システムであれば柔軟に対応できるため、自社の成長戦略を支える意味でもシステムの活用は欠かせません。
従来の勤怠管理(タイムカード等)が抱える課題とリスク
タイムカードやExcelによる従来の勤怠管理方法は、非効率で不正確なだけでなく、「不正打刻」や「コンプライアンス違反」に直結する、極めて深刻な経営リスクを内包しています。これらの課題は、「非効率性」「不正確性」「対応力の欠如」の3つに大別されます。
| 課題分類 | 具体的な内容 |
| 非効率性 | ・担当者が毎月、全従業員分のタイムカードを目視で確認し、電卓やExcelで手入力して集計。膨大な作業時間と人件費が発生する。 ・集計した勤怠データを給与計算ソフトへ再度手入力する必要があり、二度手間と入力ミスの温床となる。 |
| 不正確性 | ・本人以外が打刻する「代理打刻」や、意図的な記録の改ざんといった不正を防止できない。 ・タイムカード打刻後に残業を行う「サービス残業」が常態化しやすく、実態を把握できない。これにより、後に莫大な未払い残業代の請求リスクを抱える。 |
| 対応力の欠如 | ・残業時間の上限規制、有給休暇の取得義務化といった複雑な法改正のロジックを、手作業で全従業員分チェックし、管理するのは極めて困難。 ・テレワークや直行直帰の従業員の労働時間を客観的に記録・把握する方法がない。 |
これらの課題は、最終的に「法的」「財務」「信用的」「業務」といった、経営を揺るがしかねない深刻なリスクへと発展します。従来の勤怠管理方法は、もはや大企業の複雑な労務管理に対応できる限界を完全に超えています。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
大企業が勤怠管理システムを導入するメリット
勤怠管理システムの導入は、法改正への対応やコンプライアンス遵守といった「守り」の課題解決にとどまりません。それは、業務効率化によるコスト削減、生産性の向上、さらには従業員エンゲージメントの向上といった、企業の成長を加速させる「攻め」の経営改革につながる多様なメリットをもたらします。
従来の手作業による管理が抱えていた非効率性やリスクを、システムによって解消することで、人事・労務担当者はより戦略的な業務に集中できるようになり、経営層は客観的なデータに基づいた迅速な意思決定が可能になります。
コンプライアンス強化と労務リスクの低減
勤怠管理システムの導入により、客観的な労働時間の記録と管理を徹底することで、労働基準法をはじめとする各種法令を遵守し、未払い残業代請求や労働基準監督署からの是正勧告といった深刻な労務リスクを大幅に低減できる点です。
システムは、複雑化する労働関連法規の遵守を強力にサポートします。例えば、労働基準法で定められた時間外労働の上限規制に対しては、従業員の残業時間をリアルタイムで自動集計し、上限を超過しそうな従業員や管理者にアラートで通知します。
また、年次有給休暇の年5日取得義務についても、システム上で休暇の取得状況を管理し、未達の従業員を容易に把握することが可能です。
このように、勤怠管理システムは法務・労務部門にとって強力な盾となり、企業が法令遵守を徹底し、健全な経営を続けるための基盤を固めることができます。
勤怠管理の自動化による業務効率化とコスト削減
勤怠データの収集、集計、給与計算ソフトへの連携といった一連のプロセスを自動化することで、人事・労務担当者の業務負担を劇的に軽減し、管理に要するコストを大幅に削減できます。
システムによるコスト削減は、タイムカード用紙などの「直接コスト」と、担当者の作業時間という「間接コスト」の両面に及びます。
| コストの種類 | 削減内容の具体例 |
| 直接コスト | ・タイムカードや申請用紙のペーパーレス化による消耗品費の削減 ・記録の保管スペースにかかる費用の削減 ・労働時間の正確な把握による、不要な残業代支払いの適正化 |
| 間接コスト | ・担当者が毎月行っていた勤怠データの集計や入力作業にかかる人件費の大幅な削減(最も効果が大きい) |
例えば、従業員1,000名の企業で、担当者2名が毎月合計80時間かけていた集計作業が、システム導入により10時間に短縮された場合、年間で840時間もの工数削減につながり、人件費に換算すると数百万円単位のコスト削減に相当します。
業務効率化によって創出された時間によって、担当者は勤怠データの集計といった定型業務から解放され、人材育成や制度設計といった、より付加価値の高い「戦略的人事」にリソースを集中させることが可能になります。
テレワークやフレックスなど多様な働き方への柔軟な対応
勤怠管理システムは、場所や時間にとらわれないテレワークやフレックスタイム制といった多様な働き方を、正確な労働時間管理のもとで実現するための必須ツールです。
在宅勤務で課題となる「中抜け」時間の管理や、始業・終業時刻の曖昧さに対しては、PCのログオン・オフ記録やスマートフォンからの打刻を組み合わせることで、客観的な労働時間を把握します。
また、フレックスタイム制特有の複雑な総労働時間の過不足管理も、システムが自動で計算し、従業員と管理者に通知するため、運用の負担が大幅に軽減されます。
このような多様な働き方への柔軟な対応は、優秀な人材の獲得・定着に直結します。育児や介護と仕事を両立したい従業員にとって、柔軟な勤務制度とそれを支えるシステムの導入は、企業選びの重要な判断基準となります。
正確な勤怠データの可視化による迅速な経営判断
リアルタイムで蓄積される正確な勤怠データを分析・活用することで、部門ごとの労働生産性やプロジェクトごとの人件費(工数)を可視化し、客観的なデータに基づいた迅速かつ的確な経営判断が可能になります。
例えば、部門単位での総労働時間と成果を比較分析し、生産性の高いチームの働き方を他部署に展開したり、特定のプロジェクトに投下されている人件費を正確に把握し、人員配置の最適化を行ったりすることが可能です。
また、特定の部署や時期に残業が集中していないかをデータで把握することで、業務プロセスの見直しなどを客観的な根拠に基づいて判断できます。
多くの高機能な勤怠管理システムには、勤怠状況をグラフなどで直感的に可視化する「ダッシュボード機能」が搭載されており、データを容易に活用できます。このように勤怠管理システムは、勤怠データを単なる「記録」から、経営を改善し企業を成長させるための「戦略的資産」へと昇華させる力を持っています。
従業員満足度(EX)の向上
煩雑な勤怠関連の申請手続きを撤廃し、公平で透明性の高い労働時間管理を実現することで、従業員のストレスを軽減し、企業への信頼感を醸成し、従業員満足度(EX: Employee Experience)の向上に大きく貢献します。
従業員は、スマートフォンやPCからいつでもどこでも休暇や残業の申請が可能になり、紙の申請書を提出する手間がなくなります。また、自身の労働時間や有給休暇の残日数をいつでも正確にチェックできるため、給与計算への信頼感が高まります。
客観的な記録によりサービス残業が撲滅され、働いた分が正当に評価されるという安心感は、従業員のモチベーションを維持する上で非常に重要です。従業員満足度(EX)の向上は、離職率の低下や生産性の向上につながります。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
大企業向け勤怠管理システムの選び方と比較ポイント
大企業における勤怠管理システムの選定は、単に機能の有無を比較するだけの単純な作業ではありません。それは、自社特有の複雑な社内規定、将来の組織拡大を見据えた拡張性、そして何よりも堅牢なセキュリティといった多角的な視点が求められる、極めて重要な経営判断です。
システム選定のプロセスそのものが、人事・労務部門だけでなく、情報システム部門、経理部門、さらには経営層までを巻き込む一大プロジェクトとなります。安易な選定は、導入後の運用で混乱を招き、期待した効果を得られないばかりか、新たな経営リスクを生むことにもなりかねません。
法定より従業員に手厚い大企業特有の導入要件
大企業における勤怠管理システム選定の最初の関門は、法律で定められた最低基準を上回る、従業員に手厚い自社特有の就業規則や社内規定を、いかに正確にシステム上で再現できるか、という点にあります。
労働基準法はあくまで勤怠管理の最低ラインを定めたものであり、多くの大企業は、優秀な人材を確保・維持するために法定基準よりも手厚い条件を就業規則や労働協約で定めています。これらは法的な拘束力を持ち、システムはこれらの独自ルールに完全に対応する必要があります。
比較的導入が容易なSaaSは、法定基準を軸に設計されているため、大企業独自のルールには対応しきれない可能性があります。
そのため大企業のシステム選びでは、まず自社の複雑な就業規則を完璧に再現できるカスタマイズ性と柔軟性を最優先で確認することが、選定を成功させるための鍵となります。
クラウド型かオンプレミス型かの選択
勤怠管理システムの提供形態である「クラウド(SaaS)型」と「オンプレミス型」の選択は、自社のセキュリティポリシー、求めるカスタマイズのレベル、そしてコスト構造の考え方によって決まります。
近年のHR-Tech市場はクラウドサービスを中心に急成長しており、特に、頻繁な法改正への自動アップデート対応は、運用の負担を大幅に軽減するため大企業にとって大きなメリットです。
| 比較項目 | クラウド(SaaS)型 | オンプレミス型 |
| 初期費用 | 低い(または無料) | 高い(サーバー購入、開発費) |
| 運用コスト | 月額利用料 | 保守・メンテナンス費用、専任担当者の人件費 |
| 導入期間 | 短い(数週間~数ヶ月) | 長い(数ヶ月~1年以上) |
| カスタマイズ性 | 標準機能の範囲内が中心。柔軟性は低め | 非常に高い。自社の要件に合わせて自由に開発可能 |
| セキュリティ | ベンダーのレベルに依存 | 自社で管理。ポリシーを厳格に適用可能 |
| 法改正対応 | ベンダーが自動でアップデート | 自社で対応する必要があり、コストと時間がかかる |
高度なカスタマイズ性を求めるならオンプレミス型ですが、導入スピード、コスト効率、法改正への対応といった観点から、クラウド型も現代の大企業にとって有力な選択肢であると言えるでしょう。
機能(打刻・休暇管理・システム連携・セキュリティ等)
大企業がシステムを評価する際は、基本的な勤怠管理機能に加え、多様な打刻方法への対応力、複雑な休暇管理、既存の基幹システムとの円滑な連携実績、そして信頼性の高いエンタープライズレベルのセキュリティ機能を精査する必要があります。
これらの機能に不備があれば、給与支払いの遅延や個人情報の漏洩といった、企業の信頼を根底から揺るがす事態に直結しかねません。選定時には、以下の機能要件を確認することが重要です。
- 打刻方法:オフィス(ICカード)、工場(生体認証)、在宅勤務(PCログ)、直行直帰(スマートフォンのGPS打刻)など、あらゆる勤務環境に対応できるか。
- システム連携:自社で利用中の給与計算ソフトや人事管理システムとの確実な連携実績があるか。
- 承認ワークフロー:部署や役職に応じて、複数の承認者を介するような複雑な承認ルートを自由に設定できるか。
- セキュリティ:IPアドレス制限、シングルサインオン(SSO)といった、大企業の求めるセキュリティ水準を満たしているか。
大企業に求められるのは、単機能のツールではなく、自社のあらゆる業務ニーズに柔軟に対応できる、網羅的かつ堅牢な機能群を備えたプラットフォームです。
コスト・料金体系
コストを評価する際、大企業は表面的な「月額単価×人数」の計算だけでなく、初期費用やカスタマイズ費用、導入後の追加料金まで含めた「総所有コスト(TCO)」の視点で比較検討する必要があります。
大企業向けの料金体系は複雑な場合が多く、月額料金が安価でも、高額な初期費用や必須オプション料金が設定されているケースも少なくありません。
最終的な費用感を正確に把握するため、見積もりを取る際には、導入コンサルティング費用などの「初期費用」、料金体系や割引の有無などの「月額費用」、そして個別開発にかかる「カスタマイズ費用」といった項目を必ず確認しましょう。
正確なコスト比較のためには、自社の要件を明確にした上で、複数のベンダーから詳細な見積もりを取得し、3~5年単位での長期的な総所有コストを算出して判断することが不可欠です。
導入実績・サポート体制
大企業がシステムを選定する上で、機能やコストと同等以上に重要なのが、自社と同規模・同業種の企業への豊富な導入実績と、導入プロジェクトから運用までを支える手厚いサポート体制です。
大企業への導入は極めて複雑なプロジェクトであり、ベンダー側の経験不足はプロジェクト失敗の主要因となり得ます。実績とサポート体制を見極めるには、以下の点を確認します。
- 導入実績:自社と同じくらいの従業員規模の企業や、同じ業界の企業への導入事例を具体的に確認する。第三者機関の調査による市場シェアも信頼性の指標となります。
- サポート体制:導入時に専任の担当者がつくか、運用後のサポート窓口の対応時間や連絡手段、障害発生時のSLA(サービス品質保証制度)はどうなっているか。また、システム活用を能動的に支援するカスタマーサクセスチームの有無も重要なポイントです。
勤怠管理システムの選定は、長期的なパートナー選びに他なりません。自社の課題への深い理解を示し、導入から安定運用までを安心して任せられる、信頼性の高いベンダーを選択することが最も重要です。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
大企業におすすめの勤怠管理システム12選

| サービス名 | タイプ | 特徴・実績 |
|---|---|---|
| COMPANY | 統合型 | 大手企業向け人事システムのデファクトスタンダードとして、様々な業種業態のお客様、約1,200の大手法人グループに導入いただいており、500万人以上の従業員データを管理しています。 |
| POSITIVE | 統合型 | |
| 統合型 | ||
| 単体/フロント型 | ||
これまで解説してきたポイントを踏まえ、実際に多くの大企業で導入実績があり、市場で高く評価されている代表的な勤怠管理システムを12つ厳選してご紹介します。
大きな分類としては、人事給与システムまで含めた統合型のサービスと勤怠管理に特化および申請系などフロント(従業員が利用するサービス)業務ここで紹介する製品は、いずれも大企業特有の複雑な就業規則や多様な勤務形態への対応力、そして高度なセキュリティ水準を誇る、信頼性の高いソリューションです。もちろん、最適なシステムは企業の業種や文化、既存の人事・給与システムとの連携などによって異なります。
COMPANY 勤怠管理(Works Human Intelligence)
「COMPANY」は、日本の大手企業向けERPパッケージ市場で圧倒的なシェアを誇るWorks Human Intelligence社が提供する、統合型HCM(Human Capital Management)の勤怠管理システムです。
勤怠だけでなく人事・給与・タレントマネジメントまでを一つのシステムで完結できるのが最大の特徴です。人事・勤怠・給与といったバックオフィス業務全体の効率化と標準化を目指し、システムを一つに統合したいと考える大企業におすすめです。
| 特徴 | 具体的な内容 |
| 多様な働き方への対応 | 変形労働時間制やフレックスタイム制、在宅勤務など、大企業で採用されるあらゆる勤務形態に標準機能で対応可能。 |
| 豊富な機能モジュール | 勤怠管理だけでなく、シフト管理、休暇管理に加え、プロジェクトごとの工数管理機能も充実しており、人件費の正確な把握に貢献します。 |
| 統合データベース | 勤怠、人事、給与のデータが一元管理されているため、システム間の連携が不要。データの整合性が常に保たれ、管理の手間を大幅に削減します。 |
COMPANYの主な導入実績
JR貨物、JFEスチール、キリン、日産自動車、三井住友フィナンシャルグループ、山崎製パン、オートバックスセブン、ヤクルト、神戸大学、群馬県、ニトリ、三菱ケミカル
リシテア 就業管理|日立ソリューションズ
日立ソリューションズが提供する「リシテア」は、30年以上の歴史と日立グループ内での実践ノウハウが凝縮された、信頼性の高い勤怠管理システムです。
1994年の提供開始以来、累計1,700社以上、218万人以上の利用実績が、その安定性と信頼性の高さを証明しており、特に、コンプライアンス遵守とグローバル対応に強みを持ちます。
厳格なコンプライアンス体制の構築が急務である企業や、海外拠点も含めたグループ全体の勤怠を統一システムで管理したいと考えるグローバル企業に最適です。
| 特徴 | 具体的な内容 |
| コンプライアンス徹底 | 36協定的確な残業時間管理と段階的なアラート機能により、長時間労働を未然に防止します。 |
| グローバル対応 | 日本語、英語、中国語に標準対応。海外拠点を持つグローバル企業でも、全従業員が安心して利用できる環境を構築できます。 |
| 柔軟なシステム連携 | 人事・給与システムはもちろん、入退室管理システムや弁当発注システムなど、様々な周辺システムとの柔軟な連携が可能です。 |
リシテアの主な導入実績
JR東日本旅客鉄道、INPEX、リクルート、清水建設、LIXIL、日本航空、TIS、アサヒビール、日本生命、ソニー、日本精工、相鉄、リコー
TimePro-VG|アマノ
タイムレコーダーのパイオニアであるアマノ社が、その長年のノウハウを結集して開発した勤怠管理システム「TimePro」シリーズの大企業向けハイエンドモデルが「TimePro-VG」です。勤怠管理の分野でトップクラスのシェアを誇る専門メーカーならではの、きめ細やかな機能と高い信頼性が魅力です。
勤怠管理の専門性を重視し、ハードウェアと連携した正確な時刻管理を徹底したい企業や、セキュリティ要件からオンプレミス型での導入を検討している企業におすすめです。
| 特徴 | 具体的な内容 |
| 提供形態の柔軟性 | 自社のセキュリティポリシーや運用体制に合わせて、クラウド型とオンプレミス型のどちらでも提供可能な、貴重な製品です。 |
| 豊富な打刻手段 | ICカードや生体認証など、アマノ社製の高精度なタイムレコーダーと完全連携し、正確な時刻記録を実現します。 |
| ハイエンドモデル | シリーズの最上位製品として、大企業の複雑な就業規則や多階層の組織構造に対応する、強力なカスタマイズ性を備えています。 |
【主な導入企業】
- C&Fロジホールディングス
- 丸井グループ
- ゴールドウイン
キンタイミライ(ネオレックス)
「キンタイミライ」は、「結果的に一番使いやすい」をコンセプトに、クラウド黎明期からサービスを提供するネオレックス社の勤怠管理システムです。20年以上にわたるクラウド事業の実績があり、大企業の複雑な要件に応えるための、手厚い専任コンサルティングと柔軟なカスタマイズを強みとしています。
パッケージシステムでは自社の複雑なルールを再現しきれないと悩んでいる企業や、専任チームによる手厚いサポートを受けながらシステム導入を確実に成功させたい企業に最適な選択肢です。
| 特徴 | 具体的な内容 |
| 柔軟なカスタマイズ | 自社の就業規則に合わせ、専任のコンサルティングチームが要件をヒアリングし、システムを柔軟にカスタマイズします。 |
| 多様な打刻方法 | ICカード、QRコード、生体認証など、多様な打刻方法に対応し、多様な業種・業態のニーズに応えます。 |
| 直感的なUI | 従業員から管理者まで、誰にとっても分かりやすく直感的に操作できる画面設計にこだわっています。 |
【主な導入企業】
- イケア・ジャパン
- 西武ホールディングス
- キャメル珈琲
TIME-3X|三井E&Sシステム技研
「TIME-3X」は、造船・機械といった大手製造業の現場で培われたノウハウを基に開発された勤怠管理システムです。
三井E&Sグループの一員として長年、製造業の基幹システムを手掛けてきた実績があり、特に複雑な勤務パターンが混在する製造業やサービス業のシフト管理に強みを発揮します。
特に複雑なシフト管理が課題となっている製造業、小売業、運輸業などの大企業や、とにかく使いやすいシステムを求めている企業におすすめです。
| 特徴 | 具体的な内容 |
| 優れた操作性(UI) | 従業員や管理者が毎日使うものだからこそ、誰にとっても直感的に操作できる、見やすい画面デザインにこだわっています。 |
| 柔軟なシフト機能 | 日勤、夜勤、交代制勤務など、複雑な勤務パターンが混在する大企業のシフト作成・管理に柔軟に対応します。 |
| 工数管理との連携 | 勤怠管理と工数管理を連携させ、「誰が」「どの作業に」「どれだけの時間をかけたか」を正確に把握し、製造原価の見える化を支援します。 |
【主な導入企業】
- 旭化成
- DAISO
- AOKIホールディングス
Universal勤次郎(勤次郎)
「Universal勤次郎」は、30年以上の歴史と累計22,000社以上の導入実績を誇る「勤次郎」社のフラッグシップモデルです。勤怠管理を基点とした多彩なシステム連携と、健康経営を支援する機能が大きな特徴です。
勤怠管理を入口として、従業員の健康管理やエンゲージメント向上といった、より戦略的な人事施策に取り組みたいと考える企業に最適なソリューションです。
| 特徴 | 具体的な内容 |
| 多彩なシステム連携 | 勤怠管理を中核に、給与、人事、健康管理、安否確認など、多彩なシリーズ製品とシームレスに連携し、バックオフィス業務を幅広くサポートします。 |
| 健康経営の推進 | 労働時間のデータと、ストレスチェックなどのヘルスケアデータを連携させ、従業員の心身の健康状態を可視化。健康経営の実現を支援します。 |
| コンプライアンス遵守 | 36協定の遵守や有給休暇取得義務化など、あらゆる法改正に迅速に対応し、企業のリスク管理を支援します。 |
【主な導入企業】
- 大塚商会
- ミクロ情報サービス
WiMS/SaaS 勤務管理システム|ソリューション・アンド・テクノロジー
「WiMS/SaaS 勤務管理システム」は、クラウド型の勤怠管理システムで、内部統制やグループ会社管理といった大企業特有の要件に強く、勤怠管理と工数管理の連携による厳密な予実管理を実現します。上場企業やそのグループ会社を中心に、多くの大企業での導入実績があります。
グループ全体のガバナンスを強化したい企業や、プロジェクト単位での厳密な工数管理を実現し、従業員の生産性を高めたいと考える企業におすすめです。
| 特徴 | 具体的な内容 |
| 大企業向けシステム設計 | 上場企業に求められる内部統制(J-SOX)への対応や、複数のグループ会社の勤怠を横断的に管理できる機能など、大企業向けのシステム設計がなされています。 |
| 勤怠と工数の連携 | 出退勤の打刻と同時に業務の工数を入力することで、勤怠時間と作業時間の差異がなくなり、正確な予実管理が可能になります。 |
| セルフマネジメント促進 | 業務の予実が可視化されることで、従業員一人ひとりが自身の生産性を意識し、セルフマネジメント能力を向上させる効果が期待できます。 |
【主な導入企業】
- セブン&アイホールディングス
- 竹中工務店
- 近鉄エクスプレス
Teamspirit |チームスピリット
「Teamspirit」は、世界No.1のCRM/SFAであるSalesforceをプラットフォームとして構築された、勤怠管理・工数管理・経費精算などを一体化したクラウドサービスです。
SaaS型の勤怠・工数管理市場でトップクラスのシェアを誇り、特にSalesforceを利用しており、そのデータを最大限に活用して勤怠管理や工数管理を効率化したいと考える企業にとっては、親和性の高い選択肢と言えるでしょう。
| 特徴 | 具体的な内容 |
| Salesforceとの完全連携 | Salesforceと同じプラットフォームで動作するため、データの完全統合が可能。例えば、営業担当者がSalesforceに入力した商談活動の時間を、そのまま工数として勤怠に反映できます。 |
| 一体型ソリューション | 勤怠管理から経費精算、電子稟議までの一連の業務をワンストップで実現。従業員は複数のシステムを使い分ける必要がありません。 |
| グローバル基準の信頼性 | Salesforceの堅牢なセキュリティと高い信頼性を基盤としているため、大企業でも安心して利用できます。 |
【主な導入企業】
- DMM
- U-NEXT Holdings
- 東京理科大学
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
大企業の勤怠管理システムについてよくある質問
大企業の勤怠管理システム導入について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
- Qシステム導入までにかかる期間はどのくらい?
- A
大企業における勤怠管理システムの導入期間は、要件定義の開始から本稼働まで、一般的に6ヶ月から1年以上を要します。これは、導入するシステムの種類(クラウド型かオンプレミス型か)や、カスタマイズの度合いによって大きく変動します。
中小企業と異なり、大企業の導入プロジェクトが長期化するのは、関係部署との調整の多さ、複雑な就業規則の設定、膨大な従業員データの移行、そして給与計算に関わるミスの許されない厳密なテストが必要になるためです。
システム導入は、焦りは禁物です。特にテストと従業員への研修に十分な期間を設け、周到なプロジェクト計画を立てて進めることが、導入を成功に導くための最も重要な鍵となります。導入プロジェクトの標準的なフェーズと期間の目安は以下の通りです。
フェーズ 期間の目安 主な活動内容 1. 計画・選定 2~3ヶ月 課題の洗い出し、要件定義、RFP(提案依頼書)作成、ベンダー選定、契約 2. 設計・設定 2~4ヶ月 ベンダーとの要件すり合わせ、就業規則のパラメータ設定、承認ワークフローの設計 3. データ移行・テスト 1~3ヶ月 従業員マスターデータの移行、既存システムとの並行稼働テスト、ユーザー部門による受け入れテスト(UAT) 4. 教育・本稼働 1~2ヶ月 管理者・従業員への教育、部門ごとの段階的な展開、本稼働開始、導入後フォロー 合計 6ヶ月~12ヶ月
- Q既存の給与計算ソフトや人事システムと連携できる?
- A
大企業向けの勤怠管理システムのほとんどは、既存の給与計算ソフトや人事システムと連携可能です。ただし、その連携方法や費用は製品によって大きく異なるため、選定における極めて重要な比較ポイントとなります。
大企業は基幹となる人事・給与システムを既に導入しているため、勤怠管理システムのベンダーにとって、既存システムとの柔軟な連携機能を提供することは必須要件です。
主な連携方法には、勤怠データをCSVファイルで出力して手動で取り込む「CSVファイル連携」と、システム同士が自動で直接データをやり取りする「API連携」があります。リアルタイム性と業務効率化の効果は、後者のAPI連携が圧倒的に優れています。
ベンダーを選定する際には、単に「連携できる」という言葉だけでなく、「自社で利用中の給与計算ソフトとの具体的な連携実績」「連携方法と追加の開発費用」までを詳細に確認することが、スムーズなデータ連携を実現するために不可欠です。
- Q従業員への説明会はどのように実施すれば良い?
- A
従業員への説明会は、一度きりの集合研修で終わらせるのではなく、対象者別に内容を変え、複数の形式(集合研修、動画マニュアル、FAQサイトなど)を組み合わせて段階的に実施することが、導入を成功させる鍵です。
大企業には多様な従業員が在籍するため、画一的な説明会では全員の理解を得ることは困難です。効果的な説明会の進め方として、以下のような多面的なアプローチをおすすめします。
アプローチ 具体的な実施内容 対象者別の研修 ・管理者向け: 部下の勤怠承認やデータの活用方法など、マネジメントに必要な機能を中心に解説。
・一般従業員向け: 打刻や各種申請の操作方法など、日常業務で使う機能に絞って分かりやすく説明。多様な形式の活用 ・集合研修/Webセミナー: 導入の背景や目的を共有し、質疑応答で疑問を解消する場として実施。
・動画マニュアル: 「休暇の申請方法」など、機能ごとの短い操作動画を用意し、いつでも見返せるようにする。
・FAQサイト/チャットボット: よくある質問とその回答をまとめた社内サイトを準備し、従業員が自己解決できる環境を整える。段階的な情報提供 ①導入決定~準備期間: なぜシステムを変えるのか、いつから変わるのか、といった全体像を早期にアナウンス。
②本稼働直前: 具体的な操作方法に関する研修や説明会を集中的に実施。
③本稼働後: フォローアップ研修や、個別の質問に対応する相談会などを設ける。従業員への展開は、単なる「操作説明」ではなく、システム変更への理解を促し、全社で新しい体制へ移行するための「チェンジマネジメント」の一環と捉えるべきです。丁寧なコミュニケーション計画が、システムのスムーズな定着と活用を促します。
最適な勤怠管理システムは、大企業の成長を加速させる戦略的インフラ
本記事では、大企業における勤怠管理システムの重要性から、具体的なメリット、そして失敗しないための選び方までを網羅的に解説してきました。もはや勤怠管理システムは、単に労働時間を記録・集計するためのツールではありません。
働き方改革関連法への対応といったコンプライアンス遵守(守り)はもちろんのこと、勤怠データの活用による生産性の向上、業務効率化によるコスト削減、そして従業員満足度の向上といった、企業の持続的な成長を支える「攻めの経営基盤」としての役割を担っています。
最適なシステムを選び抜くためには、まず、法定基準を上回る手厚い休暇制度や複雑な就業規則といった、自社特有の要件を完璧に再現できる「カスタマイズ性」を見極めることが最重要です。
この記事で紹介した以外にも、世の中には数多くの優れた勤怠管理システムが存在します。さらに多くの選択肢から自社に本当に最適な製品を比較・検討するためには、網羅的な情報を収集できる専門サイトの活用が非常に有効です。
勤怠管理システムの選定・比較サイト「勤怠管理システムの選定・比較ヨウケン」では、多様な勤怠管理システムの機能や価格を客観的に比較検討できますので、ぜひご活用ください。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。