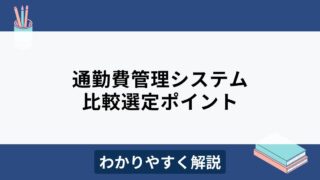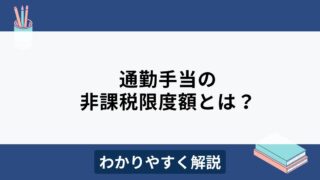従業員の満足度を高めるために欠かせない「通勤手当」。しかし、その計算方法や支給基準など、運用における課題は少なくありません。さらに、テレワークや在宅勤務が普及した現代では、通勤手当をどう設計するべきか頭を悩ませている企業経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
通勤手当は、企業が従業員に提供する福利厚生の一環として重要な役割を果たします。一方で、交通手段に応じた支給額の決め方やテレワーク従事者への対応など、考慮すべきポイントも多岐にわたります。
本記事では、通勤手当の設計・運用にお悩みの方向けに、支給額の相場から交通手段ごとの計算方法、決め方のポイントなどをわかりやすく解説します。また、実務上よく寄せられる質問への回答もまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
通勤手当の基本
通勤手当は、法律で支給が義務付けられたものではありませんが、多くの企業が従業員の経済的負担の軽減や福利厚生の充実を目的に採用しています。一度導入すれば従業員の「賃金」の一部として扱われるため、その制度設計には税法や労働法の正しい理解が不可欠です。
法律上、企業に従業員の通勤費用を負担する義務はありません。しかし、就業規則や賃金規程に支給ルールを定めた場合、その通勤手当は労働基準法第11条で定める「賃金」に該当し、企業はルールに基づき適切に支給する義務を負います。
通勤手当の制度は従業員の満足度や採用競争力にも影響しますが、その金額は社会保険料の算定基礎に含まれるなど、企業側のコストにも直結します。
そのため、担当者は通勤手当の法的な位置づけや「交通費」との違いを正確に把握し、自社に合った公平で合理的なルールを設計・運用していくことが、適切な労務管理の第一歩となります。
通勤手当とは?定義と目的
通勤手当とは、従業員が自宅から勤務先まで通勤する際に発生する費用を補助するための手当であり、就業規則や労働契約に基づいて支給されるのが一般的です。この手当は、交通費補助としての役割に加え、福利厚生の一環として位置づけられています。
その主な目的は、従業員の日々の通勤にかかる経済的負担を軽減すること、そして住宅手当などと同様に、企業の福利厚生の一環として優秀な人材の確保や定着率向上に繋げることにあります。
支給する金額や計算方法、対象となる通勤手段(公共交通機関、マイカー、自転車など)の範囲は法律で定められているわけではなく、各企業が就業規則や賃金規程で独自にルールを決定します。例えば、「最も経済的かつ合理的な経路」の実費を支給する場合もあれば、通勤距離に応じて一律の金額を支給する場合もあります。
労働基準法における通勤手当の扱い
労働基準法では通勤手当の支給義務は明記されていませんが、第37条において割増賃金の計算に含めない手当として挙げられています。
なお、就業規則や雇用契約書で通勤手当の支給について定めている場合は、企業は従業員に対して通勤手当を支給する義務が生じます。
「通勤手当」と「交通費」の違い
「通勤手当」が自宅と会社を往復する“通勤”のために定期的に支給されるのに対し、「交通費」は顧客訪問や出張など“業務”上の移動で発生した費用を実費精算するものです。両者は目的も法的性質も全く異なります。
この違いは、その支払いが「労働の対償(賃金)」にあたるか、「業務遂行に必要な経費」にあたるかという点に基づきます。通勤手当は福利厚生的な意味合いを持つ賃金の一部ですが、交通費は従業員が業務のために一時的に立て替えた経費の精算(実費弁償)であり、賃金には該当しません。
両者の違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 通勤手当 | 交通費(旅費交通費) |
| 目的 | 従業員の通勤にかかる費用の補助 | 業務上必要な移動にかかる費用の精算 |
| 法的性質 | 賃金(労働の対償) | 経費(実費弁償) |
| 課税の扱い | 所得税は一定の限度額まで非課税 | 原則として全額非課税 |
| 社会保険 | 算定基礎(標準報酬月額)に含まれる | 算定基礎に含まれない |
| 支給形態 | 給与と合わせて毎月など定期的に支給 | 発生の都度、申請に基づき実費を精算 |
| 具体例 | 電車やバスの定期代、ガソリン代 | 顧客先への訪問、遠方への出張費用 |
この「通勤手当は給与の一部、交通費は会社の経費」という区別は、給与計算、税務処理、社会保険料の算出など、労務管理のあらゆる場面で正しく認識しておく必要があります。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
通勤手当の相場
厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によると、通勤手当の企業全体での支給割合は92.3%、平均支給額は11,700円となっています。また、従業員規模別のそれぞれの数値は以下のとおりとなっています。
| 従業員規模 | 支給割合 | 平均支給額 |
|---|---|---|
| 1,000人以上 | 94.4% | 13,300円 |
| 300~999人 | 96.8% | 11,400円 |
| 100~299人 | 94.8% | 10,800円 |
| 30~99人 | 91.0% | 10,300円 |
支給割合は従業員規模30~99人の小規模企業でも91.0%と、他の諸手当に比べて高いのが特徴です。また、平均支給額は従業員規模が大きい企業ほど高い傾向が見られます。
通勤手当の計算方法
通勤手当の計算方法は、従業員の通勤手段や距離に応じて異なります。公共交通機関利用者には定期券代が基準となることが多く、マイカー通勤者や徒歩・自転車通勤者には距離や実際の通勤費用を考慮した方法が採用されます。
非課税限度額とは
非課税限度額とは、企業が従業員に支給する通勤手当のうち、所得税や住民税が課税されない上限額のことです。この限度額は、通勤手段や通勤距離に応じて国税庁によって定められています。
この制度の根拠は、通勤手当が実費弁償に近い性質を持つことを考慮し、一定範囲内での課税を免除する趣旨の所得税法の規定に基づきます。ここで労務管理上、最も注意すべき点は、所得税と社会保険料の扱いが異なることです。
通勤手当が所得税法上非課税であっても、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の算定基礎となる標準報酬月額には、支給額の全額が含まれます。この点を混同すると社会保険料の計算を誤るため、明確に区別して理解してください。
なお、支給する通勤手当が非課税限度額を超えた場合、その超過した部分の金額は給与所得として扱われ、所得税・住民税の課税対象となります。
公共交通機関を利用する場合の計算方法
公共交通機関を利用する場合、通勤定期券代を基準に支給するのが一般的です。定期券代の全額支給が最も多く採用される方法ですが、勤務形態によっては出勤日数に応じた実費支給が適用されることもあります。
公共交通機関を利用する従業員に対しては、通勤に要する実費相当額を支給することが合理的と考えられます。必ずしも最安の経路が合理的というわけではなく、所要時間や乗り換え回数などを考慮して、社会通念上、妥当と認められる経路を選択することが一般的です。
最寄り駅の考え方
最寄り駅とは通常、従業員の自宅から最も近く、かつ一般的に利用可能な駅を指します。しかし、「最も近く」の判断基準(直線距離か道なり距離か等)や、複数路線が利用可能な場合の選択基準などについては、企業ごとに判断が異なるため、就業規則等で定めておくことが重要です。
たとえば、自宅から徒歩圏内に複数の駅(A駅とB駅)がある場合、自宅に最も近いA駅よりも、勤務地へのアクセスが良いB駅を最寄り駅とみなした方が合理的である可能性もあります。
マイカー通勤の場合の計算方法
マイカー通勤では、通勤距離やガソリン代を考慮して計算します。多くの企業が距離別の基準表を用いるか、実際の経費を基に手当を設定しています。
マイカー通勤の場合、公共交通機関のように一定の運賃が存在しないため、通勤経路に応じた通勤距離またはガソリン単価と燃費をもとに通勤手当を算出するのが合理的と考えられます。
ガソリン単価と燃費による計算
マイカー通勤の通勤手当を、ガソリン単価と燃費を用いて計算する場合、一般的には以下の計算式を用います。この計算式を用いることで、ガソリン価格の変動や従業員が使用する車種の燃費の違いを、ある程度、通勤手当の額に反映させることが可能です。
通勤距離(往復)× 勤務日数 × ガソリン単価 ÷ 燃費
計算に用いるガソリン単価は、企業が独自に定めますが、資源エネルギー庁が公表する「石油製品価格調査」の結果を参考に、地域や時期を考慮して設定することが考えられます。
また、燃費は従業員が使用する車種の燃費データに基づくことが望ましいですが、実務上は困難な場合もあります。そのため、企業が車種ごとに基準燃費を定める、あるいは、全車種一律の燃費を適用する、などの方法が考えられます。
距離による計算
マイカー通勤の通勤手当を距離によって計算する場合、一般的には以下の計算式を用います。マイカー通勤にかかる費用は、走行距離にほぼ比例して増加すると考えられるため、この計算式は簡便でありながら、通勤実態をある程度反映できる合理的な方法と言えます。
通勤距離(片道)× 距離単価 × 勤務日数 × 2(往復)
距離単価は企業が独自に定めますが、国税庁が定めるマイカー通勤者の非課税限度額を参考に設定されることが多いです。例えば、片道15km以上25km未満の場合、非課税限度額は月額12,900円であるため、距離単価を400円/km程度に設定すれば、ある程度適正な範囲に収まります。
また、通勤距離の測定方法は、「従業員からの申告に基づき、地図ソフトで計測する」「実測距離を計測する」などの方法があります。
徒歩・自転車通勤の場合の計算方法
徒歩や自転車通勤の場合、通勤手当は支給されない、または一定額を支給する企業が多いです。徒歩通勤の場合、通勤にかかる費用が発生しないため、通勤手当を支給しないのが一般的です。
自転車通勤の場合も、マイカー通勤と比較すると、通勤にかかる費用は少額です。そのため、通勤手当を支給しない、または、距離に関わらず一定額を支給する企業が多くなっています。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
通勤手当の決め方のポイント
通勤手当を適切に決めるには、支給要件や基準を明確に定め、公平性を確保する必要があります。テレワークや在宅勤務の増加に対応した新しい運用方法や、不正受給を防ぐ仕組みを整えることが重要です。
支給要件を明確にする
通勤手当の支給対象や条件を明文化することで、従業員間の不公平感を防ぎ、企業の透明性を高めることができます。通勤手当の支給要件が曖昧な場合、従業員によって解釈が異なり、不公平感やトラブルが生じる可能性があります。
例えば、「公共交通機関を利用する場合に支給する」という規定だけでは、新幹線や特急列車の利用も認められるのか、自転車と電車を併用する場合はどうなるのかなど、様々な疑問が生じます。こうしたトラブルを避けるためには、就業規則等で支給要件を詳細に定めることが重要です。
テレワーク・在宅勤務に対する扱いを決めておく
テレワークや在宅勤務の普及に伴い、従来の通勤を前提とした通勤手当のあり方を見直す必要が生じています。企業は、テレワーク・在宅勤務時の通勤手当の扱いについて、支給しない、実費精算とする、在宅勤務手当を支給する、などの対応を検討し、就業規則等に明記して従業員に周知することが重要です。
テレワークや在宅勤務では、従業員は自宅などで業務を行うため、通勤が発生しません。そのため、従来の通勤を前提とした通勤手当の支給は、実態にそぐわないものとなります。
具体的には、以下のような対応策が考えられます。
- 月の半分以上出社する場合は定期券代を支給し、それ以外は出社日数に応じた金額を支給するなど、出社日数に応じて支給額を調整する。
- 出社した日の交通費を実費精算する。
- 通勤手当を支給する代わりに、在宅勤務手当(通信費や光熱費の補助など)を支給する。
- 通勤手当を廃止し、その分を基本給に上乗せする。
不正受給を防止する
通勤手当の不正受給は、企業に経済的損失を与えるだけでなく、他の従業員の士気低下や不公平感に繋がり、企業秩序を乱す行為です。支給申請時の通勤経路の確認、定期的な実態調査、不正受給者への厳正な処分など、不正受給を防止するための対策を講じ、就業規則等に明記しておく必要があります。
通勤手当の不正受給の例として、実際には自転車通勤なのに電車通勤と偽って申請したり、虚偽の通勤経路を申告して過大な通勤手当を受け取ったりするケースが考えられます。不正受給を防止するための具体的な対策としては、以下のようなものが挙げられます。
- 支給申請時の確認: 通勤経路や通勤手段について、地図ソフトや公共交通機関のウェブサイトなどを活用して確認する。
- 定期的な実態調査: 従業員の通勤実態を定期的に確認し、申告内容と相違がないか調査する。
- 不正受給者への処分: 不正受給が発覚した場合は、就業規則等に基づき、不正受給分の返還請求などの厳正な処分を行う。
- 従業員への啓発: 不正受給は許されない行為であることを従業員に周知徹底し、不正行為を抑止する。
定期券は数ヶ月ごとにまとめて支給する
通勤手当として定期券代を支給する場合、1ヶ月分ずつ支給するよりも、3ヶ月や6ヶ月など複数月分をまとめて支給する方が、企業、従業員双方にとってメリットがある場合が多いです。従業員の利便性や企業側の事務コストを考慮し、適切な支給方法を検討しましょう。
多くの公共交通機関では、定期券を複数月分まとめて購入する方が、1ヶ月分ずつ購入するよりも割引率が高くなります。そのため、企業が複数月分の定期券代をまとめて支給することで、通勤手当の総支給額を抑えられる可能性があります。
ただし、複数月分の定期券代をまとめて支給する場合、従業員が途中で退職したり、通勤経路が変更になったりした場合に、定期券の払い戻しや差額精算などの手続きが煩雑になるというデメリットもあります。
直線距離か道なり距離か
通勤手当の計算で用いる距離を「直線距離」とするか「道なり距離」とするかよって、支給額が変わる可能性があるため、就業規則等で明確に定義し、従業員に周知しておくことが重要です。
直線距離とは、地図上で2点間を直線で結んだ距離です。管理が容易で従業員による差異が生じにくいのがメリットですが、実際の通勤経路との乖離が生じる可能性があるため、注意が必要です。
一方の道なり距離とは、実際の道路や交通機関の経路に沿った距離で、一般的に直線距離よりも長くなります。道なり距離を採用する場合、実際の通勤実態に近い距離を算出できる反面、距離の測定に手間がかかるなど、管理コストが増加することがあります。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
通勤手当についてよくある質問
通勤手当について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
- Q通勤手当は課税対象?
- A
通勤手当は、原則として給与所得として課税対象となりますが、通勤手段や通勤距離に応じて、一定の非課税限度額が定められています。非課税限度額を超えて支給された場合は、超えた部分が課税対象となります。
通勤手当は、従業員の通勤にかかる費用を補助するものですが、給与所得の一部とみなされるため、原則として課税対象となります。ただし、通勤にかかる費用は従業員の実費負担となるため、一定の非課税限度額が設けられています。
例えば、公共交通機関を利用する場合、最も経済的かつ合理的な経路による通勤手当の額が月額15万円以下であれば非課税となります。また、マイカー・自転車通勤の場合は、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が定められています。
- Qパート・アルバイトの通勤手当の日割り計算はどうする?
- A
編集者と校正役
思考プロセスを表示
通勤手当についてよくある質問
この章では、「通勤手当は課税されるのか」「パートタイマーの日割り計算はどうするのか」「一度始めた制度は廃止できるのか」といった、労務管理の担当者が実務で頻繁に遭遇する疑問について、Q&A形式で分かりやすく回答します。
これらの疑問は、基本的な計算方法を理解していても、税金や社会保険、多様な働き方への対応といった、より複雑な実務上の問題から生じます。それぞれの質問に対して、法的根拠や実務上のベストプラクティスを交えながら具体的な対応方法を解説しますので、日々の業務や従業員からの問い合わせ対応にお役立てください。
Q1. 通勤手当は課税対象?
この質問に対する答えは、「何の税金・保険料か」によって異なります。**所得税・住民税については「一定額まで非課税」**ですが、**社会保険料や雇用保険料については「全額が計算対象」**となります。この違いを混同しないことが極めて重要です。
所得税法上、通勤手当は実費弁償の性質が強いことから、国税庁が定める限度額(公共交通機関は月15万円まで、マイカー等は距離に応じて)までは非課税とされています。
一方で、厚生労働省の通達では、通勤手当は「労働の対償」である「賃金(報酬)」に該当するとされています。そのため、非課税枠に関係なく、支給された金額の全額が社会保険料の計算基礎である「標準報酬月額」や、雇用保険料の計算基礎である「賃金総額」に含まれます。
両者の違いを以下の表にまとめました。
税金・保険料の種類 課税・算定の扱い 備 考 所得税・住民税 一定額まで非課税 国税庁の限度額を超えた分だけが課税対象 社会保険料 全額が算定対象 非課税分も含め、支給額の全額が標準報酬月額に含まれる 雇用保険料 全額が算定対象 支給額の全額が保険料計算の基礎となる賃金総額に含まれる Google スプレッドシートにエクスポート
給与計算を行う際は、「所得税は一部非課税だが、社会保険料・雇用保険料は全額計算対象」と、絶対に間違えないように注意してください。
Q2. パート・アルバイトの通勤手当の日割り計算はどうする?
勤務日数が変動するパートタイマーやアルバイトの方には、月額の定期代を支給するのではなく、出勤日数に応じた「日割り計算」で通勤手当を支給するのが最も公平かつ合理的です。
日割り計算を義務付ける法律はありませんが、実態に即して費用を支払う「実費弁償」の原則に立てば、出勤しない日の分まで手当を支給する必要はないため、この方法が最も妥当と言えます。具体的な計算方法は、就業規則に以下のように定めておくと良いでしょう。
- 計算方法:
- 公共交通機関:
1日あたりの往復運賃 × その月の実出勤日数 - マイカー通勤:
(往復距離 × 1kmあたりの単価) × その月の実出勤日数
- 公共交通機関:
- 上限額の設定: トラブル防止のため、「日割りで計算した支給額は、1ヶ月の通勤定期代を上回らないこと」を上限として規定しておくのが一般的です。
このルールを就業規則に明記し、全対象者に公平に適用することが重要です。
- 計算方法:
- Q通勤手当は廃止できる?
- A
通勤手当の支給が法律で義務づけられていない以上、その廃止についても企業の任意と言えます。ただし、就業規則等で通勤手当の支給を定めている場合、従業員の同意を得ずに一方的に廃止することは、不利益変更に該当し、無効となる可能性があります。
通勤手当を廃止する代わりに、基本給の増額や新たな手当の支給など、従業員の不利益を緩和する措置を講じることで、不利益変更に該当しないと判断される場合もあります。
また、企業の経営状況の悪化など、廃止に合理的な理由がある場合、従業員との協議を尽くした上で廃止が認められる可能性もあります。
通勤手当の運用はシステム化が不可欠
通勤手当は、企業が従業員に提供する福利厚生の一環として重要な制度です。しかし、その設計や運用方法には多くの疑問や課題が伴います。
通勤手当制度を適切に運用するためには、就業規則等で明確なルールを定め、従業員に周知徹底することが不可欠です。しかし、従業員の通勤手段や通勤距離は個々に異なり、また、テレワークの導入など働き方も多様化しているため、手作業で管理するのは限界があります。
こうした課題を解決するには、給与計算システムや人事システムなどとシームレスに連携できる勤怠管理システムの導入が効果的です。従業員の勤怠情報と連携することで、出社日数に応じた通勤手当の支給も効率化できます。
勤怠管理システムを導入する際には、企業の規模や勤務形態に合った最適なシステムを選ぶことが大切です。「勤怠管理システムの選定比較サイト」を利用すれば、多様なシステムを要件別に一括で比較できるため、御社にマッチした最適なシステムを楽に見つけ出せます。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。