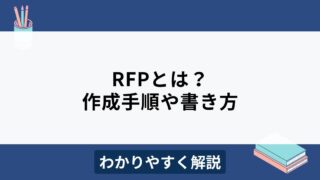- 「ベンダーから期待外れの提案しか集まらなかった…」
- 「後から追加費用が発生し、予算を大幅に超過してしまった…」
- 「導入したシステムが、実際の業務に合わなかった…」
システム調達において失敗を防ぐためには、情報収集(RFI)、提案依頼(RFP)、見積取得(RFQ)という3つのステップを正しく踏み、それぞれの文書を正確に使い分ける必要があります。
しかし、実際にはこの違いがあいまいなまま進んでしまい、冒頭に列挙したように、提案内容がチグハグになったり、想定外の費用が発生したりするケースも少なくありません。
本記事では、そんなよくある混乱を解消すべく、「RFP」「RFI」「RFQ」の意味と違い、活用タイミング、具体的な記載項目をわかりやすく解説します。
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
RFP・RFI・RFQの違い一覧
RFP、RFI、RFQは、企業の購買・調達活動において、ベンダーへ依頼を行うための3種類の文書(依頼書)です。
これらは利用する目的とタイミングに明確な違いがあり、例えば新しい勤怠管理システムや給与計算システムを導入する際、この違いを理解し正しく使い分けることが、プロジェクト成功の鍵となります。
これらの文書を使い分けるべき最大の根拠は、ベンダー選定におけるトラブルを回避し、自社の課題に最適な製品・サービスを導入するためです。
RFI、RFP、RFQという段階的なプロセスを踏むことで、情報の不確実性を徐々に減らし、最終的な要件の精度を高めることができます。3つの文書の具体的な違いは以下のとおりです。
| 項目 | RFI (Request for Information) | RFP (Request for Proposal) | RFQ (Request for Quotation) |
|---|---|---|---|
| 日本語名 | 情報提供依頼書 | 提案依頼書 | 見積依頼書 |
| 目的 | ベンダーや製品に関する幅広い情報収集 | 課題解決のための具体的な提案の依頼 | 要件が確定した上での正確な価格(見積)の依頼 |
| 発行タイミング | システム選定プロセスの初期段階 | 候補ベンダーを数社に絞り込んだ段階 | 最終候補ベンダーを1~3社に絞り込んだ最終段階 |
| 依頼内容 | 企業概要、製品の機能一覧、導入事例など基本情報の提示 | 課題背景、目的、要件などを提示し、解決策の提案を求める | 具体的な機能、数量などを記載し、同条件での価格(費用)提示を求める |
| ゴール | 市場や技術の把握、候補ベンダーリストの作成 | 複数の提案を比較・検討し、最適なベンダーを選定する | 価格交渉を行い、発注先を最終決定する |
例えば「法改正に対応するため新しい勤怠管理システムを検討しているが、どんな製品があるのか全く分からない」という段階では、まず複数のベンダーにRFIを発行し、広く情報提供を依頼するのが有効です。これにより、自社の課題を解決する可能性のある様々な方法を把握できます。
そして、RFIで得た情報をもとに要件(給与システムとの連携、打刻方法など)を固めた上で、候補のベンダーにRFPを提出し、具体的な提案と費用感を依頼します。このように、RFI、RFP、RFQはそれぞれが異なる目的と役割を持つ重要なビジネス文書です。
特に労務管理のように法規制や複雑な社内規定が絡むシステムの調達においては、これらを適切なタイミングで正しく使い分けることが、自社に最適なベンダーを選定し、プロジェクトを成功に導くための不可欠なプロセスとなります。
RFP・RFI・RFQの利用フロー
システム導入やベンダー選定において、失敗が少なく最も理想的とされる利用フローは、「RFI → RFP → RFQ」という順番で段階的に進めるプロセスです。この流れで進めることで、情報収集から具体的な提案の比較、そして最終的な価格決定までを、論理的かつ効率的に行うことが可能になります。
このフローが推奨されるのは、意思決定の根拠となる情報の精度を、段階を追うごとに高めていくことができるためです。いきなりRFP(提案依頼書)から始めると、自社がまだ知らない優れた技術や製品の情報を得る機会を失う可能性があります。
また、要件が曖昧なままRFQ(見積依頼書)を依頼しても、ベンダーごとに見積の前提条件が異なり、正確な価格比較が困難になるなど、トラブルや手戻りの原因になりかねません。この利用フローを、より具体的な段階(フェーズ)に分けて解説します。
市場や技術動向を把握し、課題解決の可能性を探ります。10~15社程度の幅広いベンダーにRFIを提出し、製品概要や導入事例などの資料提供を依頼します。ここでは優劣をつけず、あくまで情報収集に徹し、自社の理解を深めることが目的です。
RFIで得た情報をもとに、自社の要件に合った具体的な提案を比較検討します。候補ベンダーを3~5社に絞り込み、現状の課題や背景、目的を丁寧に記載したRFPを作成・送付します。
提案内容に納得した最終候補から、同条件での見積を取得し、費用面での最終比較と決定を行います。ベンダーを1~3社に絞り、詳細な機能や開発範囲を明記したRFQを提出します。ただし、RFPの段階で概算見積も依頼するため、仕様が大きく変更されなければ、このプロセスは省略されることもあります。
「RFI → RFP → RFQ」という利用フローは、ベンダー選定における失敗リスクを最小限に抑え、自社の課題を真に解決できる最適なパートナーを見つけ出すための王道プロセスです。
この流れを基本として理解し、自社の状況に応じて適切に活用することが、新しいシステム導入プロジェクトを成功に導くための確実な一歩となります。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
RFPとは
RFP(Request for Proposal)とは、日本語で「提案依頼書」と訳され、自社が抱える課題や達成したい目的をベンダーに明示し、それらを解決するための具体的なシステム構成や導入・開発の方法、そしてそれに要する費用を含んだ提案を正式に依頼するための文書です。
特に、法改正や複雑な社内規定が絡む労務管理の領域においては、複数のベンダーから最適な提案を引き出すための「羅針盤」となる、極めて重要なビジネス文書と位置づけられます。
RFPが重要視される最大の理由は、ベンダーとの認識の齟齬から生じる導入後のトラブルを未然に回避できる点にあります。
口頭での打ち合わせや簡易なメールだけで依頼した場合、自社の業務の複雑さや真の課題がベンダーに正確に伝わらない可能性があり、「期待していた機能がなかった」「追加費用が想定外に発生した」といった問題に繋がりかねません。
RFPという標準化された文書を用いることで、自社の要件を正確に伝えるとともに、複数のベンダーからの提案を公平な土俵で比較・検討することが可能となり、客観的で合理的な選定が実現します。
RFPの定義と目的
RFPの定義は「自社の課題や要件を体系的に明記し、ベンダーに対して課題解決のための具体的な提案を正式に依頼するための文書」です。
その目的は「複数のベンダーから、同条件下で質の高い提案を収集し、客観的な基準で比較・検討することを通じて、自社のビジネスに最も貢献する最適なパートナーを選定すること」にあります。
RFPを活用することで、ベンダー選定における「公平性」と「網羅性」を担保できます。担当者の個人的な好みや、特定のベンダーの営業力だけで選定を進めてしまうと、企業全体にとっての最適解とはならない可能性があります。
RFPを用いることで、選定プロセスそのものが標準化・可視化され、各社の提案を多角的な視点から公平に評価することができ、なぜそのベンダーを選定したのかという論理的な根拠を社内外に明確に示すことが可能となるのです。
RFPには、主に以下の3つの目的・役割が含まれます。
- 自社課題の明確化と整理: RFPを作成するプロセスは、関係部署へのヒアリングや現状の業務フローの棚卸しを伴います。この活動を通じて、これまで漠然としていた課題やシステム導入の真の背景が言語化・明確化され、社内での目的意識の統一が図られます。
- 提案の質の向上と均質化: ベンダーは、RFPに記載された情報を根拠として提案を作成します。したがって、具体的で詳細なRFPは、各社からより質の高い、的を射た提案を引き出すことに直結します。
- 選定プロセスの公平性・透明性の担保: 全ベンダーに同じRFPを提出し、同じ基準で評価することで、選定プロセスの公平性と透明性が保たれ、選定結果に対する社内の納得感も醸成しやすくなります。
このように、RFPの目的は単に提案を集めるという形式的な活動ではなく、「自社の課題整理」「提案の質の向上」「公平な選定」という3つの重要な目的を達成するための手段です。この目的を十分に理解した上でRFPを作成・活用することが、システム導入プロジェクトの成功確率を飛躍的に高めます。
RFPの記載項目
質の高い提案を引き出すRFPには、記載すべき必須項目がいくつか存在します。これらは大きく分けると、「①プロジェクトの概要」「②現状の課題と目的」「③具体的な要件(機能要件・非機能要件)」「④提案依頼事項」「⑤選定プロセスとスケジュール」の5つが主要な構成要素です。
これらの項目は、ベンダーに「思考の材料」を過不足なく提供し、提案の精度を最大限に高めてもらうために欠かせません。もしRFPに記載された情報が不足していると、ベンダーは自社の課題や目的を正確に理解できず、憶測で提案を作成したり、選定に余計な時間がかかったりするトラブルの原因となります。
勤怠管理システムの導入を例に、主要な記載項目とそのポイントを以下に示します。
| 大項目 | 主な記載項目 | 記載のポイント(勤怠管理システムの例) |
|---|---|---|
| ①プロジェクト概要 | ・プロジェクト名 ・背景と趣旨 ・スケジュール概要 | 「多様な働き方に対応するための次期勤怠管理システム導入プロジェクト」など、趣旨が明確に伝わるようにする。 |
| ②現状の課題と導入目的 | ・現状の業務フロー ・現在抱えている課題 ・システム導入で実現したいこと | 「手作業による集計で毎月20時間の残業が発生している」「頻繁な法改正に迅速に対応したい」など、課題を具体的・定量的に記載する。 |
| ③要件定義 | ・機能要件 ・非機能要件(性能、セキュリティ等) | 【機能要件】「ICカード・スマホアプリでの打刻」「残業時間の自動計算とアラート機能」など、必須(Must)と希望(Want)を分けて記載する。 【非機能要件】「レスポンス時間は3秒以内」「ISMS認証の取得」など。 |
| ④提案依頼事項 | ・提案書に盛り込んでほしい項目 ・見積の条件と内訳 ・導入実績の提示 ・導入後のサポート体制 | 「初期費用と月額費用(サーバー代、保守費用など)を分けて提示」「同業他社への導入実績を3社以上提示」など、依頼内容を明確に指定する。 |
| ⑤選定プロセスとスケジュール | ・提案締切日 ・質疑応答期間 ・プレゼンテーション日程 ・ベンダー決定予定日 | 具体的な日付を明記することで、ベンダーは社内リソースの調整がしやすくなり、プロセスが円滑に進行する。 |
これらの項目を過不足なく、かつ具体的に記載することが、結果として自社の課題解決に最も貢献する優れた提案と、信頼できるパートナーを選定するための強固な土台となります。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
RFIとは
RFI(Request for Information)とは、日本語で「情報提供依頼書」と訳され、システム導入や業務委託先の選定を検討し始めた初期段階において、ベンダーに対して企業の概要、製品・サービスの基本情報、導入実績といった情報提供を幅広く依頼するための文書です。
まだ自社の要件が具体的に固まっていない時期に、市場の動向把握や技術の実現可能性を調査する目的で活用されます。
RFIが有効なのは、ベンダー選定の初期段階における情報の非対称性を解消できる点にあります。実際に、多くの企業がDX推進の課題として「適切な外部ベンダーやパートナーを見つけられない」ことを挙げており、検討の初期段階では情報が不足しているのが一般的です。
この状態でいきなり具体的な提案依頼(RFP)に進んでしまうと、自社の狭い視野の中でしかベンダーを検討できず、最適な選択肢を見逃す可能性があります。RFIは、この課題を解決し、広い視野で検討を始めるための有効な第一歩となります。
RFIは、いわば未知の領域へ踏み出す際の「地図」を作成するような活動です。まずは広く情報を収集して市場の全体像を理解し、自社が進むべき方向性を見定める。この丁寧な準備プロセスが、その後の要件定義やRFP(提案依頼書)の精度を格段に高め、最終的なベンダー選定の成功に繋がります。
RFIの定義と目的
RFIの定義は「ベンダー選定や要件定義のプロセスに先立ち、市場の動向、新しい技術、製品・サービス、ベンダーの実績などに関する幅広い情報提供を、あくまで中立的な立場で依頼するための文書」です。
RFPとの決定的な違いは、その目的が「具体的な提案や見積を求めること」ではなく、「情報収集に徹し、自社の知識を深めて検討の方向性を定めること」に限定される点です。
要件が固まっていない初期段階で詳細な提案や価格を求めてしまうと、ベンダー側に大きな作業負担を強いることになり、協力をためらったり、情報提供の質が低下したりする可能性があります。
RFIが持つ主な目的は、以下の3つに整理できます。
- 市場・技術動向の把握(市場調査): 自社の課題を解決しうる製品やサービスが世の中にどれくらい存在するのか、最新の技術トレンドは何か、といった市場の全体像を広く把握します。
- 実現可能性の調査(フィジビリティスタディ): 自社が漠然と考えている構想が、現在の技術で実現可能なのか、また、実現するとすればどれくらいの費用感や時間がかかりそうか、といった大枠を掴みます。
- ベンダー候補のリストアップ(ロングリスト作成): 自社の課題に関心を示し、的確で分かりやすい情報提供をしてくれる信頼できそうなベンダーをリストアップします。このリストが、次の段階であるRFP(提案依頼書)の送付先候補となります。
このように、RFIの目的は何かを「決定する」ことではなく、決定するための材料を「知る」ことにあります。この情報収集という本来の目的に徹することで、公平な立場で市場を俯瞰し、その後の意思決定の質を高めるための強固な土台を築くことができるのです。
RFIの記載項目
RFIに記載すべき項目は、詳細な要件を求めるRFPほど厳密である必要はありません。重要なのは、ベンダーが協力しやすいように、簡潔で分かりやすい内容にすることです。
主要な構成要素としては、「①依頼の趣旨・背景」「②自社の概要と課題」「③情報提供を依頼したい項目」「④今後のスケジュール」の4点が挙げられます。
「依頼の趣旨」や「自社の課題」を伝えなければ、ベンダーは何を期待されているのか分からず、的の外れた情報を送ってくるかもしれません。また、「情報提供依頼項目」を明確に指定しておかないと、各社から体裁の異なる膨大な資料が送られてきて、後で情報を整理・比較するのが大変になります。
以下に、RFIの記載項目の具体的な作成例を示します。
件名: 人事制度改革に関する情報提供のお願い
1. はじめに(依頼の趣旨):この度は、弊社の「人事制度改革」に関する情報収集にご協力いただき、誠にありがとうございます。つきましては、貴社がご提供されている関連ソリューションについて、以下の情報をご提示いただけますようお願い申し上げます。
2. 弊社の概要と背景・課題:弊社は、従業員〇〇名の製造業です。現在、年功序列型の人事制度に限界を感じており、従業員のエンゲージメント向上と、成果が正当に評価される新人事制度の導入を検討しております。
3. 情報提供依頼項目:つきましては、以下の項目について情報をご提供ください。
- 貴社の会社概要(パンフレット等)
- 貴社が提供する人事評価・タレントマネジメント関連の製品・サービスの概要資料
- 上記製品・サービスの標準的な機能一覧
- 同様の課題を持つ他社様(特に製造業)への導入事例(3社程度)
- おおよその価格帯やライセンス体系(※詳細な見積は不要です)
4. 今後のプロセスと提出期限
- ご提出期限: 2025年〇月〇日(〇)
- 今後の流れ: ご提出いただいた情報を元に社内で検討を進め、2025年〇月頃に、より具体的なRFP(提案依頼書)を送付させていただく予定です。
RFIの記載項目は、ベンダーに詳細な提案を強いるものではなく、自社の課題をオープンに伝えつつも、相手の負担を考慮した簡潔な依頼を心がけるスタンスで作成することが肝要です。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
RFQとは
RFQ(Request for Quotation)とは、日本語で「見積依頼書」と訳され、導入する製品やサービスの要件(仕様)が具体的に決定している状況で、複数のベンダーに対して、完全に同一の条件下での正確な価格(見積)の提示を依頼するための文書です。
主にRFP(提案依頼書)で提案内容の評価を終え、発注先候補を数社に絞り込んだベンダー選定の最終段階で用いられます。RFQがベンダー選定の最終段階で重要となるのは、「コストの妥当性」を客観的に評価し、最終的な意思決定を行うためです。
どんなに優れた提案であっても、企業として予算を度外視することはできません。各社の見積の前提条件が異なっていると、単純な価格比較ができず、どのベンダーが本当にコストパフォーマンスに優れているのか判断が難しくなります。
RFQは、このプロセスを標準化し、各社の価格を公平な土俵で比較することで、費用の適正化と選定プロセスの透明化を実現する有効な手段なのです。
RFQは、いわばベンダー選定における最後の「値札」を確認する作業です。RFPで評価した提案内容という「価値」と、RFQで明らかになる「価格」とを天秤にかけ、自社にとって最も費用対効果の高い決定を下すための、客観的で極めて重要な判断材料と言えるでしょう。
RFQの定義と目的
RFQの定義は「要件が完全に確定した製品・サービスについて、複数のベンダーから同一条件下での価格見積を収集し、比較するための依頼書」です。
その目的は、機能や提案内容が同等レベルであると評価された最終候補ベンダーの中から、「価格」という明確かつ客観的な基準を用いて、最終的な発注先を決定することにあります。
ベンダー選定の最終段階でコストの妥当性を客観的に評価することは、企業の利益を守るための重要なプロセスです。これにより、担当者のどんぶり勘定や、ベンダーとの不透明な関係による不適切な価格決定を回避し、なぜその価格でそのベンダーに決定したのか、という説明責任を果たすことが可能になります。
RFQの目的をより深く理解するために、RFPの目的との違いを明確にしておきましょう。
- RFPの目的: How(どうやって課題を解決するか)の提案を求めることにあります。価格も評価項目の一つですが、あくまで提案全体の一部です。
- RFQの目的: How much(いくらかかるか)の正確な価格を求めることにあります。「この仕様のものを、いくらで提供できますか?」という問いかけに特化し、純粋な価格競争を促します。
RFQの記載項目
RFQに記載すべき項目は、ベンダーが正確な価格を算出するために必要な情報に特化させるべきです。具体的には、「①対象製品・サービスの具体的な仕様」「②数量」「③納期・納品場所」「④見積に含めるべき費用項目の詳細」「⑤見積の前提条件」などが主要な構成要素となります。
見積に含めるべき費用項目(例:送料、保守費用など)を明記しておかないと、A社の見積には含まれ、B社の見積には含まれていない、といった状況が容易に発生します。これでは、後から追加費用を請求されるといったトラブルに繋がりかねません。
例えば、給与計算業務を外部の専門業者にアウトソーシングするケースでの記載項目例は以下の通りです。
| 大項目 | 主な記載項目 |
|---|---|
| ① 依頼概要 | ・給与計算アウトソーシング業務の見積依頼の件 |
| ② 業務範囲・仕様 | ・対象従業員数:〇〇名 ・給与体系:月給制、時給制 ・給与計算サイクル:月次、賞与(年2回) ・具体的な業務内容:勤怠データ集計、給与計算、給与明細発行・Web配布、年末調整業務 |
| ③ 見積依頼項目(費用内訳) | ・初期導入費用 ・月額基本料(〇〇名まで) ・超過人員単価(1名あたり) ・年末調整業務費用(1名あたり) |
| ④ 前提条件・その他 | ・契約期間:〇年間 ・見積の有効期限:〇日間 ・支払い条件(例:月末締め翌月末払い) |
RFQの記載項目を作成する上での最重要ポイントは、「曖昧さの徹底的な排除」に尽きます。価格に影響しうる全ての条件を、誰が読んでも同じ解釈ができるレベルまで具体的に明記することによって初めて、透明性の高い価格比較が実現し、最終的に有意義なコスト交渉を進めることができます。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
RFP・RFIの違いについてよくある質問
RFPとRFIの違いについて、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
- QRFIとRFP、どちらを最初に使うべき?
- A
原則として、RFI(情報提供依頼書)を最初に使うべきです。ベンダー選定のプロセスは、広い選択肢から段階的に絞り込んでいく「じょうご(ファネル)」のようなものです。
RFIで広く情報収集を行い、その上でRFP(提案依頼書)で具体的な提案を依頼するという流れが、最も合理的で失敗の少ない方法です。
市場にどのような製品や技術があるのかを十分に把握しないままRFPを作成してしまうと、「もっと優れた解決策やベンダーを見逃してしまう」という機会損失のリスクや、「期待する提案が集まらず、RFPを出し直す」といった手戻りのリスクが生じます。
最初にRFIで市場の全体像を把握することで、これらのリスクを回避し、より的確なRFPを作成するための土台を築けるのです。
ただし、以下のような限定的なケースでは、RFIを省略し、RFPから始めることもあります。
- 導入するシステムが明確な場合: 導入したい製品やシステムが業界で広く使われている標準的なもので、自社の要件も非常に明確な場合。
- 過去に類似プロジェクトの経験がある場合: 社内に知見が蓄積されており、信頼できる候補ベンダーのリストが既に存在する場合。
- プロジェクトの規模が小さい、または緊急性が高い場合: スケジュール的にRFIのプロセスを踏む時間的余裕がない場合。
- QRFIとRFPにおける評価基準はどのように決めるべき?
- A
RFIとRFPでは、その目的が根本的に異なるため、評価基準も全く異なるものを設定すべきです。RFIの評価基準は「情報提供の質とベンダーの将来性」に、RFPの評価基準は「課題解決能力と費用対効果」に、それぞれ重点を置いて設定します。
RFIのゴールは、自社の知識を深め、良いベンダー候補をリストアップすることであり、評価すべきは「いかに分かりやすく有益な情報を提供してくれたか」です。
一方、RFPのゴールは、自社の課題を最も効果的に解決してくれるパートナーを決定することであり、「要件をどれだけ満たしているか」「費用は妥当か」といった、より実践的な基準で評価します。
具体的な評価項目の違いは以下のとおりです。
RFIの評価基準 RFPの評価基準 評価の目的 情報収集とベンダーの可能性の把握 課題解決能力と費用対効果の比較検討 主な評価項目 ・情報の分かりやすさ、的確性
・企業の安定性、実績
・製品/サービスの将来性
・問い合わせへの対応の速さ、丁寧さ
・自社の課題への理解度・要件への適合度(機能)
・提案内容の具体的性、実現性
・プロジェクト管理体制、運用サポート
・費用の妥当性(初期・ランニング)
・導入スケジュールの現実性
まとめ
新しい勤怠管理システムや人事システムの導入は、企業の生産性や従業員満足度を左右する重要なビジネス上の意思決定です。その選定プロセスで用いられる「RFI」「RFP」「RFQ」という3つの文書を効果的に活用することが、後悔のないベンダー選定を実現する鍵となります。
最も重要なのは、原則として「RFI → RFP → RFQ」という段階的なプロセスを踏むことです。この流れは、広い情報収集から具体的な提案の比較、そして最終的な価格評価へと、意思決定の精度を徐々に高めていくための基本ステップです。
また、各段階の目的が異なるため、評価基準も明確に区別すべきです。RFIでは「情報の質」、RFPでは「課題解決能力」、RFQでは「価格の妥当性」と、評価の物差しを使い分けることで、客観的で公平なベンダー選定が実現します。
これらの文書は単なる依頼書ではなく、自社の課題を整理し、ベンダーとの共通理解を築き、プロジェクトを成功に導くための戦略的なコミュニケーションツールなのです。
これらを適切に使い分けることで、ベンダーミスマッチや予算超過といった調達の失敗を未然に防ぎ、導入後の運用まで見据えた正確な判断が可能となります。
また、評価基準についても、RFI段階では情報の網羅性や信頼性、RFPでは提案内容の具体性や要件適合度など、文書の目的に応じた項目を設けることが非常に重要です。
とはいえ、実際にどのベンダーを選べばよいのか、どんな機能が自社に適しているのかを判断するのは簡単ではありません。そんなときは、RFIやRFPを作成する前にあらかじめ各ベンダーの機能要件を比較できる「勤怠管理システムの選定・比較ヨウケン」の利用をおすすめします。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。