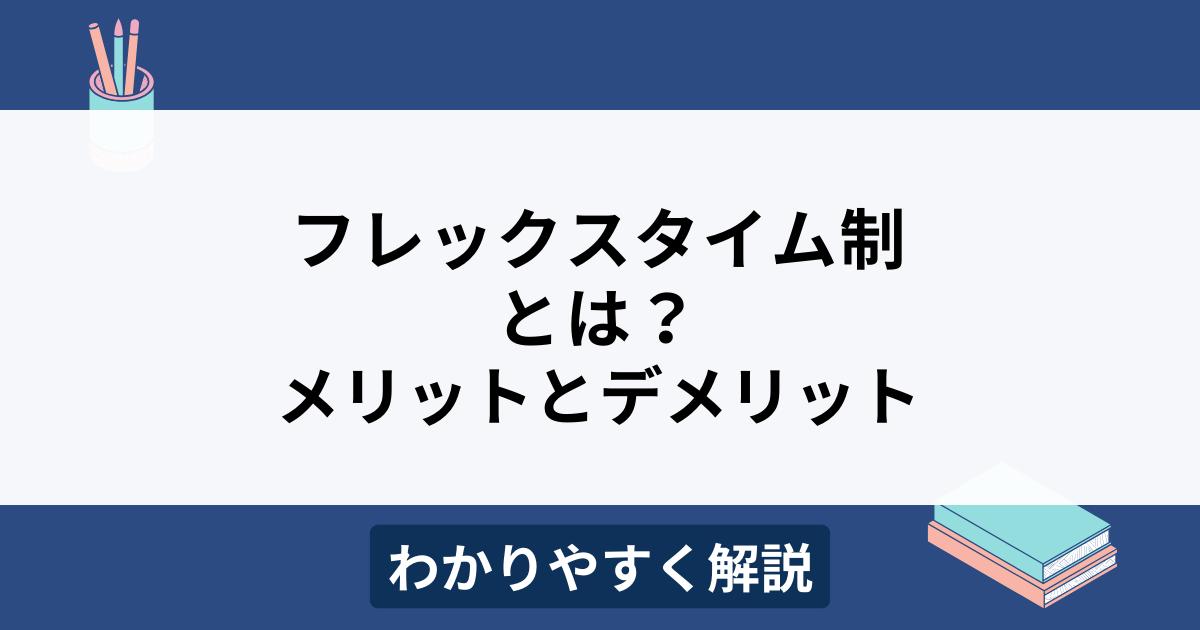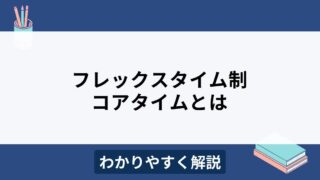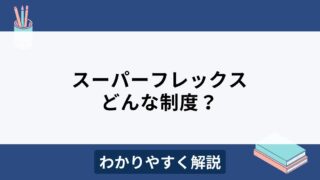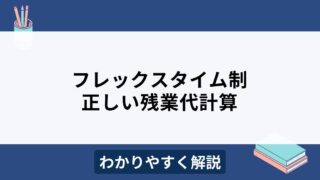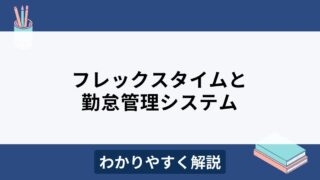フレックスタイム制はメリットも当然多い制度ですが、いざ導入して気付かされるデメリットも意外と多いものです。ただし、それぞれのデメリットには対応可能な解決策があります。デメリット対策を押さえて実行することで、フレックスタイム制のメリットを最大限に享受できます。
フレックスタイム制のように一旦導入すると撤廃が難しい制度は、そもそも事業場に制度がマッチするのか、デメリット対策が過度な負担にならないか、などを総合的に判断して導入を検討する必要があります。
この記事では、フレックスタイム制の基本から、メリット・デメリット、そして実際の導入手順までをわかりやすく解説します。
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制は変形労働時間制の一種です。変形労働時間制は4種類あり、他に1年単位の変形労働時間制、1ヶ月単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制があります。
しかし、フレックスタイム制は、他の3つの変形労働時間制とは大きく異なる性質を持つ労働時間制度です。
フレックスタイム制の概要
フレックスタイム制は、従業員が一定の期間内で所定の労働時間を自由に配分できる労働時間制度です。この制度の目的は、従業員が自身のライフスタイルや業務の状況に応じて、始業・終業の時刻を柔軟に設定できるようにすることにあります。
企業によっては、コアタイム(全員が出勤しなければならない時間帯)を設けることで、チーム間のコミュニケーションや情報共有を確保しています。
フレックスタイム制の目的
フレックスタイム制の導入目的は多岐にわたりますが、主に従業員のワークライフバランスの向上、生産性の向上、通勤ラッシュの回避などが挙げられます。従業員が自分の生活リズムに合わせて働けるようになることで、仕事とプライベートの両立がしやすくなり、結果として仕事の効率も上がると考えられています。
1-3. フレックスタイム制と裁量労働制の違い
フレックスタイム制と裁量労働制はしばしば混同されがちですが、両者には明確な違いがあります。フレックスタイム制は労働時間の配分を従業員が決定できる制度であり、裁量労働制は労働時間ではなく成果を基準にする制度です。
裁量労働制では、労働時間の長さではなく、担当業務の遂行に必要な時間を自己管理することが求められます。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
フレックスタイム制の仕組み
ここでは、フレックスタイム制で使われる用語とともに、その仕組みをご紹介します。
清算期間と総労働時間
フレックスタイム制における「清算期間」とは、労働時間が計算される期間のことを指し、通常は1ヶ月単位で設定されます。この期間内で、従業員は「総労働時間」を満たすように勤務する必要があります。総労働時間は、法定労働時間に基づいて企業が定めるもので、この時間を超えた場合は残業として扱われます。
コアタイム、フレキシブルタイム
コアタイムは、従業員が必ず出勤しなければならない時間帯を指し、フレキシブルタイムはその前後の時間帯で、従業員が自由に出勤・退勤できる時間帯です。
コアタイムの設定により、必要な会議や協働作業のための最低限の同時出勤時間を確保しつつ、フレキシブルタイムを活用することで個々の従業員の働きやすさを追求します。
時差出勤制度との比較
時差出勤制度は、従業員が出勤・退勤の時刻を数パターンから選択する制度であり、フレックスタイム制とは異なり、個々の従業員が日々の勤務時間を自由に設定することはできません。
時差出勤制度は主に通勤ラッシュの緩和を目的としており、フレックスタイム制ほどの柔軟性はありませんが、導入と管理が比較的容易です。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
フレックスタイム制のメリット
フレックスタイム制導入により得られるメリットは、主に以下の3つです。
- ワークライフバランスの向上
- 生産性の向上
- 離職率の低減
ワークライフバランスの向上
フレックスタイム制を導入する最大のメリットの一つは、従業員が自身のライフスタイルに合わせて働けるようになることです。これにより、家庭や趣味、自己啓発など、仕事以外の活動にも十分な時間を割くことが可能になり、ワークライフバランスの向上が期待できます。
生産性の向上
従業員が自分の体調や仕事の状況に合わせて勤務時間を調整できるため、無理なく効率的に仕事を進めることができます。これにより、全体としての生産性の向上が見込まれます。また、従業員の満足度が高まることで、仕事へのモチベーション向上にもつながります。
離職率の低減
フレックスタイム制は従業員にとって魅力的な働き方の一つであり、この制度を導入することで企業の魅力が高まり、優秀な人材の確保や離職率の低減に寄与します。従業員が長期にわたって安定して働ける環境を提供することは、企業にとっても大きなメリットとなります。.
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
フレックスタイム制のデメリット
フレックスタイム制導入により懸念されるデメリットは、主に以下の3つです。
勤務時間の管理の難しさ
フレックスタイム制では、従業員個々の勤務時間が不規則になるため、勤務時間の管理が難しくなります。これにより、労働時間の過不足や残業時間の把握が困難になる場合があり、適切な管理体制やツールの導入が必要になります。
コミュニケーションの課題
従業員の出勤時間がバラバラになることで、チーム内や部署間でのコミュニケーションが取りづらくなる可能性があります。これを解決するためには、コアタイムの設定やオンラインツールを活用した非同期コミュニケーションの促進が重要です。
顧客との連絡の難しさ
フレックスタイム制を導入すると、従業員が顧客と連絡を取る際に、通常の業務時間外である可能性があります。これにより、顧客からの信頼を損なうリスクがあり、顧客対応のためのルール設定やフレキシブルな対応が求められます。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
フレックスタイム制の導入と管理
具体的なフレックスタイム制の導入手順について、解説します。
準備
フレックスタイム制を導入する前には、従業員のニーズや業務の特性を把握するための社内調査が必要です。また、試行期間を設けて制度の運用を検証し、問題点を洗い出すことも重要です。
労使協定の締結
フレックスタイム制を正式に導入するためには、労使協定の締結が必要です。この協定には、清算期間や総労働時間、コアタイムとフレキシブルタイムの設定など、制度の詳細が記載されます。法的要件を満たすためにも、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。
社内周知
フレックスタイム制の導入後は、従業員に対して制度の内容や運用方法を丁寧に説明し、理解を深めてもらうことが重要です。また、定期的なフィードバックの収集と改善策の実施により、制度の運用を最適化していく必要があります。
フレックスタイム制と残業計算
フレックスタイム制における残業計算は、通常の労働時間制度とは異なります。清算期間終了時に総労働時間を超えた分が残業として認識され、残業代が支払われます。
従業員は自身の勤務時間を適切に管理し、不足分が発生しないよう注意が必要です。また、企業は残業が過度に発生しないよう、勤務時間の管理体制を整える必要があります。
フレックスタイム制の導入には、勤怠管理システムが必須
フレックスタイム制が導入された場合、労働者ごとに労働時間は全くバラバラになります。仮に、自社の現在の時間管理が手入力やExcelレベルの管理になっていれば、人事労務部門の業務負担が圧倒的に増える事態は避けられません。
勤怠管理システムを取り入れることで、全労働者の労働時間を一括管理できます。また、コミュニティツールと連携できるシステムを導入すれば、さらに社内のコミュニケーションロスの問題も解決可能です。
ぜひ、この機会に勤怠管理システムの導入を検討してみてください。勤怠管理システムの選定・比較ナビでは、多くの勤怠管理システムを紹介していますので、是非一度ご覧ください。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。