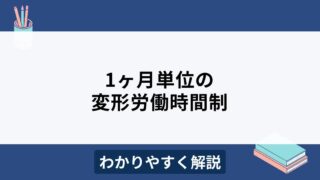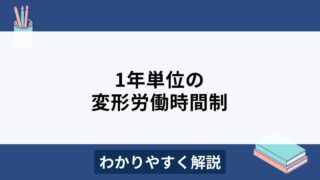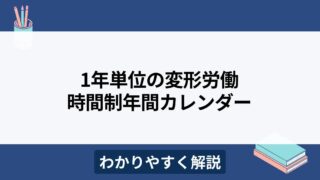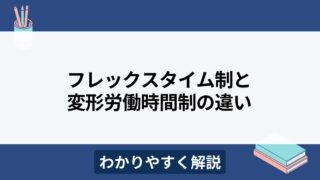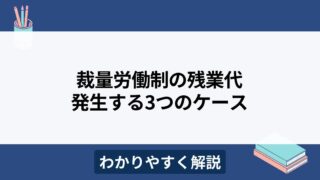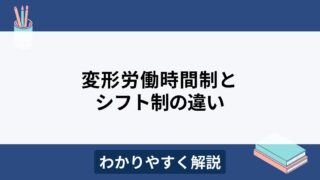変形労働時間制には4種類の制度があり、それぞれのメリット・デメリットは必ずしも同じではありません。具体的なケースを想定して導入を検討しましょう。
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
変形労働時間制とは
変形労働時間制とは、1ヶ月や1年単位で労働時間を柔軟に調整する制度です。労働基準法では法定労働時間(1日8時間、週40時間)が定められています。法定労働時間を超える労働は時間外労働になり、会社は従業員に割増賃金(残業代)を支払わなければいけません。
一方、変形労働時間制では、1年間単位、1カ月単位、1週間単位で労働時間を調整可能です。定められた範囲内でトータルの労働時間がおさまっていれば、週40時間または1日8時間を超えても時間外労働になりません。労働時間を弾力的に調整することで、従業員にとってもメリハリある労働が可能になります。
変形労働時間制の概要と目的
変形労働時間制の目的は、労働時間の柔軟な調整を可能にし、企業の生産性向上と従業員のワークライフバランスの実現を図ることです。従業員が長時間労働による健康障害を避け、プライベートな時間を確保できるようにするために設計されています。
企業にとっては、労働力の需要と供給を効率的にマッチングさせることができ、人件費の最適化が可能になります。
変形労働時間制は4種類ある
変形労働時間制には、以下の4種類があります。
- 1ヶ月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
- フレックスタイム制
これらは、企業の業種や業務内容、従業員の働き方の多様性に応じて選択できるように設計されています。たとえば、季節による業務量の変動が大きい業種には1年単位の変形労働時間制が適しています。また、月初や月末など月内で繁閑が変動する業種には1ヶ月単位の変形労働時間制が適しています。
変形労働時間制のメリット
変形労働時間制の導入による会社の大きなメリットは、残業代(時間外労働の割増賃金)を抑えられる点です。繁忙期では所定労働時間を多く確保でき、逆に閑散期では少なくするなど、繁閑に応じて労働時間を調整できるため、期間トータルの残業代を抑えることが可能です。
また、多様な働き方を推進している会社として、社内外に対してアピールできます。変形労働時間制の導入で、現代社会の要請に対応している会社としてイメージアップにもつながります。
さらに、従業員に対して閑散期の短時間労働や休暇の取得を推進し、リフレッシュしてもらい、会社全体のモチベーションアップが可能になります。
一方で従業員にとっては、繁忙期と閑散期の労働時間が変わることで、メリハリの利いた働き方が可能となるというメリットがあります。たとえば所定労働時間の短い閑散期には、家族サービスや趣味に充てる時間が増えるなど、ワークライフバランスの向上が期待できます。
変形労働時間制のデメリット
変形労働時間制のデメリットとしては、導入手続きや運用管理が複雑になることが考えられます。特に人事労務の労働時間管理や経理の賃金計算が非常に煩雑になります。
導入前は従業員の労働時間を、法定労働時間の基準に従って残業代を算出できたところ、変形労働時間制導入後は従業員ごと、あるいは部署ごとにバラバラの所定労働時間となります。よって従業員ごとに、個別に勤務カレンダーの設定、勤怠管理と残業代の計算が必要です。
また導入には、就業規則改定や労使協定などの労働法関係の手続が必要になります。手続きを進める際には、法的に問題がないかを十分にチェックして慎重に進めなければならないため、会社、特に人事労務部門にとっては非常に負担のかかる作業です。
さらに、労働法関係の手続き後は、就業規則や労使協定の内容などを従業員に周知しなければなりません。もし従業員への周知が徹底できないと、変形労働時間制に関して誤解が生じ、従業員の不満、不公平感やモチベーションダウンにつながります。
一方で従業員にとっては、同じ労働時間にもかかわらず残業代が減るというデメリットも考えられます。また社内全体で一律同じだった勤務時間が、導入後は部署や職種によって変わることで、部署間、社員間で不公平感を感じるケースも出てきます。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
1ヶ月単位の変形労働時間制とは
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の期間(変形期間と呼びます)を定めて労働時間を調整することで、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働が可能となる制度です。1ヶ月単位の変形労働時間制は、特に1か月間の中で繁忙期と閑散期の差が激しい業種や職種にメリットがあります。
たとえば、土日や祝日などの特定日や連休に来店客が多くなる傾向にある小売業、月初と月末に業務が集中しやすい会社の経理部門などに適していると言えるでしょう。
1ヶ月単位の変形労働時間制のメリット
1ヶ月単位の変形労働時間制は、会社にとっては繁忙期の残業代を抑えられ、従業員にとっては長時間働く日と早く帰れる日が事前に分かるので、予定が立てやすくメリハリのある労働が可能になるというメリットがあります。
1ヶ月単位の変形労働時間制では、1ヶ月以内の期間を平均し、週当たりの労働時間が40時間(あるいは44時間)以内であれば時間外労働になりません。週や日ごとの労働時間の上限がないので、思い切った所定労働時間の設定ができます。
1ヶ月単位の変形労働時間制のデメリット
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するには、就業規則の変更及び労働基準監督署への届出が必要になります。また、労働日の設定や残業代の計算などの作業が煩雑になるため、人事労務部門の負担が大きくなるというデメリットもあります。
さらに、一度決めてしまうと途中で変更できないため、取引先の事情で納期が変わった場合など、不測の事態が発生した場合に対応できないリスクもあります。設定した繁閑期と現実の繁閑期が逆転した場合、想定外の残業代が発生する恐れがあります。
1年単位の変形労働時間制とは
1ヶ月単位の変形労働時間制に対して、1年単位では、1日・1週ごとの労働時間や連続労働日数に上限があります。そのため、思い切った所定労働時間にはできませんが、極端な勤務シフトにはなりにくいのが特徴です。
1年単位の変形労働時間制のメリット
1年単位の変形労働時間制は、会社にとっては繁忙期に所定労働時間を多く確保し、逆に閑散期では少なくして、年間を通じて残業代を抑えるメリットがあります。また、従業員にとっては、閑散期に半休を含む時短労働や長期の休暇取得が期待できます。
1年間や季節で繁忙期と閑散期の差が激しい業種との相性が良いといえます。シーズン・オフシーズンがはっきりしている会社は、年間の労働計画が立てやすくなります。
1年単位の変形労働時間制のデメリット
1年単位の変形労働時間制の導入には、就業規則の変更、労使協定の締結と労働基準監督署への届出が必要です。そのため、1ヶ月単位よりもさらに手続きが煩雑になる点がデメリットといえます。
また、1年分まとめて勤務カレンダーを作れない場合は、何回かに分割して作成することになりますが、その度に作成の手間がかかります。
さらに、部署ごとに1年単位の変形労働時間制の適用に差がある場合、従業員への説明が不十分だと、従業員が不信感を抱きかねないため、従業員への周知・説明は重要です。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは
1週間単位の非定型的変形労働時間制は、他の変形労働時間制と比較し、期間が短いことが特徴です。1週間の労働時間40時間の範囲内で、各日の労働時間を設定できる制度です。ただし、1日の所定労働時間の上限は10時間となっています。
制度としては存在していますが、現実に採用している事業場はほとんどありません。
1週間単位の非定型的変形労働時間制のメリット
1週間単位の非定型的変形労働時間制は、1週間という短いタームの中で労働時間を調整できるため、週末が忙しくなる飲食店などのシフト管理に対応できるのがメリットです。
1週間単位の非定型的変形労働時間制のデメリット
1週間単位の非定型的変形労働時間制の対象事業場は、常時30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業と、非常に限定的になっています。導入には労使協定の締結と届出が必要で、導入後は1週間の各日の労働時間を、その週が始まる前に従業員に書面で通知しなければなりません。
適用対象である常時30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業に、専属の労務管理担当者が常駐している事例は少ないと考えられます。よって、現場の店長や支配人が毎週、日ごとの労働時間を設定し全従業員に書面で通知という業務をこなす必要があり、制度の運用は現実的ではないのが実態です。
また、一度日ごとの労働時間を決めてしまうと週半ばで変更できないため、柔軟な対応も難しいことも導入への障壁となっています。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
変形労働時間制と他の制度との違い
変形労働時間制と混同しやすい以下の制度について、その特徴や違いを解説します。
- フレックスタイム制
- 裁量労働時間制
- シフト制
変形労働時間制とフレックスタイム制との違い
フレックスタイム制は厳密に言えば、変形労働時間制の一種です。ただし、他の変形労働時間制とは根本的な考え方が異なるため、慣習的に分けて考えられています。
フレックスタイム制は、始業・終業時刻を従業員が自分で設定できるため、より柔軟な働き方に対応できるのが特徴です。フレックスタイム制において、必ず出勤すべき時間帯をコアタイム、従業員が自由に出退勤を設定できる時間帯をフレキシブルタイムと呼びます。
また、他の変形労働時間制が基本的に期間内の週平均労働時間で時間外労働を判断するのに対して、フレックスタイム制の場合は清算期間と呼ばれる対象期間内のトータルの総労働時間で時間外労働を判断する点も、大きな違いといえます。
変形労働時間制と裁量労働時間制との違い
裁量労働時間制は、実労働時間に関係なく、あらかじめ労使協定で定めたみなし労働時間分だけ労働したものと扱う制度です。裁量労働時間制においては、基本的に時間外労働が発生しませんが、職種や業務によらず導入できる変形労働時間制と異なり、対象となる業務が限られている点も大きな違いといえます。
なお、裁量労働時間制であっても、みなし労働時間の設定や働いた時間帯によっては割増賃金が必要となるケースもあるため、注意しましょう。
変形労働時間制とシフト制との違い
シフト制は、労働日や労働時間が一定でない勤務表に従って勤務するという外形は変形労働時間制と似ていますが、制度趣旨や効果はまったく異なります。シフト制はあくまでも勤務形態の一つにすぎず、変形労働時間制のように労働基準法に定められている制度ではありません。
変形労働時間制が、期間ごとに決められた枠の中で労働時間をやり繰りする制度であるのに対して、シフト制は複数の労働者による交代勤務であるため、労働時間の調整効果はありません。あくまでも勤務表に従って、法定労働時間を超えないように勤務するのが原則です。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
変形労働時間制についてよくある質問
変形労働時間制について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
- Q変形労働時間制は勝手に変更できる?
- A
変形労働時間制で定めた所定労働日や日ごとの所定労働時間を、会社都合で一方的に変更することは認められません。
変形労働時間制は、対象期間内における週の平均労働時間を一定時間に収めることを条件に、繁閑に応じた柔軟な労働時間の設定を可能とする制度であるため、一方的な事後変更を認めてしまうと、この制度趣旨そのものが失われてしまいます。
なお、大規模災害や設備の故障、経営統合など不測の事態によりやむを得ない事情がある場合は、例外的に変更が認められる可能性があるため、管轄の労働基準監督署に確認してみましょう。
- Q変形労働時間制における労働日数の限度は?
- A
1年単位の変形労働時間制においては、1年につき労働日数の上限は280日と定められています。年間カレンダーを作成する際は、所定労働日が280日を超えないよう注意しましょう。
また、1年単位の変形労働時間制では連続で労働させられる日数は原則6日までとなっています。ただし、労使協定で定めた特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる日数(つまり最大連続12日)まで可能です。
なお、1年単位の変形労働時間制以外の変形労働時間制については、上記のような総労働日数及び連続労働日数の制限はありません。
- Q変形労働時間制で途中入社・途中退社があったら?
- A
変形労働時間制を採用している事業場で、変形期間の途中に入退社する従業員がいた場合、他の従業員と同じように適用してしまうと不都合が生じるため、個別に対応する必要があります。
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合は、当注入退社があった月のみ変形労働時間制の対象外とするか、残日数で按分した時間(15日であれば「15 ÷ 7 ✕ 40 = 85.7時間)に収まるようにシフトを設定します。
1年単位の変形労働時間制の場合は、労働させた期間を平均し週40時間を超えて労働させた時間分の時間外割増賃金を支払う必要があります。具体的には、以下の計算式により割増賃金の対象となる時間を算出します。
実際に変形労働時間制を適用して労働させた期間中の実労働時間 - (40時間 ✕ 実際に変形労働時間制を適用して労働させた日数 ÷ 7)
変形労働時間制の導入には、勤怠管理システムが有効
変形労働時間制を導入する際は、煩雑な勤務カレンダーの管理、残業代の計算などマンパワーを要する労務管理への対応が不可欠です。
勤怠管理システムを導入することによって、変形労働時間制の運用・管理をシステム化し、人事労務管理全般の負担を軽減できます。
勤怠管理システムの導入を検討される企業の皆さまは、ぜひ一度「勤怠管理システムの選定・比較ナビ」をご覧頂き、自社にマッチした勤怠管理システムを探してみてください。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。