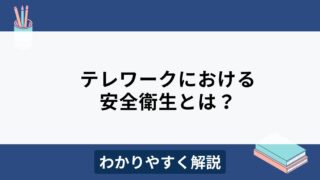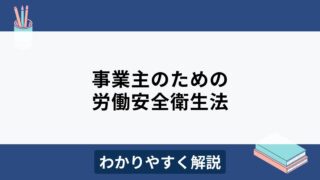労働安全衛生法(以下「安衛法」)は、労働者の安全と健康を確保するための重要な法律です。近年は働き方改革の一連の改正法の一つとして耳にする機会も増えてきました。
ただ、その条文は非常に読みづらく、事業主の方にはとっつきにくい内容となっています。この記事では、安衛法の目的や罰則、事業主として何をすべきかなどについて、わかりやすく解説します。
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
労働安全衛生法(安衛法)とは
労働安全衛生法(以下、「安衛法」)は、労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。
労働者災害補償保険法が労働災害が発生した場合の補償を目的としているのに対し、安衛法は労働災害の発生防止に主眼が置かれています。主に、労働者が安全で健康に働けるために事業主が講ずべき措置や責任について定めています。
安衛法は1972年に制定された法律ですが、元々労働基準法の一部に含まれていました。しかし、高度経済成長期に多発した労働災害を減らすため、労働者の安全・健康確保といった内容が、別の法律として設けられる形となりました。
労働者や企業を取り巻く環境は絶えず変化をしているため、労働安全衛生法は頻繁に法改正が行われます。近年は、長時間労働の是正やストレスチェックなどに関する改正が行われました。
労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則とは
労働安全衛生法施行令は、安衛法の規定を実施するために必要な細かいルールを定めた政令です。政令とは、法律を基にして内閣がルールを定めた法令を指します。
労働安全衛生規則は、施行令よりさらに細かい運用ルールについて規定した厚生労働省による省令です。省令とは、法律の運用ルールなどについて各行政省庁が定めた法令を指します。
労働安全衛生法の対象となる事業主・労働者
「労働者を使用し事業を行う者」つまり、労働者を一人でも雇う個人事業主及び法人が対象となります。
労働者の定義は、労働基準法第9条に規定する労働者と同義ですが、「同居の親族のみを使用している事業主に使用される労働者」及び「家事使用人」は適用外となっています。
また、日本船舶又は一部の外国船舶に乗り組む船員は「船員法」の適用を受けるため、安衛法の適用外となっています。
なお、2025年4月より、危険箇所等での作業に対する措置(退避、危険箇所への立入禁止等、火気使用禁止、悪天候時の作業禁止など)について、保護の対象範囲が自社の従業員に加えて、同じ現場で働くすべての人(一人親方や他社の従業員など)まで拡大されました。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
労働安全衛生法で、事業主が講ずべき措置とは
労働者の安全・健康を確保するため、事業主が講ずべき措置の範囲は多岐に渡ります。以下9つの措置をそれぞれ掘り下げて解説します。
- 安全衛生管理体制(管理責任スタッフの配置)
- 安全衛生委員会の設置
- 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
- 安全衛生教育の実施
- 就業制限措置
- 作業環境測定
- 快適な職場環境の形成のための措置
- 健康診断の実施
- ストレスチェックの実施
安全衛生管理体制(管理責任スタッフの配置)
業種や従業員規模に応じて、安全衛生管理のための専任スタッフを配置します。たとえば、常時50人以上の労働者を雇用する建設業の事業場の場合、安全管理者・衛生管理者・産業医などの選任が必要です。
| 管理者 | 役割 | 選任要件など |
|---|---|---|
| 総括安全衛生管理者 | 事業場の安全・衛生に関する業務を統括管理し、安全管理者・衛生管理者を指揮管理する | 3種類の業種区分に応じ、一定の従業員規模の事業場 |
| 安全管理者 | 作業場の保全措置など、労働者の安全に係る技術的事項を管理する | 常時50人以上の労働者を使用する一定の業種(建設業や製造業)の事業場 |
| 衛生管理者 | 作業場の衛生管理など、労働者の衛生に係る技術的事項を管理する | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 |
| 産業医 | 専門的な立場から労働者の健康管理について、指導・助言を行う医師 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 |
| 作業主任者 | 高圧室内作業などを行う労働者の指揮、機械の点検、安全装置の使用状況の監視など | 政令で定められた特定の作業を行う際、免許取得者や技能講習修了者の中から選任 |
| 統括安全衛生責任者 | 特定事業において複数の関係請負人の労働者が混在する場所での、労働災害防止に関する指揮・統括管理 | 建設業・造船業で同一の場所で複数の関係請負人による作業が行われる場合 |
| 安全衛生推進者(衛生推進者) | 安全管理者と衛生管理者に該当する業務を行う | 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場 |
安全衛生委員会の設置
「衛生委員会」は、労働者の健康被害防止を目的として、常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置が義務付けられています。こちらは業種による設置義務の違いはありません。
「安全委員会」は、職場の安全確保や労災被害防止を目的として、常時50人以上の労働者を使用する建設業や一部の製造業などの事業場、及び常時100人以上の労働者を使用する電気業やガス業などの事業場に設置が義務付けられています。
なお、安全委員会の設置が義務付けられている事業場においては、それぞれの委員会の設置に代えて「安全衛生委員会」の設置も認められています。
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
「機械等による危険」「爆発性・発火性の物質による危険」「電気・熱などエネルギーによる危険」を防止するための措置を講じる必要があります。労働災害が発生しないよう、機械・設備等の定期的な検査を行い、安全確保に努めなければなりません。
ボイラーやクレーンなど、危険な作業を必要とする一定の機械は特定機械等と呼ばれ、製造が制限されたり検査が義務付けられたりしています。
また、ガスや粉塵の発生を伴う作業や、放射線、高温・低温、騒音などの環境下で行う有害業務による健康障害を防止するための措置も講じなければなりません。
これらの個別具体的な取り扱いについては、「労働安全衛生規則」に細かく規定されています。
安全衛生教育の実施
「労働者を雇い入れたとき」及び「作業内容に変更があったとき」に、安全衛生教育を実施しなければなりません。具体的には、以下の内容に関して指導を行います。
- 機械や設備の取り扱い方法
- 作業開始時の点検
- 作業手順の確認
また、一定のフォークリフト運転業務や研削といしの取替え業務などの危険有害業務に従事する労働者に対して、業務に関する安全および衛生のための特別教育を実施しなければなりません。
さらに、製造業や電気業、ガス業などにおいて、現場を指揮する職長に対しては、新たに任命した際などに職長教育を実施する必要があります。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
就業制限措置
フォークリフトやクレーン操作など、政令で定める一定の業務に関しては、指定の免許や登録を受けた労働者にしか行わせてはなりません。また、当該業務に就く者は、作業中その資格を証する免許証などを携帯しなければなりません。
作業環境測定
有害な業務を行う屋内作業場等においては、必要な作業環境測定を行い、その結果を保管しなければなりません。一例を挙げると、アスベストを扱う作業場においては、石綿濃度を計測し、測定結果を40年間保存しなければなりません。
快適な職場環境の形成のための措置
作業環境整備として、作業に応じた照度基準を守る、騒音・振動を防止するなどの措置が求められます。
また、労働者の疲労・ストレス軽減のために休憩室や仮眠室などの疲労回復施設の設置、男女別トイレの適切な設置、職場の清掃などにも努めなければなりません。
健康診断の実施
健康診断については、新規雇用時や定期検診など、実施時期や対象者が以下のように決められています。
| 健康診断の種類 | 対象者 | 実施時期 | |
|---|---|---|---|
| 一般健康診断 | 雇入時の健康診断 | 常時使用する労働者 | 雇入れの際 |
| 定期健康診断 | 常時使用する労働者 | 1年以内に1回 | |
| 特定業務従事者の健康診断 | 特定業務に常時従事する労働者(特定業務従事者) | 特定業務への配置替えの際 6カ月以内に1回 |
|
| 海外派遣労働者の健康診断 | 海外に6カ月以上派遣する労働者 | 海外に6カ月以上派遣する際 帰国後に、国内業務に就いてもらう際 |
|
| 給食従業員の検便 | 事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者 | 雇入れの際 配置替えの際 |
|
| 特殊健康診断 | 法定の有害業務に従事する労働者 | 雇入れの際 配置替えの際など |
|
健康診断実施中の賃金は?
一般健康診断実施中の賃金は、労使間の協議によって定めることができますが、できる限り支払うのが望ましいとされています。
対して、特殊健康診断は、業務遂行との関連性が高く、その実施中の時間は労働時間とみなされるため、当然に賃金を支払う必要があります。
ストレスチェックの実施
2015年12月1日より、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、ストレスチェックの実施が義務付けられました。また、常時使用する労働者が50人未満の事業場においても、実施に努めることとされています(努力義務)。
メンタルヘルス不調を防止するため、1年に1回ストレスチェックを実施し、その結果に基づく医師の面接指導などの措置を取る必要があります。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
労働安全衛生法についてよくある質問
労働安全衛生法について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
- Q労働安全衛生法に違反した場合の罰則は?
- A
安衛法は労働者の生命の安全に関連する法律であることから、多くの規定について違反した場合の罰則が定められています。以下に代表的なものをご紹介します。
該当規定 違反内容 罰則 製造等の禁止 労働者に重度の健康障害を生ずる物(政令で定めるもの)を、製造・輸入・譲渡・提供・使用した 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 作業主任者 特定の危険作業を行う際の作業主任者の選任を怠り、または作業主任者による作業監視を怠った 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 事業者の講ずべき措置等 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を怠った 安全衛生管理体制 安全管理者や衛生管理者の選任を怠り、またはそれらの者による必要な管理を怠った 50万円以下の罰金 安全衛生教育 労働者を雇い入れたときなどに必要な安全衛生教育を怠った 労働安全衛生法違反時の罰則 違反行為をした違反者本人のほか、法人または個人事業主も同時に罰せられる可能性もあります(両罰規定)。
- Q労働安全衛生法は2025年4月からどう変わった?
- A
2025年4月に労働安全衛生法の改正があり、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う自社の従業員以外の人に対しても、自社の従業員と同等の保護が図られるよう、必要な措置を実施することが事業者に義務付けられました。
改正法の主なポイントは以下の2点です。
- 危険箇所等において事業者が行う退避や立入禁止等の措置の対象範囲を、作業場で何らかの作業に従事する全ての者に拡大
- 危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等に対する周知の義務化
2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、以下の1、2を対象とする保護措置が義務付けられます|厚生労働省
労働安全衛生法は過重労働防止のカギ
労働安全衛生法は比較的改正が多い法律で、社会の要請が反映されやすいと言えます。労働安全衛生法の遵守は重要です。労働者の安全と健康保護=結果的に会社を守ることにもつながります。
労働時間を正確に把握するためには、勤怠管理システムの導入が有効です。労働時間・時間外労働・休日労働の時間数など、勤怠管理に必要なデータを自動で集計します。システムには常に最新のデータが反映されるため、管理職はすぐに部下の勤怠状況を把握できます。
労務担当者と何度もやりとりを重ねる必要はありません。一方、労務担当者も煩雑な計算業務を自動化できるため、他の作業に時間を割けます。
「勤怠管理システムの選定・比較ナビ」をご利用いただくと、必要な要件を満たしている選択肢から、自社に最もマッチングするシステムを探し出せます。低コストでハイスペックな機能を搭載している勤怠管理システムを多数扱っている点も、嬉しいポイントです。
勤怠管理システムの導入を検討している方は、勤怠管理システムの選定・比較ナビを是非ご利用ください。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。