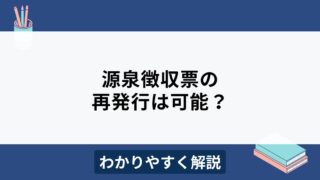- 「源泉徴収票って、確定申告に絶対必要なんですか?」
- 「源泉徴収票をなくしたんですけど…」
- 「転職してきたのですが、前の会社の源泉徴収票はどうすれば…?」
特定の時期になると、多くの事業主や労務担当者が、源泉徴収票と確定申告の関係に関する問い合わせ対応に頭を悩ませています。特に、アルバイトや副業、転職といった多様な雇用形態が増える現代においては、従来通りの処理では対応しきれないケースが増加中です。
確定申告において、源泉徴収票は「必要書類」とされる一方、条件によっては「不要」となるケースもあるため、誤って案内してしまえば、従業員を混乱させかねません。
この記事では、確定申告における源泉徴収票の必要性や例外的な取り扱い、事業主・労務管理者が押さえておくべき実務上のポイントを、わかりやすく解説します。
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
源泉徴収票と確定申告の関係
事業者にとって「源泉徴収票」を正確に作成し従業員へ交付することは、法律で定められた重要な義務です。そして、この源泉徴収票は、従業員が「確定申告」を行い、年間の所得税を正しく納税するための根拠書類として使用されます。
多くの会社員は、会社が行う「年末調整」によって所得税の計算と納税が完了しますが、年間の給与収入が2,000万円を超える方や、副業所得が20万円を超える方、あるいは医療費控除など年末調整では対応できない控除を適用したい方などは、従業員自身による確定申告が必要となります。
これらの従業員にとって、会社から交付される源泉徴収票は、確定申告書を作成するための公的な証明書となるのです。源泉徴収票の発行は単なる事務手続きではなく、従業員の適正な納税を支えるという重要な役割を担っていることを、まずは押さえておきましょう。
源泉徴収票とは
源泉徴収票とは、事業者が1年間に従業員へ支払った給与・賞与の総額(支払金額)と、その給与から徴収(天引き)した所得税の合計額(源泉徴収税額)などを記載し、その内容を証明する書類です。所得税法により、企業や事業者は従業員に対してこの書類を交付する義務があります。
には「支払金額」「給与所得控除後の金額」「源泉徴収税額」「社会保険料の控除額」などが記載されており、年末調整の結果を含めて税務署や本人に報告する役割を果たします。
また、源泉徴収票は税務手続きだけでなく、住宅ローン審査や賃貸契約など、従業員の生活における収入証明書としても広く利用されます。そのため、従業員から再発行を依頼された場合は迅速に対応することが求められます。
確定申告とは
確定申告とは、個人が1年間(1月1日~12月31日)の全ての所得と、それにかかる所得税の最終的な税額を自ら計算し、税務署へ報告・納税する一連の手続きを指します。
日本の所得税は、納税者が自ら税額を計算し申告する「申告納税制度」を基本としています。会社が毎月の給与から天引きしている源泉徴収税額はあくまで概算の前払いに過ぎず、この確定申告を通じて正しい税額を算出し、過不足を精算する必要があるのです。
年収が2,000万円を超える人、年の途中で退職して年末調整を受けていない人、副業での収入が20万円を超える人など、所得税法で定められた条件に該当する場合は、確定申告が義務づけられています。
一方、申告義務がない場合でも、医療費控除やふるさと納税による寄附金控除などを申告したいときは、「還付申告」として自発的に申告することで、所得税の一部が戻ってくる可能性があります。
給与所得・年末調整との関係
「年末調整」とは、源泉徴収された所得税の過不足を年末に雇用主が自動的に調整する制度であり、原則として会社員はこれで税の精算が完了します。所得税法第190条に基づき、企業には年末調整を行う義務があります。
そして、この年末調整を正確に行った結果を最終的に取りまとめたものが「源泉徴収票」となります。いわば、年末調整は「企業が行う確定申告の代行手続き」と言えるでしょう。
ただし、副業がある、年の途中で退職した、医療費控除や住宅ローン控除を申請したいといったケースでは、年末調整では対応できないため、別途確定申告が必要になります。
具体的な流れは以下の通りです。
- 各種申告書の回収(11月頃): 従業員から「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」などを回収します。
- 年税額の計算(12月頃): 1年間の給与総額を確定させ、申告書情報をもとに所得控除を適用し、最終的な所得税額を計算します。
- 過不足の精算(12月または1月の給与): 毎月の源泉徴収税額の合計と最終税額を比較し、差額を給与で還付または徴収します。
- 源泉徴収票の作成・交付(翌年1月末まで): 上記の計算結果を正確に反映した源泉徴収票を作成し、全従業員へ交付します。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
源泉徴収票は確定申告に不要?必要なケースは?
源泉徴収票は、原則として確定申告時に必要な書類ですが、すべての人が提出を求められるわけではありません。所得の状況や申告の目的によっては、源泉徴収票を提出せずに申告が完了する場合もあります。
たとえば、年末調整で所得税が精算されており、追加の控除や収入がない場合には、確定申告そのものが不要です。また、e-Taxを使用し、マイナポータルとの連携を利用している場合には、源泉徴収票の情報が自動で反映されるため、紙の提出は求められません。
一方、控除申請・副業・転職・医療費控除などによって、年末調整だけでは対応できない人については、源泉徴収票が必須となり、正確な記載がなければ申告が受理されないこともあります。
そのため、労務管理者は従業員ごとに「申告が必要か」「源泉徴収票が必要か」を見極めたうえで、的確なサポート体制を整えることが重要です。特に副業者や短期離職者に向けての情報提供は、税務トラブルの未然防止につながります。
なぜ源泉徴収票が不要な場合があるのか
確定申告時に源泉徴収票の「添付」が不要とされた主な理由は、行政手続きの効率化にあります。具体的には、①事業者から税務署へ既に情報が提供されていること、そして②e-Tax(電子申告)の普及により手続きがデジタル化したこと、の2点が大きな要因です。
令和4年度以降はマイナポータル連携の普及が進み、e-Taxを使用することで源泉徴収票の情報が自動で取得・転記されるケースも増えています。これにより、物理的な書類提出は不要になる場合があります
まず、事業者は毎年1月末までに、前年の給与支払情報をまとめた「法定調書合計表」を税務署に提出しています。これにより、税務署は多くの納税者の所得情報を事前に把握しています。
次に、国が推進するe-Taxでは、申告者が手元の源泉徴収票を見ながら金額を直接入力するため、紙の書類を物理的に提出する必要がありません。さらにマイナポータル連携を利用すれば、源泉徴収票の情報を自動で取得・入力することも可能になり、添付の必要性はさらに低下しています。
源泉徴収票が必須となるケース
確定申告で源泉徴収票の提出が必須となるのは、主に年末調整が未実施または不十分な場合や、給与以外の所得がある場合です。これらのケースでは、確定申告書への正確な記入と、税務署による審査に必要な証拠書類として、源泉徴収票の提出が求められます。
所得税法第121条・第226条により、給与支払者は源泉徴収票の交付義務があり、確定申告においては所得税の課税標準の算出に必要な証明書類として位置づけられています。以下のようなケースでは、原則として源泉徴収票が必要です。
- 年の途中で退職し年末調整を受けていない
- 2か所以上の会社から給与を受け取っている(副業含む)
- 年収が2,000万円を超えており、年末調整対象外
- 医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除などの申請を行う
- 源泉徴収された税金の還付申請をする
特に注意すべきは、複数の源泉徴収票を合算して申告しなければならないケースです。例えば本業と副業の両方で源泉徴収票が発行されている場合、それぞれの「支払金額」「源泉徴収税額」「所得控除額」を正確に合算し、申告書に記載する必要があります。
また、e-Taxで自動取得ができない企業に勤めていた場合や、年末に間に合わなかった場合は、紙の源泉徴収票を自分で管理・提出する必要があります。自動化が進んでも、源泉徴収票の原本が手元にあることは重要です。
アルバイト・副業・転職時の注意点
アルバイト・パート、副業、転職(中途退職)といった状況にある従業員は、確定申告が必要になる可能性が高いといえます。そのため、事業者としては、これらの従業員に対する源泉徴収票の交付について、特に注意を払う必要があります。
| 対象者 | 注意すべきポイント |
|---|---|
| アルバイト・パート | 複数の勤務先を掛け持ちしている可能性があるため、年間の支払金額の大小にかかわらず、給与を支払った全従業員に源泉徴収票を交付します。 |
| 副業をしている従業員 | 主たる給与と副業所得を合算して申告するため、自社発行の源泉徴収票が必ず必要になります。 |
| 中途退職者 | 退職後1ヶ月以内を目安に、速やかに源泉徴収票を交付します。これは退職者との間で最もトラブルになりやすい点の一つであり、迅速な対応が求められます。 |
これらの従業員にとって、企業が発行する源泉徴収票は、彼らが納税義務を果たすための生命線とも言えます。それぞれの状況を理解し、迅速かつ正確な書類交付を徹底することは、企業のコンプライアンス遵守はもちろん、無用なトラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。
フリーランスの方は、こちらの記事を参照ください。
【フリーランス必見】確定申告でもう困らない!申告の手順を徹底解説|日本デザイン
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
源泉徴収票の見方・各項目の意味
事業者や労務管理者にとって、源泉徴収票に記載されている各項目の意味を正確に理解することは、誤った申告を防ぐうえでも極めて重要です。各項目は給与計算と所得税法に密接に結びついており、その意味を従業員に説明できることは、企業の信頼性構築にも繋がります。
これらの数字を正しく読み取れないと、税金の過不足が発生する可能性があります。たとえば控除額の入力漏れは還付額の減少に直結し、税務調査の対象になることもあります。
労務管理者としては、従業員に対して「源泉徴収票の内容がどのように申告に使われるか」「どこを確認すべきか」を教育・周知することが大切です。
支払金額・所得税額・控除額などの見方
源泉徴収票の中で特に重要な項目は、「①支払金額」「②給与所得控除後の金額」「③所得控除の額の合計額」「④源泉徴収税額」の4つです。これらは所得税額を算出するための一連の流れを示しており、企業の担当者はこの計算ロジックを理解しておく必要があります。
所得税の計算は、所得税法に定められた以下の流れで行われ、源泉徴収票の主要項目もこの流れに沿っています。
- 支払金額(いわゆる年収)から、法律で定められた給与所得控除を差し引くと、「給与所得控除後の金額」が算出されます。
- そこから、社会保険料や生命保険料、扶養控除といった従業員個々の所得控除の合計額を差し引き、課税対象となる「課税所得金額」を求めます。
- 最終的に、課税所得金額に所得税率を掛けて計算されたものが、年間の納税額である「源泉徴収税額」となります。
これらの項目はすべて連動しているため、一つでも計算を誤ると最終税額に影響が出ます。特に、従業員から提出された申告書に基づき計算する「所得控除の額の合計額」は、誤りが発生しやすいポイントです。発行前には各項目に誤りがないか、入念に確認する体制を整えることが企業の責任として求められます。
転職者の場合の記載内容
年の途中で入社した転職者(中途採用者)の年末調整を行う場合、その従業員が前職の会社から受け取った源泉徴収票の内容を合算して、年間の所得税を計算する必要があります。そして、自社が発行する源泉徴収票には、その合算した内容を記載しなければなりません。
所得税法では、年末調整はその年に支払われた給与の総額を対象に行うことと定められているため、その年の最終的な給与支払者となった企業が、年間の所得情報をすべて集約して正しい税額を計算する義務を負います。
労務担当者様が転職者の年末調整を行う際の具体的な手順は、以下の通りです。
- 前職の源泉徴収票を提出してもらう: 対象者から、その年に入社前に退職した全ての会社の源泉徴収票を提出してもらいます。
- 前職分を合算して年末調整を計算: 自社での支払額・社会保険料・源泉徴収税額に、前職の源泉徴収票に記載された各金額を合計して、年税額を算出します。
- 源泉徴収票への記載:
- 「支払金額」などの各欄には、前職分と自社分を合算した金額を記載します。
- 「摘要」欄に、前職の情報を必ず記載します。 これは必須の記載事項であり、前職の会社名、支払金額、社会保険料額、源泉徴収税額、退職年月日を転記します。
この「摘要」欄への前職情報の記載は、忘れやすく、かつ重要な法的要件です。転職者の年末調整を正しく行うことは、その年の最終給与支払者としての重要な責務となります。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
確定申告書への転記方法
源泉徴収票をもとに確定申告書を作成する際には、記載されている金額や項目を正確に所定の箇所へ転記する必要があります。特に誤転記が多いのは「支払金額」「所得控除額」「源泉徴収税額」などであり、これらを間違えると、税額計算が誤り、還付金の減額または追徴課税の原因になることもあります。
確定申告書は、所得税法に基づき様式が定められており、源泉徴収票の項目と論理的に対応するように設計されています。これは、従業員による自己申告の正確性を担保し、税務署の確認作業を効率化するためです。
労務管理者としては、源泉徴収票の交付だけでなく、その内容が確定申告書のどこに転記されるのかを従業員に説明し、必要に応じてサポートを提供することが重要です。
源泉徴収票から確定申告書へ正しく転記する方法
源泉徴収票の主要4項目である「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」は、確定申告書の様式に設けられた各欄へ、それぞれ一対一で対応しています。具体的には、源泉徴収票の各項目は、確定申告書(第一表)の以下の欄に転記します。
- 「支払金額」 → 収入金額等の「給与(カ)」
- 「給与所得控除後の金額」 → 所得金額等の「給与(1)」
- 「所得控除の額の合計額」 → 所得から差し引かれる金額の各控除欄
- 「源泉徴収税額」 → 税金の計算の「源泉徴収税額(48)」
特に「所得控除の額の合計額」については、確定申告書では合計額だけでなく、社会保険料控除や生命保険料控除といった個別の控除額をそれぞれ記入する必要があります。これらの内訳は、源泉徴収票の中段〜下段に記載されていますので、そちらを参照するよう従業員に案内すると親切です。
給与計算システムなどの活用
確定申告における源泉徴収票の転記ミスや記入漏れを防ぐために、近年は給与計算システムやクラウド型会計ソフトの活用が急速に進んでいます。これらのシステムを労務管理に取り入れることで、源泉徴収票の自動作成・確認・再発行が可能になり、業務の正確性と効率が大きく向上します。
近年の給与計算システムは、毎年のように改正される所得税法や社会保険料率の変更に、アップデートを通じて自動で対応します。これにより、担当者が法改正の細部を見逃すといった人為的ミスを防ぎ、常に法令に準拠した計算を担保できるのです。
具体的なメリットは多岐にわたります。
- 正確性の向上: 年末調整の複雑な計算を自動化し、ヒューマンエラーを抜本的に削減します。
- 業務効率の改善: 源泉徴-収票や法定調書合計表といった各種書類の作成が自動化され、担当者の作業負荷を大幅に軽減します。
- コンプライアンス強化: 法改正への自動追従により、常に最新の状態で法令を遵守できます。
- 従業員サービス向上: 多くのシステムでは、従業員がWeb上で給与明細や源泉徴収票を閲覧・ダウンロードでき、再発行などの問い合わせ対応工数を削減できます。
給与計算システムの活用は、単なる業務効率化ツールにとどまらず、企業の税務・労務に関するコンプライアンス体制を強化し、計算ミスなどのリスクを最小化するための戦略的な投資と言えるでしょう。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
源泉徴収票と確定申告についてよくある質問
源泉徴収票と確定申告について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
- Q税務署への提出が必要な「法定調書合計表」とは?
- A
法定調書合計表とは、給与や報酬などの支払に関して、税務署へ提出する「法定調書(源泉徴収票や支払調書など)」の提出枚数と金額の総合計をまとめた書類です。所得税法第226条および、国税通則法施行規則第12条に基づき、事業主に提出義務があります。
具体的には、以下のような書類の提出をともなう場合、その添付書類として合計表の提出が必要です。
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 報酬・料金等の支払調書(士業・外注等)
- 不動産の使用料等の支払調書 など
提出の対象者は「前年中に報酬や給与を支払ったすべての法人および個人事業主」で、毎年1月31日が提出期限です。
なお、e-Taxを使った電子提出の場合でも、合計表の作成は必須です。また、合計表の提出を忘れると、個別の源泉徴収票や支払調書の内容が税務署で確認できず、調査対象になる可能性もあります。
- Q確定申告に必要な書類は?
- A
確定申告を正しく行うためには、所得の種類や申告内容に応じた書類を準備する必要があります。必要書類は申告の種類によって異なりますが、給与所得者の場合は以下が基本的な書類となります。
分類 書類名 説明 所得を証明する書類 源泉徴収票 (副業が事業所得なら)収支内訳書など 控除を証明する書類 社会保険料の支払証明書
保険控除証明書(生命保険料控除、地震保険料控除 等)
医療費控除の明細書
寄附金受領証明書(ふるさと納税など)各種控除適用のために必要 その他 本人確認書類(マイナンバーカード等)
還付金を受け取るための本人名義の口座情報e-Tax利用や本人確認などのため
- Q従業員から源泉徴収票の再発行を依頼されたら?
- A
源泉徴収票は、労働者本人が確定申告や各種手続きに使用する重要書類であるため、紛失や未着により再発行を依頼されることはよくあります。企業は、従業員の求めに応じて源泉徴収票を再発行する義務があります(所得税法第226条第1項、同法施行規則第75条)。
再発行の基本的なフローは以下のとおりです。
- 本人確認の実施(身元確認書類の提出)
- 発行対象期間の確認(例:令和6年分)
- 給与データ・年末調整情報の照合
- 再発行書類に「再発行」と明記
- 郵送対応の場合は宛先確認・封緘処理を徹底
補足として、従業員本人以外からの依頼(例:税理士や親族)については、委任状の提出を求めることが望ましいです。また、マイナンバー法に基づく個人情報保護の観点からも、取り扱いには慎重さが求められます。
企業によっては、クラウド型給与システムや人事ポータルを利用しており、従業員が自分で源泉徴収票をダウンロードできる仕組みがある場合もあります。これにより、発行依頼の対応業務を削減できます。
まとめ
本記事では、企業の事業主様および労務管理担当者様が知っておくべき「源泉徴収票」と「確定申告」の関連業務について、網羅的に解説しました。
事業者にとって、全従業員に対し正確な源泉徴収票を発行することは、所得税法に定められた重要な義務です。これは、従業員が自身の所得を証明し、確定申告によって納税義務を果たすための根拠となる、極めて重要な書類です。
これらの間違いが許されない一連の給与計算・年末調整業務を効率化し、その正確性を担保するためには、信頼できる給与計算システムの活用が極めて有効です。
そして、その正確な給与計算の全ての基礎(インプット)となるのが、従業員一人ひとりの日々の「勤怠データ」です。残業時間や休日出勤、各種休暇の管理といった勤怠情報に誤りがあれば、それは給与額の誤算、ひいては源泉徴収額や社会保険料の誤りへと直結してしまいます。
ミスのない労務管理体制の基盤を固め、問題の源流を断つためには、まず自社の就業規則や働き方に最適な勤怠管理システムを選定し、労働時間を正確に把握することが不可欠です。
勤怠管理システムの選定・比較サイト「勤怠管理システムの選定・比較ヨウケン」では、多種多様なシステムの機能や料金を客観的に比較し、貴社の課題を解決する最適なツールを見つけることができます。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。