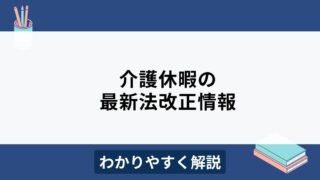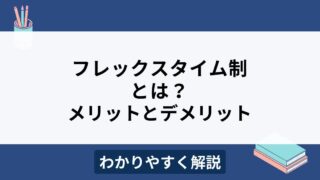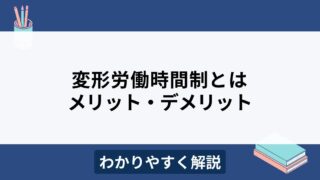2025年4月より「子の看護休暇」は適用範囲が拡張され、名称も「子の看護等休暇」と改められます。これに伴い、企業においても就業規則等の改正が必要となります。
この記事では、事業主や管理者の方向けに、子の看護等休暇の改正内容や前回の改正時より認められている時間単位取得について、わかりやすく解説します。
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
子の看護等休暇とは
子の看護等休暇とは、小学校第三学年修了前の子どもが怪我や病気に掛かった場合の看護などのために休暇の取得を申請できる制度です。なお、今回の改正によって対象となる子の範囲や取得事由などが変更となっているため、のちほど個別に解説します。
また、今回の改正は同じ育児・介護休業法に規定されている介護休業も対象となっています。介護休業の改正については、以下の記事をご覧ください。
子の看護等休暇の対象となる労働者
育児・介護休業法第16条の2には「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」とありますが、わかりやすく言うと「小学校3年生が修了するまでの子」を養育する労働者が対象となります。対象となる子は実子に限らず、養子であっても対象となります。
(子の看護休暇の申出)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16条の2|法令検索 e-Gov
第十六条の二 九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。)を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(以下「子の看護等休暇」という。)を取得することができる。
改正前は、「小学校就学の始期に達するまでの子」が対象となっていたため、今回の改正により対象となるこの年齢が延長されたことになります。
なお、「1週間の所定労働日数が2日以下の労働者」については、労使協定を締結することにより対象外とすることが可能です。改正前は、「入社後6ヵ月未満の労働者」も労使協定で除外可能でしたが、今回の改正により、この要件は撤廃されました。
子の看護等休暇の取得日数
子の看護等休暇の取得日数は1年度につき5日で、対象となる子を2人以上養育している場合は1年度につき最大10日まで取得可能です。取得日数については、今回の改正で変更がありませんでした。
なお、対象となる子の人数に応じて比例増加するわけではないため、3人以上養育していたとしても、最大取得日数はあくまでも10日となります。
子の看護等休暇の取得事由
改正点を踏まえた子の看護等休暇の取得事由は以下のとおりです。
- 負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話
- 疾病の予防を図るために必要な予防接種または健康診断を受けさせる子の世話
- 感染症の予防上必要な臨時休校や学級閉鎖などの対象となった子の世話
- 子の入園式、卒園式または入学式への出席
今回の改正で、3.と4.が新たに取得事由として追加され、より広い範囲で認められることになりました。なお、4.については学校の式典等が対象であるため、運動会や授業参観などは認められないとされています。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
子の看護休暇の時間単位取得とは
2021年1月の改正法施行により、それまで1日単位もしくは半日単位のみ認められていた子の看護休暇が、時間単位で取得可能になりました。状況に応じて柔軟な使い方ができるため、仕事への影響を抑えながら積極的に利用できるようになっています。
また、本改正に伴い、従来は取得が認められなかった「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者」も、子の看護休暇を取得可能となりました。
「時簡単位」とは1の整数倍であり、たとえば「2時間単位で認める」というような規定は認められません。一方で、「30分単位で認める」という規定は、法の内容をより柔軟にした措置であるため、差し支えありません。
なお、時間単位で取得することが困難な業務に従事する労働者については、労使協定を締結することにより時間単位取得の対象外とすることが可能です。
1日に取得可能な時間は?
基本的には、1日の所定労働時間に満たない時間まで取得が可能です。1日の所定労働時間が8時間の場合は、最大7時間まで利用できます。出勤して1時間働いた段階で子どもの体調不良が発覚した場合、子の看護休暇を利用して子どもの看病に専念できます。
子の看護休暇の取得時間数が一日の所定労働時間に達すると、1日としてカウントします。1日8時間勤務の場合、4日連続で2時間利用した労働者は子の看護休暇を1日分利用したとカウントされるため、残りの休暇数は4日となります(対象となる子が2人以上の場合は9日)。
シフト制などで日によって所定労働時間が変わる場合は、1年間における1日あたりの平均所定労働時間が基準となります。また、1年間における総所定労働時間数が決まっていない場合には、所定労働時間数が決まっている期間における1日平均所定労働時間数が基準となります。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
子の看護休暇の時間単位取得についての実務のポイント
年度途中で短時間勤務に切り替わった場合やフレックスタイム制を採用している場合は、注意が必要です。実務上起こりうる以下のケースについて、それぞれの適切な取り扱いを解説します。
- 1日の所定労働時間が時間単位ではない場合
- 途中で所定労働時間が変わった場合
- 子の看護休暇の時間単位取得が休憩時間にかかる場合
- フレックスタイム制における取り扱い
- 変形労働時間制における取り扱い
1日の所定労働時間が時間単位ではない場合
1日の所定労働時間が7時間30分など、時間単位に満たない端数がある場合は、時間単位に切り上げて取得単位をカウントする必要があります。
たとえば、所定労働時間が7時間30分の場合は分単位の時間を切り上げて8時間とみなし、かりに7時間の取得があった場合は、残りは4日と1時間ということになります。
途中で所定労働時間が変わった場合
年度途中で短時間勤務に切り替わるなどして所定労働時間が変わった場合は、変更された時間に比例して取得可能な時間数が変動します。この場合も、変更後の時間に生じた端数は、、時間単位に切り上げる必要があります。
たとえば、取得可能日数が「4日と4時間」残っている労働者が、時短勤務となり1日の所定労働時間が7時間から5時間に変更となった場合は、次のように扱います。
4時間 × (5時間 / 7時間)=2.857時間
端数を切り上げて3時間とし、残りは「4日と3時間」となって、以降は5時間取得ごとに1日としてカウントします。
子の看護休暇の時間単位取得が休憩時間にかかる場合
時間単位の子の看護休暇取得が、休憩時間にかかる場合は、休憩時間を除いた実際に勤務すべき時間帯で取得させる必要があります。これは、労働義務のない休憩時間に休暇を取得する余地がないと解釈されるためです。
たとえば、始業と就業が8:30~17:00(休憩12:00~13:00)の事業場において、始業から4時間、子の看護休暇を取得した従業員がいた場合で考えます。単純に計算した場合、8:30~12:30の取得となり、休憩時間に差し掛かってしまいます。
この場合は、「8:30~12:00」と「13:00~13:30」に分割して、合計4時間取得したと計算することになります。休憩時間を子の看護休暇の時間にカウントしないよう、注意が必要です。
フレックスタイム制における取り扱い
フレックスタイム制の対象労働者となっている場合でも、子の看護休暇は請求に応じて取得させる必要があります。
フレックスタイム制は、清算期間と呼ばれる期間内で決められた労働時間の総枠の範囲で、始業・終業時間の設定を労働者に委ねる制度です。労働者が自由に設定できる時間帯を「フレキシブルタイム」、必ず出社するべき時間帯を「コアタイム」と呼びます。
コアタイムについては、必ずしも設ける必要がないため、そうなると一見、子の看護休暇の時間単位での取得については、対象外としても問題ないように思われます。
しかし、子の看護休暇は、育児の必要性に応じて労働義務を免除する制度であり、フレックスタイム制の制度趣旨と全く異なることから、フレックスタイム制の対象者であっても時間単位での取得を認めなくてはなりません。
変形労働時間制における取り扱い
変形労働時間制は、変形期間と呼ばれる期間内で、繁閑などに応じて日や週の所定労働時間が変動する制度です。よって、子の看護休暇の1日が何時間に相当するのかについて、注意が必要です。
具体的には、変形労働時間制の適用労働者が子の看護休暇を時間単位で取得する場合は、変形期間における1日平均所定労働時間数(1時間に満たない端数がある場合には、端数切り上げ)分の休暇で「1日分」の休暇として取り扱います。
これは取得日による不公平感をなくすためで。たとえば、繁忙期で所定労働時間が9時間に設定されている日と、閑散期で所定労働時間が6時間に設定されている日に、それぞれ6時間の子の看護休暇を取得したとします。
通常通り運用した場合、前者は9時間-6時間で3時間残るのに対して、後者は1日分の取得してカウントされてしまいます。そこで、変形期間における1日平均所定労働時間数分を「1日分」の休暇として取り扱うことで、このような不具合を調整することになっています。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
子の看護等休暇についてよくある質問
子の看護等休暇について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
- Q子の看護等休暇は有給?無給?
- A
子の看護等休暇取得時の給与に関しての規定は無いため、有給とするか無給とするかについては、企業の判断に委ねられています。
一般的には無給とする企業が多くなっていますが、トラブルを避けるためにも、取得時の賃金については就業規則等へ明記しておきましょう。
- Q子の看護等休暇に違反した場合の罰則は?
- A
育児・介護休業法には、子の看護等休暇に関する罰則は定められていません。よって、子の看護等休暇の請求を拒んだとしても、そのことを以て直ちに罰則が科せられるわけではありません。
ただし、上記のような違反事項に関して、厚生労働大臣は当該企業に報告を求め、是正勧告をすることができます。そして、この是正勧告を無視したり虚偽の報告を行ったりした場合は、20万円の過料が科せられる可能性があります。
さらに悪質と判断された場合には、厚生労働大臣の名において企業名を公表されることもあるため、法令遵守を徹底しましょう。
勤怠管理システムで子の看護等休暇の改正にも柔軟に対応
子の看護休暇は、2021年の時間単位取得に続き、今回の対象となる子や取得事由の拡大など、より利用しやすい制度への改正が続いています。
従業員にとって喜ばしい改正である一方、経営サイドにとっては勤怠管理が複雑化する要素が増えたことになります。育児介護休業法関連の改正は今後も続くと予想され、勤怠管理もそれに応じた対応が必要です。
勤怠管理システムを導入することで、時間単位での休暇管理など、イレギュラーな勤怠にも柔軟に対応できるだけでなく、法改正にもスムーズに対応できます。
「勤怠管理システムの選定・比較ナビ」であれば、必要な要件を満たしている勤怠管理システムの中から、自社に最もマッチングするシステムを探し出せます。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。