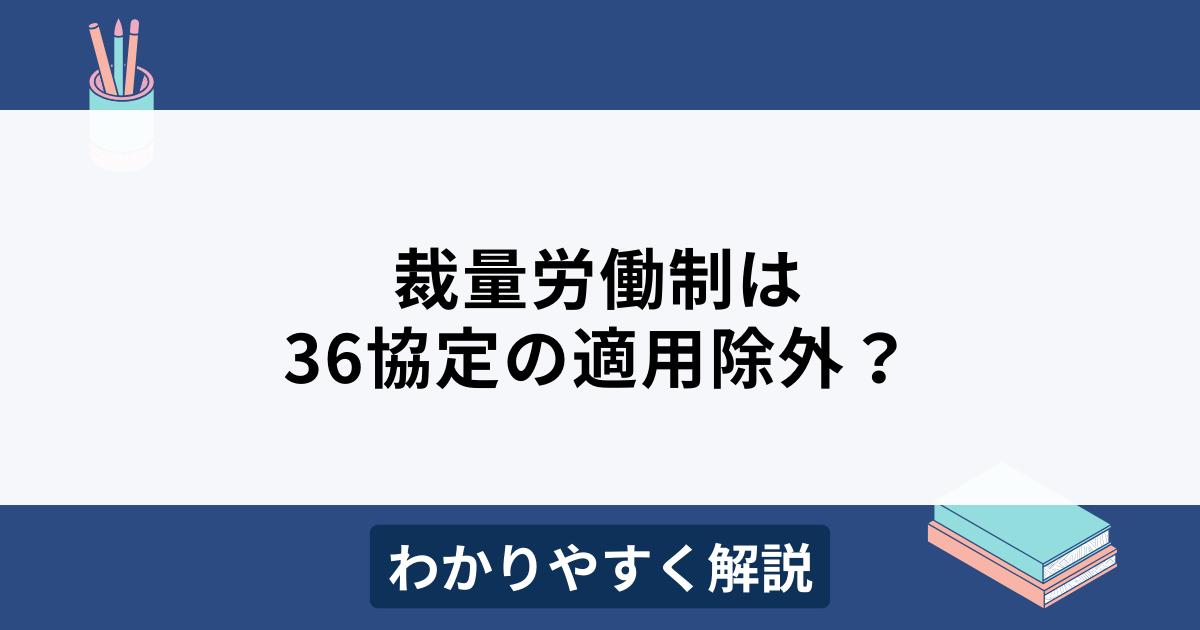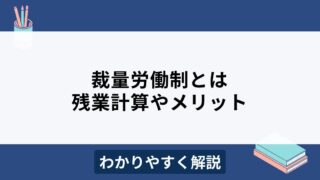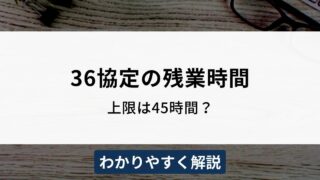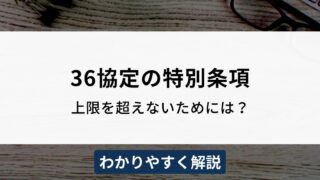「裁量労働制は残業代が要らない」「だから、36協定も必要ない」。
このような誤解をされている事業主の方も、少なくないようです。しかし、そもそも裁量労働制は残業代を削減するための制度ではなく、労働時間の設定や実態によっては残業代が発生するため、当然36協定も必要になってきます。
この記事では、裁量労働制において36協定が必要となる3つのケースについて、わかりやすく解説します。
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
裁量労働制とは
裁量労働制とは、実労働時間に関係なく、あらかじめ労使協定で定めたみなし労働時間分だけ労働したものとみなされる制度です。
裁量労働制は、企画立案や経営分析など、仕事の成果と労働時間の長さとの関係が希薄な業務に従事する労働者に対する、「成果報酬型」の労働制度として定められています。
専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制
裁量労働制には「専門業務型」と「企画業務型」の2種類があり、それぞれ対象業務や要件が厳格に定められています。
専門業務型裁量労働制は、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として定められた20の業務から対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、あらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
導入には労使協定の締結が必要で、2024年4月の法改正により従来求められていなかった対象労働者の個別同意も必要となりました。
企画業務型裁量労働制は、本社や本店など事業運営の決定権を持つ事業場の対象業務につく労働者に対して、労使委員会であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
恣意的な運用を防止するため、労使委員会の決議など、専門業務型よりも厳格な導入手続きが要求されています。
2024年4月の改正ポイント
裁量労働制は、法改正法を受けて2024年4月から制度の内容がいくつか変更されます。主な改正ポイントは以下のとおりです。
- 専門業務型裁量労働制の対象業務が追加されて20業務になった
- 専門業務型裁量労働制において、対象労働者の個別同意が必須要件になった
- 専門業務型・企画業務型のいずれについても、労働者本人の同意撤回手続きと同意及び撤回の記録保存に関する定めが義務付けられた
- 企画業務型裁量労働制において、対象労働者に適用される賃金・評価制度について労使委員会への説明が義務付けられた
- 企画業務型裁量労働制において、労使委員会の開催頻度が6ヶ月以内ごとに1回となった
- 企画業務型裁量労働制の定期報告が、労使委員会の決議の日から起算して初回は6ヶ月以内に1回、その後1年以内ごとに1回となった
裁量労働制の労働時間の考え方
裁量労働制では、労使協定を締結し、所定労働日のみなし労働時間を定め、実労働時間に関係なくこのみなし労働時間分働いたとして扱います。
たとえば、みなし労働時間を8時間と定めた場合は、実労働時間が9時間であっても残業代は発生しません。一方で、実労働時間が7時間しかない場合でも8時間働いたとみなされるため、賃金控除は認められません。
なお、法定休日の労働(休日労働)については、裁量労働制の対象外であり、実労働時間に応じた休日割増賃金が必要です。所定休日については、労使協定にてみなし労働時間の対象とすると定めた場合はみなし労働時間、定めていない場合は実労働時間でカウントします。
また、22時から翌5時までの深夜労働は、裁量労働制でも関係なく、既定の深夜割増賃金(25%以上)を支払う必要があります。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
36協定とは
36協定とは、「時間外・休日労働に関する協定届」の通称で、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超える労働、及び休日労働を命じるために必要な労使協定です。
具体的に法定時間外労働・休日労働を命じるためには、36協定を締結・届出した上で、就業規則等に時間外労働・休日労働を命じることがある旨を規定する必要があります。
なお、現実に発生した法定時間外労働・休日労働に対しては、36協定の締結の有無に関わらず、割増賃金を支払わなければなりません。
36協定の上限時間は?1日の上限はある?
36協定の締結・届出をした場合でも、時間外労働の上限は原則「月45時間・年360時間」までと定められています。ただし、時間外労働と休日労働は別々に扱うため、休日労働の時間は上記の上限時間にはカウントしません。
なお、36協定届には1日について時間外労働させる時間を記入する欄がありますが、これはあくまでも目安として記入するものであり、特に法的に1日あたりの上限が設けられているわけではありません。
「特別条項」があれば、原則の上限超えも可能
臨時的な特別の事情により、原則の時間を超えて労働させる必要がある場合は、労使が合意した特別条項を設定することで、更に時間外労働を命じることが可能です。ただし、特別条項を適用する場合でも、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 年間の時間外労働の合計が720時間以内(休日労働は含めず)
- 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
- 時間外労働と休⽇労働の合計が2~6ヶ月平均のいずれも80時間以内
- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6回まで
なお、臨時的な特別な事情とは、大規模なクレーム対応やシステムの復旧作業など、急激に業務量が増加した場合に限定され、慢性的な人手不足や業務上の都合など、曖昧な理由では適用が認められません。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
裁量労働制でも36協定が適用除外とならない3つのケース
前提として、裁量労働制の対象労働者であっても、36協定の原則の上限規制や特別条項のルールは、等しく適用されるということをまずは押さえておきましょう。その上で、実際にどのようなケースで36協定が必要となるのかをみていきましょう。
ケース1:みなし労働時間を8時間超と定めた
まずは、労使協定にて定めたみなし労働時間が、法定労働時間である8時間を超えている場合です。ここで言う労使協定とは、36協定のことではなく、裁量労働制について定めた労使協定です。
たとえば、みなし労働時間を9時間と定めた場合は、所定労働日に常に1時間ずつの時間外労働が発生することになります。
なお、みなし労働時間を10時間と定めてしまうと、月の所定労働日が20日と想定した場合、月の上限45時間の方はクリアできるものの、年間の上限360時間を超えてしまうため、注意が必要です。
ケース2:所定(法定外)休日に労働が発生する
所定休日の労働時間は、労使協定において「みなし労働時間を適用する」と定めた場合はみなし労働時間を、特に定めがない場合は実労働時間を、それぞれカウントします。
上記のどちらで扱うにしても、たとえばみなし労働時間を8時間と定め。週所定労働日が5日の場合、所定休日に労働が発生することにより、週の法定労働時間40時間を超過することになります。
よって、日々の労働時間が法定労働時間以内に収まっているとしても、週の法定労働時間を超過することになるため、36協定が必要です。
ケース3:休日労働が発生する
法定休日の労働(休日労働)は、所定労働日や所定休日の労働時間とは別で管理する必要があります。たとえ、みなし労働時間が8時間以内で、週の法定労働時間40時間も超過していなかったとしても、休日労働が発生する場合は36協定が必要です。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
裁量労働制と36協定の管理は勤怠管理システムで運用がおすすめ
裁量労働制は、しばしば「残業代カットのための制度」と勘違いされることが多く、そのつもりで導入してしまうと、思わぬ法令違反・労使トラブルを招きかねません。
あくまでも「労働時間に縛られない、成果報酬型の新しい働き方のための制度」であることを念頭に、法に則った運用が求められます。また、実労働時間と賃金が切り離されているというだけで、長時間労働抑制のための労働時間の管理は必要です。
勤怠管理システムを利用することで、みなし労働時間の設定に応じた適切な残業や休日労働の管理が可能となります。
「勤怠管理システムの選定・比較ナビ」をご利用いただくと、裁量労働制の運用に便利な勤怠管理システムの中から、自社に最もマッチングする製品を探し出せます。低コストでハイスペックな機能を搭載している勤怠管理システムを多数扱っている点も、嬉しいポイントです。
裁量労働制導入に向け、勤怠管理システムの導入を検討している方は、勤怠管理システムの選定・比較ナビを是非ご利用ください。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。