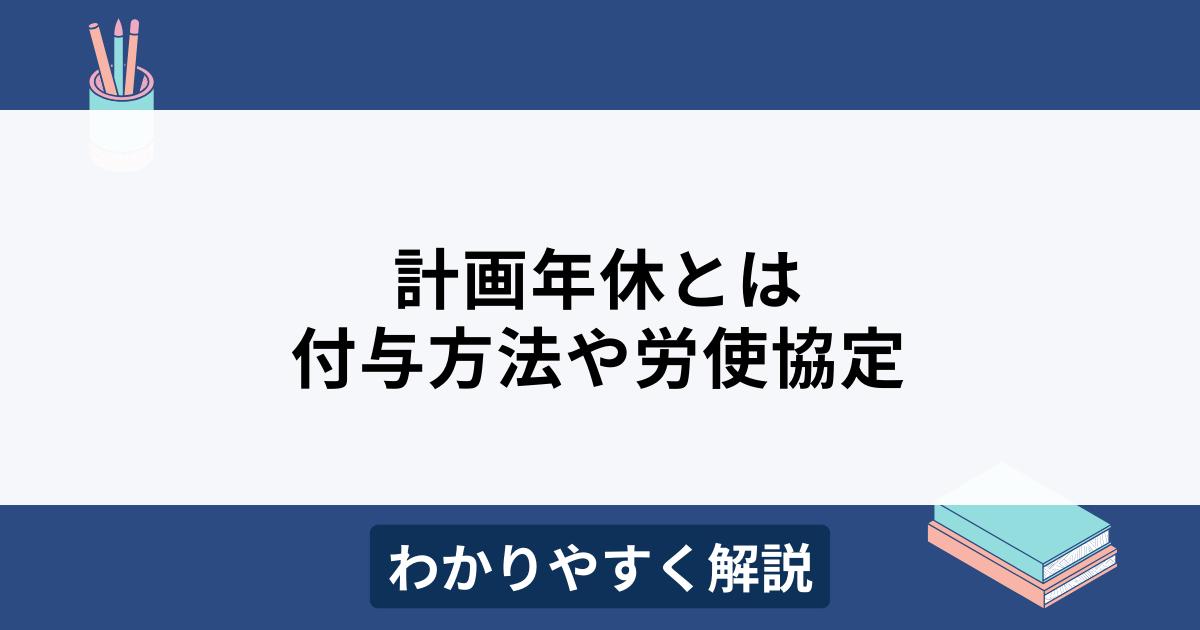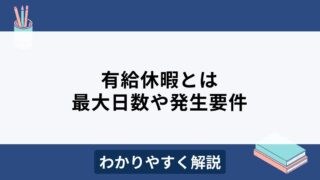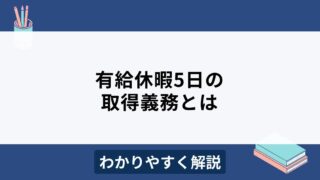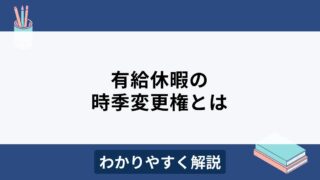計画年休を上手く使うことによって、義務化された5日分の年次有給休暇の消化を達成できるだけでなく、全体の取得率を大きくアップさせることができます。
計画年休(正式には「年次有給休暇の計画的付与制度」と言います)は、以前から存在していた制度ですが、2019年4月からの有給取得義務化に伴い、俄然注目を浴びるようになりました。
理由としては、計画年休を使うことにより取得義務とされた5日の有給消化が可能となるためであり、厚生労働省のパンフレットにおいても、計画年休の利用が推奨されています。
ただし、実際に計画年休を運用していると、対象外の労働者や退職者の取り扱いなどについて、さまざまな疑問に突き当たります。
本記事では、計画年休の導入に当たってのガイドラインを示しつつ、労務管理の現場で起こり得る運用上の問題点と対応策について解説します。
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
計画年休とは
計画年休は、正式には「年次有給休暇の計画的付与制度」といいます。有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残日数について、労使協定により計画的に休暇取得日を割り当てることができる制度です。
計画年休は、あらかじめ計画的に有給休暇取得日を割り振れるため、労働者はためらいを感じることなく有給休暇を取得可能です。また、計画年休で取得した有給休暇は、取得義務である5日分としてカウント可能であり、取得義務の達成のために有効な制度です。
一方、計画年休で指定された日については、「労働者の時季指定権」「使用者の時季変更権」ともに行使が認められていないことには注意が必要です。
有給休暇とどう違う?
計画年休は有給休暇の取得方法の一つであり、特に比較して何かが違うという性質のものではありません。有給休暇は法的には「年次有給休暇」と呼び、要件を満たした労働者に対して、賃金が保証された休暇を一定日数分付与する制度です。
計画年休の対象者
計画年休は、付与日数のうち5日を除いた残日数について指定できます。つまり、労働者が自由に取得できる有給休暇を最低5日間は残さなければならず、年6日以上の有給を付与されている労働者が対象となります。
全ての有給休暇を計画年休にすると、労働者は好きな日に休めなくなり、労働基準法で保障されている有給休暇を自由に取得できる権利が侵されるためです。
計画年休の上限日数は「有給休暇付与日数-5日」で計算します。よって、計画年休に充てられる日数は、勤務形態、勤続年数、また前年から繰越された有給休暇の日数によっても変わります。計画年休対象者と付与可能日数は下記のとおりです。
上記のとおり、週所定労働日数4日の労働者は、初年度に2日しか計画年休に充てることができません。また、週所定労働日数1日の労働者は、勤続年数に関わらず計画年休の対象にはなりません。
計画年休のメリット・デメリット
計画年休の導入に当たっては、使用者と労働者双方のメリット・デメリットを見きわめる必要があります。
| メリット | デメリット | |
| 使用者 | ||
| 労働者 |
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
計画年休の導入手順と労使協定
計画年休の導入には、労使協定の締結と就業規則への明記が必要です。なお、労使協定を労働基準監督署まで届け出ることまでは求められていません。
労使協定では、「対象者」「日数」「具体的な方法」「付与日数が少ない者の扱い」「付与日を変更する場合の手続き」を定めなければなりません。
計画一斉付与によって、新規採用者など5日を超える年次有給休暇がない者に対しては、「有給の特別休暇とする」もしくは「休業手当として平均賃金の60%以上を支払う」いずれかの方法を取る必要があります。
【就業規則記載例】
第〇条 会社は、労働者代表との書面による協定(労使協定)により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
計画年休の方法は3パターン
計画年休の方法は、以下の3パターンがあり、従業員規模や業態にマッチした方法を選択する必要があります。
- 一斉付与方式
- 交替制付与方式
- 個人別付与方式
管理が楽で大型連休を組みやすい一斉付与方式
一斉付与方式は事業場や企業単位で全従業員一斉に休業とする方式です。
【メリット】
- 一律に有給休暇を取得するため、有給休暇の管理が楽になります
- 年末年始やゴールデンウィークなどに組み入れると大型連休を作りやすいです
- 事業場や企業単位で一斉に稼働がストップするため、経費の削減効果が期待できます
【デメリット】
- 取引先や顧客に迷惑が掛からない一斉休業日を見定める必要があります
【向いている企業】
- 製造業、従業員の多い大企業
- 一斉休業による取引先や顧客への影響が少ない企業
業務への影響が少なく柔軟性がある交替制付与方式
交替制付与方式は、班やグループ別に交替で有給を付与する方式です。
【メリット】
- 取引先、顧客への影響を最小限に抑えられます
- 繁閑に応じて有給休暇をコントロールしやすくなります
【デメリット】
- 経費削減の効果は薄いです
- 労働者の希望通りにはならず、大型連休になりづらいです
【向いている企業】
- 常に誰かが稼働している必要のある流通業、接客サービス業
- 部署や担当ごとに繁閑の差が大きい事業場
- 一斉休業が難しい企業
労働者満足度が高い個人別付与方式
個人別付与方式とは、誕生日や結婚記念日など、個人の希望する日をアニバーサリー休暇として付与する方法です。
労働者が「年次有給休暇計画表」などに記載した希望日に基づいて、会社が労働者ごとに計画年休日を設定するケースが多いです。
【メリット】
- 労働者の満足度が非常に高くなります
【デメリット】
- 従業員の数が多いほど、企業側の管理の負担が大きくなります
【向いている企業】
- 従業員の数が少ない中小零細企業
- ワークライフバランスをアピールしたい企業
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
計画年休についてよくある質問
計画年休について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
- Q指定付与日を過ぎてから入社した労働者の取扱いは?
- Q計画年休対象外の労働者が計画年休日に有給を申し出た場合は?
- Q労働者が計画付与日の有給取得を拒否した場合は?
- Q退職予定者の有給取得を、計画年休を理由に拒否できる?
計画年休は勤怠管理システムでぐっと楽になる
計画年休は、有給休暇取得率アップが大いに期待できる一方で、特に個人別付与方式を選択した場合などは、その管理による負担が大きくなります。
また、設定可能な日数も雇用形態や勤続年数によりバラバラであることから、最適な日数を設定するのも難しいという面もあります。
そこで、勤怠管理システムを導入することにより、労働者ごとの計画年休日や取得状況が一元化されて管理がぐっと楽になります。計画年休制度を最大限に活用するためにも、勤怠管理システム導入を検討しましょう。
勤怠管理システムの選定・比較ナビは、多くの勤怠管理システムから自社にマッチした最適なシステムを見つけ出せるサイトです。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。