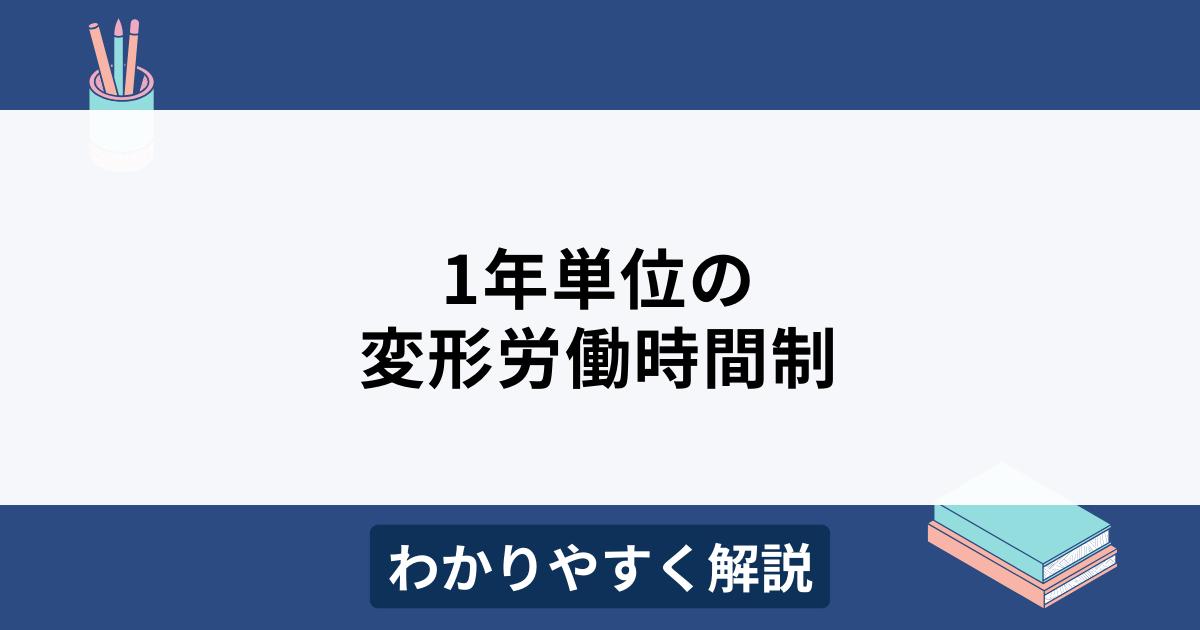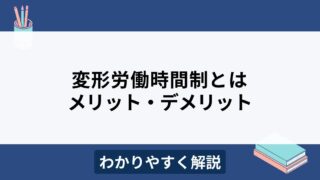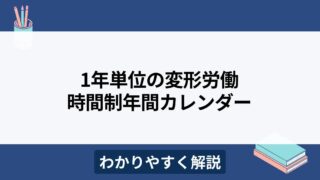1年単位の変形労働時間制は、年間の繁忙期や閑散期の差が大きい事業場にとって大きなメリットを得られる制度です。ただし、導入手順はやや煩雑であり、また残業代の計算なども事前にしっかり押さえておく必要があります。
この記事では、1年単位の変形労働時間制について、そのメリット・デメリットから、他の変形労働時間制との違い、協定届の書き方、残業代の計算まで、わかりやすく解説します。
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
1年単位の変形労働時間制とは
1年単位の変形労働時間制とは、変形労働時間制の中でも対象期間が1ヶ月を超え1年以内であるものを指します。具体的には、期間内の週平均所定労働時間を一定の時間内で収めることで、特定の日や週に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働が可能となります。
1年単位の変形労働時間制の概要と目的
1年単位の変形労働時間制とは、1ヶ月を超え1年以内の対象期間(以下、「変形期間」と呼びます)を定めて、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働ができる制度です。導入に際しては、変形期間内の勤務カレンダーを作成します。
労働基準法においては、労働時間の上限(法定労働時間)は1日8時間・週40時間と定められており、これを超えて労働を命じるには労使協定(36協定)の締結や残業代(時間外割増賃金)の支払いが必要です。しかし、業種によっては法定労働時間どおりの運用をするのが困難なケースもあります。
そこで労働基準法第32条の4では、1年以内の変形期間中の労働時間を平均して週40時間の範囲内であれば、特定の週や日に法定労働時間を超える労働を命じることを認めています。
1年単位の変形労働時間制は、弾力的に運用できる一方、導入と運用については慎重に進める必要があります。導入によるメリットとデメリットを整理し、就業規則や労使協定の手続などの基礎をしっかり理解しましょう。
1年単位の変形労働時間制導入のメリット
1年単位の変形労働時間制の導入により、繁忙期では所定労働時間を長くすることで多くの労働力を確保でき、また逆に閑散期では所定労働時間を短くすることで、無駄な労働時間を削ることもできます。1年単位の変形労働時間制は、使用者側と労働者側双方とも業務の効率化を図ることが可能です。
使用者は繁忙期と閑散期で所定労働時間を増減させ、年間を通じて時間外労働に対する割増賃金(残業代)を抑えるメリットがあります。
また、労働者に対して閑散期の短時間労働や休暇の取得を推進し、リフレッシュしてもらうことで、会社全体のモチベーションアップが可能になります。
一方、労働者にとっては繁忙期と閑散期の労働時間が変わることで、メリハリの利いた働き方が可能となるのがメリットです。
従来、労働者は仕事が暇な時には何もせず、漫然と勤務時間が終了するまで待つ一方で、仕事が忙しい時には勤務時間内に仕事が終わらないこともしばしばでした。しかし、変形労働時間制では忙しい時には長時間働き、暇な時には短時間あるいは休暇が取得できます。
土日が休日となっている会社であれば、平日に休暇を取得しにくい状況ですが、平日のレジャー施設が混雑しているケースは少なく、また役所などの行政機関の窓口対応は原則平日のみです。労働者は気兼ねなく平日の休暇を取得できるのは、大きなメリットです。
1年単位の変形労働時間制導入のデメリット・注意点
使用者側の最大のデメリットは、変形労働時間制の導入手続きと運用の問題です。特に人事部門の時間管理や勤怠管理が非常に複雑で煩雑になります。
従来、人事担当者は労働者の労働時間を、法定労働時間の基準に従って残業代を算出できていたところ、1年単位の変形労働時間制では適用されている部署や繁閑ごとに、バラバラの所定労働時間となります。そのため部署の適用有無による労働時間管理、勤務カレンダーの管理、残業代の計算が必要です。
また導入時の手続きについては、就業規則改定や労使協定を締結しなければなりません。手続きを進める際、問題がないかを十分にチェックして慎重に進める必要があります。使用者、特に人事部門にとっては非常に大変な作業となります。
一方、労働者にとってのデメリットは、残業代の問題です。残業代は、新しく会社が設定した所定労働時間が基準となるため、同じ労働時間にもかかわらず。導入前に支払われていた残業代が導入後は支払われないケースも出てきます。
特に繁忙期の所定労働時間は長く設定されるため、繁忙期では労働者は長時間働いているわりには残業代が少ないと感じるようになります。
また、導入前は社内全体が一律の同じ勤務時間でしたが、導入後は部署や職種によって勤務時間は変わるため、 勤務時間の異なる他の社員に気遣って、会社から帰りづらくなる労働者も出てきます。
適用の有無による勤務時間の違いにより、社内から不平不満が出るような事態を想定して、導入に際しては十分に説明を尽くすことが大切です。
1年単位の変形労働時間制と相性の良い業種・職種
1年単位の変形労働時間制は、1年間で繁忙期と閑散期の差が激しい業界にとっては相性が良いです。
多くの企業は、年末と年度末(決算月)は繁忙期になる傾向が強いといえます。業種・職種で見ると、小売業では年末年始セールや夏冬のバーゲンが繁忙期になります。建設業や土木業は年度末(3月)に工事が集中します。
職種で見ると、営業職は業績集計の関係で、上期末と年度末を含む四半期末月は営業成績の追い込みを図る必要があり、経理職は年度末(決算月)と、税務署への法人税申告が終わる翌々月までは決算作業に追われます。
このように、年間で業務が集中する時期がある程度決まっている業種・職種は、1年単位の変形労働時間制の効果を高くなります。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
1年単位の変形労働時間制と1ヶ月単位の変形労働時間制との違い
変形労働時間制には、1年単位の変形労働時間制と類似した1ヶ月単位の変形労働時間制があります。両者は変形期間の長さだけではなく以下のような違いがあります。
- 労使協定の締結が必須
- 労働日数の上限がある
- 連続労働日数の上限と特定期間がある
- 1日当たりの労働時間は10時間まで
- 1週当たりの労働時間は52時間まで
1. 労使協定の締結が必須
1年単位の変形労働時間制を導入する場合は、就業規則の変更および労使協定の締結をし、労働基準監督署に届け出る必要があり、就業規則の変更と労使協定の締結どちらも必須となっています。
一方で1ヶ月単位の場合は、就業規則の変更または労使協定の締結いずれかを定めて、労働基準監督署に届け出をします。就業規則によるか、労使協定によるかは使用者が決めることができます。
2. 労働日数の上限がある
1ヶ月単位、1年単位ともに所定労働時間の上限がある点は同じですが、1年単位の場合は1年あたり280日という労働日数の上限(対象期間が3ヶ月以下の場合を除く)があります。対象期間が3ヶ月を超え1年未満の場合は、下記の計算式で労働日数の上限を設定します。
労働日数の上限=280日×対象期間の歴日数÷365日(端数は切捨て)
3. 連続労働日数の上限と特定期間がある
1年単位の連続労働日数の上限は原則6日と定められています。ただし、対象期間のうち特に繁忙である時期を特定期間として定めることで、1週間に1日の休日が確保できる日数(最長12日まで)まで連続勤務が可能となります。
なお、労使協定に定めた特定期間を対象期間の途中で変更することはできません。また、変形期間の大半を特定期間として設定することも認められません。
一方で1ヶ月単位の変形労働時間制には、連続労働日数の上限も特定期間の定めもありません。
4. 1日当たりの労働時間は10時間まで
1年単位の場合、1日あたりの労働時間は10時間が上限と定められています。なお、隔日勤務のタクシー運転手の業務に従事する一定の労働者については、1日あたりの労働時間の限度は16時間となっています。
一方で1ヶ月単位の変形労働時間制には、1日あたりの労働時間の上限はありません。
5. 1週当たりの労働時間は52時間まで
1年単位の場合、1週あたりの労働時間は52時間が上限と定められています。ただし、対象期間が3ヶ月を超える場合は、以下のとおりに設定しなければなりません。
- 所定労働時間が48時間を超える週は連続して3週以下
- 所定労働時間が48時間を超える週は3ヶ月単位ごとに3回以下
なお、積雪地域については、一定の業務に従事する労働者は1.と2.の労働時間が48時間を超える週についての制限はありません。
一方で1ヶ月単位の変形労働時間制には、1週あたりの労働時間の上限はありません。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
1年単位の変形労働時間制導入の流れ
1年単位の変形労働時間制の導入は、以下の流れに沿って行われます。
- 対象者を決める
- 起算日及び対象期間を決める
- 特定期間を決める
- 労働日と労働時間を決める
- 有効期間を決める
- 就業規則及び労使協定への記載・届出
導入には労使協定の締結が必要ですが、手続きを誤るとあとで労働基準監督署の調査で法令違反を指摘されるおそれがあります。
また、残業代の上乗せ支給が必要になるケースも考えられます。導入の手続きと流れをきちんと理解して、万全な準備を進めることが重要です。
1. 対象者を決める
労働基準法では、変形労働時間制を導入する際、対象者については特に制限は設けられていませんが、対象者の範囲については明確に定める必要があります。
対象者を全従業員にするのか、あるいは特定の部門や職種の従業員のみを対象にするのかを明確にします。変形期間中の中途採用、中途退職の労働者も賃金の精算を条件に対象にできます。
なお、年少者については原則1年単位の変形労働時間制で労働させることはできませんが、1週48時間、1日8時間以内であれば可能です。また、妊産婦が請求した場合には1週40時間、1日8時間の範囲内でしか労働させられないため、1年単位の変形労働時間制で労働させることはできません。
2. 起算日及び対象期間を決める
起算日と変形期間を具体的に決めます。1年単位の変形労働時間制の変形期間は、1ヶ月を超え1年以内の期間となります。この範囲であれば問題ないため、例えば変形期間を3ヶ月や6ヶ月にすることも可能です。
起算日をいつに設定するかは自由に決定できます。変形期間を1年にした場合、「4月1日」や「毎年〇月第〇月曜日」のように決めるのが一般的です。
3. 特定期間を決める
特定期間は必ずしも設けなくても構いませんが、設定する場合は明記する必要があります。なお、変形期間の相当部分(例えば1年の半分以上など)を特定期間にすることはできません。
4. 労働日と労働時間を決める
変形期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えないように、対象期間の各日、各週の所定労働時間を決定します。
変形期間の全期間に渡って定める必要がありますが(勤務カレンダーの作成)、一度に作成することが難しい場合、変形期間を1ヶ月以上に期間を区分することで、以下のように定めることも可能です。
- 最初の期間における労働日
- 最初の期間における労働日ごとの労働時間
- 最初の期間を除く各期間における労働日数
- 最初の期間を除く各期間における総労働時間
ただし、最初の期間を除く各期間の労働日と労働時間については、その期間の始まる少なくとも30日前に、労働者の過半数で組織する労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者の同意を得て、書面で定めなければなりません。
5. 有効期間を決める
1年単位の変形労働時間制の導入に必要な労使協定の有効期間は、変形期間以上の期間を定める必要があります。変形期間と同じ期間を設定して、その都度労使協定を再締結するのが一般的です。
6. 就業規則及び労使協定への記載・届出
変更後の就業規則、締結した労使協定と、勤務カレンダーを労働基準監督署に提出します。
また、就業規則や労使協定は、運用を開始する前に、その内容を従業員に周知しなければなりません。変形労働時間制について、従業員の理解を深めてもらうとともに、制度への誤解から生じる従業員の不満やモチベーションダウンを防止することも重要です。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
1年単位の変形労働時間制における残業代の計算方法
1年単位の変形労働時間制の割増賃金は、1日単位、1週単位、対象期間全体の3つに分けて計算します。
1. 1日について
1日あたりの所定労働時間を8時間を超えて定めた日は、定めた時間を超えた時間分が割増賃金の対象です。また、所定労働時間を8時間以下と定めた日は、8時間を超えた時間分が割増賃金の対象です。
たとえば、所定労働時間を9時間と定めた日は9時間を超えた部分、所定労働時間を7時間と定めた日は8時間を超えた部分について、残業時間として集計します。
2. 1週間について
1週あたりの所定労働時間を40時間を超えて定めた週は、定めた時間を超えた時間分が割増賃金の対象です。また、所定労働時間を40時間以下と定めた週は、40時間を超えた時間分が割増賃金の対象です。ただし、日単位で既に割増賃金の対象にした時間分は除きます。
たとえば、所定労働時間を45時間と定めた週は45時間を超えた部分、所定労働時間を35時間と定めた週は40時間を超えた部分について、残業時間として集計します。
3. 変形期間通算
変形期間における法定労働時間を超えた時間分が、割増賃金の対象になります。ただし、日単位と週単位で既に割増賃金の対象にした時間分は除きます。また、変形期間における所定労働時間として設定できる総枠は、下記の通り計算します。
変形期間の所定労働時間として設定できる総枠 = 40時間×対象期間の歴日数÷7
具体的には、1年365日の場合の法定労働時間は2,085時間で、閏年(366日)の場合は2,091時間になります。
1年単位の変形労働時間制の導入には、勤怠管理システムが有効
1年単位の変形労働時間制は、従業員や会社にとって様々なメリットがありますが、導入した場合には煩雑な作業・手続きが待ち構えています。勤務カレンダーの作成や残業代の計算などマンパワーが必要です。また、労務管理の負担も圧倒的に増えることが予想されます。
これらの問題点を一気に解消してくれるのが、勤怠管理システムの導入です。勤怠管理システム導入を検討される企業の皆さまは、ぜひ一度「勤怠管理システムの選定・比較ナビ」をご覧ください。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。