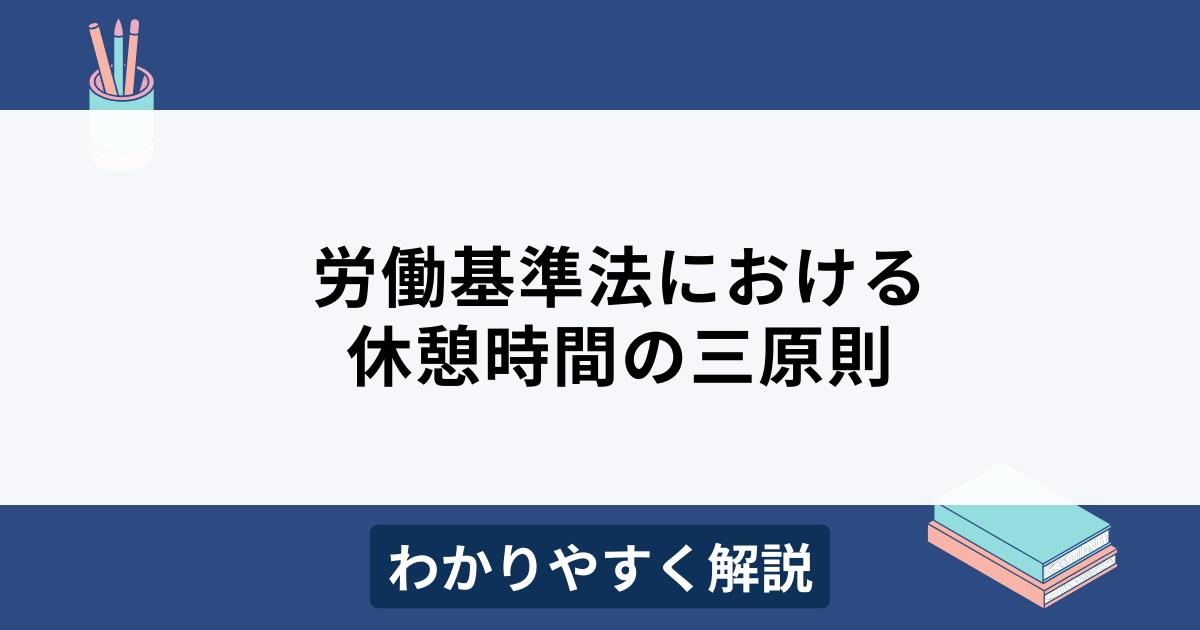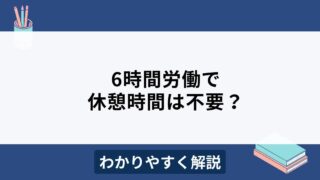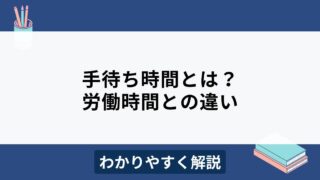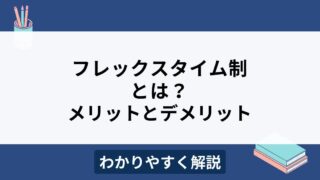労働基準法における休憩時間は、「途中に」「一斉に」「自由に」という三原則があり、労働時間に応じて「45分以上」もしくは「1時間以上」与えなければならないとされています。
労働時間中にとる休憩は、労働者の心身をリフレッシュし、また会社内のコミュニケーションを図る意味でも重要です。コンプライアンスの観点から、労働基準法の原則と例外を理解して遵守することはもちろん大切です。
ただし、実際の労務管理においては、他の規定や個々の事情によって、原則と例外のどちらを適用すべきなのか取扱いに悩むことが少なくありません。この記事では、具体的なケースを想定し、それぞれどのように取り扱うべきかを分かりやすく解説します。
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
労働基準法の休憩時間は「なし」「45分」「1時間」の3パターンのみ
休憩時間に関して、労働基準法34条では下記のように定められています。
(休憩)
労働基準法|法令検索 e-Gov
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働基準法上の休憩時間は、以下の3パターンのみであり、通達や判例においても他に具体的な休憩時間や運用については示されていません。
- 労働時間8時間超は1時間の休憩
- 労働時間6時間超は45分の休憩
- 労働時間6時間以内は休憩必要なし
労働時間6時間以下の場合は、休憩ゼロでも問題なし
労働時間が6時間ピッタリ、もしくは6時間以内に収まるのであれば休憩時間を与えなくても問題はありません。
しかし、残業が発生した場合は残業時間を含めて実労働時間を判断する必要があります。例えば、所定労働時間が6時間で1時間の残業が発生した場合、実労働時間は計7時間になるため、途中に少なくとも45分の休憩時間を確保しなければなりません。
通常、労働時間6時間以下の労働者は、正社員よりもパートタイマーやアルバイトが該当するケースが多いですが、休憩時間については雇用形態で区別することはできません。パートタイマーやアルバイトであっても休憩時間を同じように与えなければなりません。
「パートやアルバイトであること」のみを理由として、休憩時間を与えないことは法律違反になりますので注意が必要です。
どんなに長時間労働でも、休憩は1時間で問題ない?
「8時間を超える場合は少なくとも1時間」という規定を超える休憩時間は、法律上では義務付けられていません。また、「労働時間8時間を超えるごとに休憩1時間が必要」という意味でもありません。
極論ですが、条文上は労働者に1時間の休憩を与えれば何時間でも労働させることが可能です。しかし、こうした長時間労働は明らかに労働者の健康や作業効率に悪影響を及ぼします。
休憩時間なしで長時間勤務することにより、労働者の集中力低下を招いて、思わぬ労災事故に発展する危険性も高まります。
また、労働基準法上は問題がないとしても、会社には安全配慮義務という別の観点があるため、労働者の休憩時間や連続勤務時間については適正な管理が求められます。やむを得ず労働時間が長時間に及ぶ場合は、法定外休憩を与えるのが無難です。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
休憩時間の三原則とは?
労働基準法では休憩時間の長さだけではなく、どのように休憩を運用しなければならないかを以下の三原則として定めています。
- 途中付与の原則
- 一斉付与の原則
- 自由利用の原則
休憩時間は、「途中に」「一斉に」「自由に」与えなければならないのが原則ですが、業種や労使協定によって認められている例外も存在します。
休憩時間は労働時間の「途中に」与えなければならない
一つ目は「途中付与の原則」です。休憩時間は必ず労働時間の途中に設定しなければなりません。
必ずしも、多くの会社が設定しているランチ時間(昼12時前後の休憩時間)を開始時間として設定しなければならない、というルールはありません。あくまでも、労働時間の途中に休憩時間を設定すれば問題ありません。
間違った運用としてよく見られるのは、業務開始と同時に休憩時間に入るケースや、業務終了後に休憩を取らせて帰宅させるというケースです。
これらはいずれも、「連続した労働による心身の疲れを回復する」という休憩の目的から逸脱しており、休憩時間としては認められません。
なお、途中に与えていれば複数回に分割して与えることも認められていますが、この場合でも余りに細かく分割するという与え方は認められません。「途中付与の原則」は、ほかの二つの原則と違って例外がないのが特徴です。
休憩時間は労働者全員に「一斉に」与えなければならない
二つ目は「一斉付与の原則」です。労働者が休憩時間を一斉に取るように設定しなければなりません。一斉とは、事業場におけるパートタイマーやアルバイトなどを含む全労働者を、原則同じ時間で休憩時間を与えるという意味です。
休憩時間は、就業規則に必ず記載しなければならない事項であり、原則的に労働者ごとに個別に設定したり、労働者の好きな時間帯に取らせたりすることはできません。
ただし、労使協定で「休憩時間を一斉に与えないこと」について合意がなされていれば、休憩時間を一斉に与えないことも可能です。また、次に挙げる業種は、労使協定の有無にかかわらず一斉付与の対象外とされます。
【一斉付与の原則の例外】
- 一斉に休憩を与えることで、むしろ一般社会に不便や混乱を生じさせる以下の事業
- 運送、販売、理容、金融保険、映像演劇、通信、病院診療所、保育所、旅館、料理飲食、官公署
- 同一空間による一斉休憩が困難である、坑内労働者
休憩時間は「自由に」利用させなければならない
三つ目は「自由利用の原則」です。休憩時間は、労働者に自由に利用させる必要があります。休憩時間は、労働から解放されている必要があり、基本的にその時間の使い方は制限してはなりません。
休憩中に電話番や来客対応を任されている場合は、労働から解放されているとは言えず「手待ち時間」として労働時間とみなされます。
また、午後の勤務の準備をするために、休憩時間が終了する10分前にそれぞれのデスクに着席させるようなケースも休憩時間とはみなされません。労働者の休憩時間を会社が束縛してはならないのです。ただし、以下のような場合は、自由利用の原則が制限されます。
【自由利用の原則の例外】
- 警察官、消防吏員、常勤の消防団員や乳児院、児童養護施設及び障害児入居施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者については適用除外となります
- 事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えないとして、自由利用の例外がある程度認められます
- 事業所内に労働者が完全に労働から解放される休憩施設や食事を取れる施設がある場合は、外出を制限することが認められます
- 事業の正常な運営やほかの労働者の自由利用の権利を妨げる行為は、制限できます
- 坑内労働者については、自由な移動や行動を認めると安全管理上支障が出るため、適用除外となります
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
ケース別で考える休憩時間の実務
労働基準法における休憩時間の三原則を実際の現場で適用していくと、さまざまなケースにおいて疑問点に遭遇します。
また、労働基準法の他の規定との関連性や、労働基準法以外の法律との関連性からもさまざまな矛盾が生じてくるため、実務的には取扱いに苦慮するケースもあります。
休憩返上の申し出は断ることができる
労働者から「休憩なしで構わないので、その分早く帰りたい」と申し出があった場合、使用者はこれを断ることができます。
休憩時間を付与するのは「使用者の義務」です。労働者の便宜を図って申し出を認めてしまうと、結果的に労働基準法に違反することになります。よって、このような申し出は断ることができますし、コンプライアンスの観点からはむしろ断らなくてはなりません。
また、「今日は1時間遅刻したので、その分休憩時間を取らずに働きます」という労働者の申し出も、遅刻によって実労働時間が少なくなり休憩時間が必要なくなる場合を除いて、断らなくてはなりません。
時間単位年休の時間は休憩時間有無の判断に含めない
労働者が時間単位の年次有給休暇(以下、時間単位年休)を取得した日の労働時間については、時間単位年休の時間を除いた実労働時間で休憩の有無を判断します。
時間単位年休とは、年間の有給休暇を取得しやすくするために、2010年4月の改正労働基準法によって導入された制度です。労働者は1日単位ではなく、時間単位で年間5日を限度に有給休暇を取得可能です。
例えば、所定労働時間8時間、休憩時間1時間の事業場において、ある労働者が前半の4時間の時間単位年休を取得し、後半の4時間だけ労働した場合、規定通りに休憩時間を1時間与えなければならないのでしょうか。
この場合の労働時間は、あくまでも「実労働時間」で考えるため、労働時間は4時間となり休憩を与える必要はありません。
フレックスタイム制のコアタイムと休憩一斉付与の原則との関係
フレックスタイム制を採用している場合、コアタイムの設定と休憩一斉付与の原則との間で矛盾が生じるケースが考えられます、
これについては、フレックスタイム制におけるコアタイムと休憩時間は、それぞれ独立しており分けて考える必要があります。フレックスタイム制を導入している事業場で、以下のケースにおける休憩付与の必要性について見てみます。
- コアタイム 10:00~12:00、13:00~15:00
- 休憩時間 12:00~13:00
- ある労働者が、10:00~15:00のコアタイムの間のみ労働した
この場合の結論としては、休憩を与える必要はありません。実労働時間だけを見ると休憩なしでも「5時間」となり、付与義務が無いのは当然であるように思えます。
しかし、一方でコアタイムに休憩時間が含まれるとすると、この労働者だけ「一斉付与」の原則に反することになります。
これについては、コアタイムと休憩時間はそれぞれ独立しているため、当該労働者の実労働時間は5時間でそもそも休憩の付与義務がなく、「一斉付与」の原則にも反しないということになります。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
休憩時間についてよくある質問
- Q管理監督者には休憩時間は不要?
- Q休憩時間が取れなかった場合は?
- Q休憩時間は分割して付与できる?
休憩時間の管理は、勤怠管理システムで
休憩時間は、生産性向上、労働者の勤怠意欲維持、健康への配慮などの面から労働時間に応じて適切に付与する必要があります。
また、一斉付与の例外が発生したり、分割して付与する労働者がいる場合など、休憩時間の管理を適切に実施するには、勤怠管理システムは必要不可欠なツールです。勤怠管理システムを導入して、労働時間と休憩時間のメリハリのある職場づくりを目指してみませんか。
「勤怠管理システムの選定・比較ナビ」は、多くの勤怠管理システムから自社にマッチした最適なシステムを見つけ出せるサイトです。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。