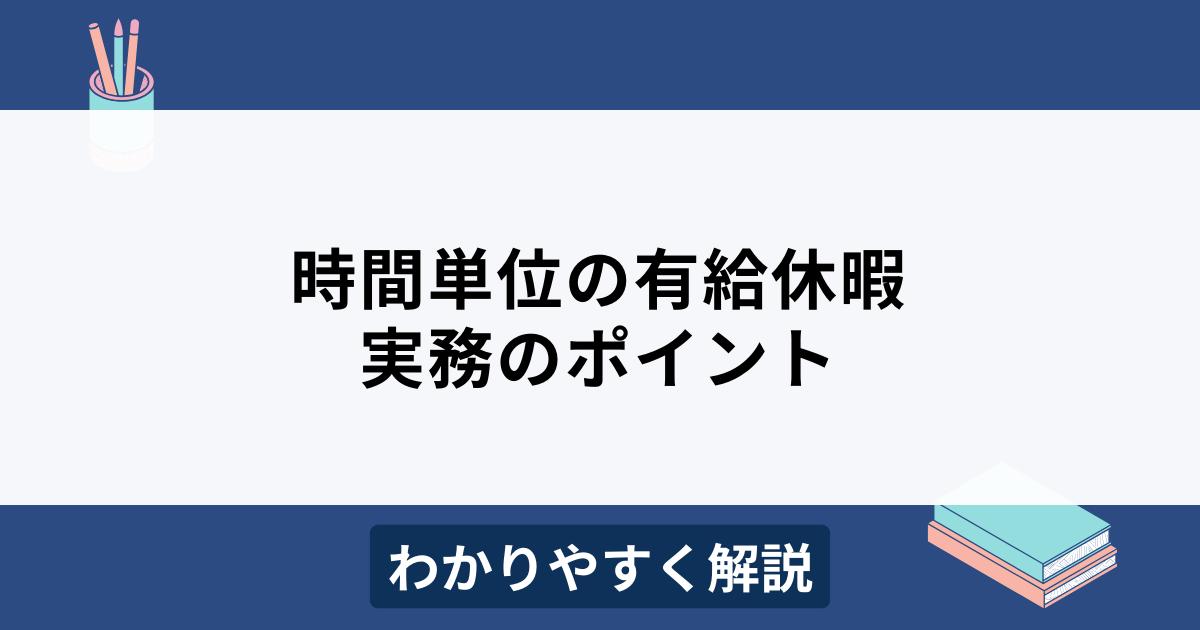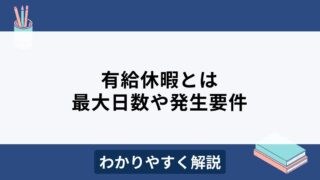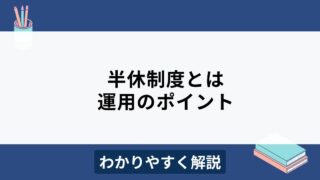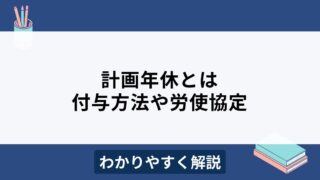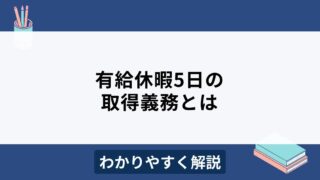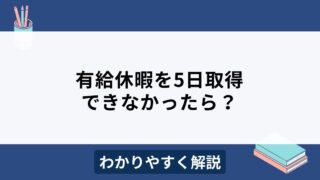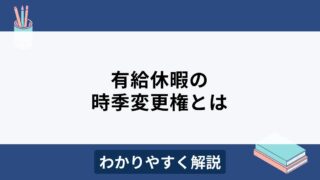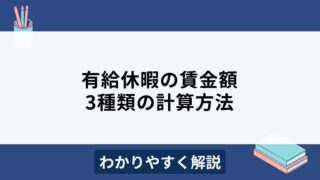時間単位の年次有給休暇(時間単位年休)は、実務上の取扱いが難しい制度です。しかし、有効に活用することで有給の取得率アップや従業員の満足度アップにつながります。
時間単位年休は労働者が取得しやすい休暇制度である反面、本来の一日単位の有給休暇が取得しづらいという懸念をよく耳にします。
この記事では、労務管理の実務に携わる使用者や人事労務担当者の方向けに、時間単位年休に関する実務のポイントを余すところなく解説します。
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
有給休暇の時間単位取得(時間単位年休)とは?
時間単位年休は、年次有給休暇を取得しやすくするために、2010年4月の改正労働基準法によって導入された制度です。労働者は、1日単位ではなく、労使協定で定めた時間単位で、年間5日を限度に有給休暇を取得できます。
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
労働基準法第39条4項 |法令検索e-Gov
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)
三 その他厚生労働省令で定める事項
時間単位の有給休暇の取得日数は?
時間単位年休の年5日というのは、1日単位の所定労働時間×5日分という意味です。1日分の年次有給休暇に対応する時間数は、所定労働時間数を基に計算します(時間に満たない端数がある場合は、時間単位に切り上げてから計算)。
例えば、所定労働時間が7時間30分の場合、最大「8時間×5日=40時間」分が時間単位で取得できます。端数の切り上げは、7時間30分を切り上げて1日8時間で計算する必要があります。7時間30分×5日=37時間30分を切り上げ、38時間にするという意味ではありません。
なお、通常の年休と同じく使い切れなかった時間単位年休は翌年度に繰り越しになります。ただし、繰り越し分も合わせて5日分であり、時間単位年休が増えるわけではありません。
時間単位年休のメリット・デメリット
時間単位年休の導入に当たっては、使用者と労働者双方のメリットとデメリットについて理解しておく必要があります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 使用者 | ||
| 労働者 | |
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
時間単位年休の導入手順
時間単位年休の導入には、労使協定の締結と就業規則の変更が必要です。労使協定に関しては、労働基準監督署への届出の必要はありませんが、就業規則を変更した場合は「就業規則変更届」の提出が必要です。
労使協定で決めるべき事項は4つ
時間単位年休を導入する際、下記の4つを労使協定で決めます。
- 時間単位年休の対象労働者の範囲
- 時間単位年休の日数
- 時間単位年休1日の時間数
- 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
1. 時間単位年休の対象労働者の範囲
部署や業務ごとに対象者を分けるのは問題ありません。しかし、有給休暇の取得目的で区別することは認められていません。例えば、「育児目的の有給に限って認める」などの規定は無効です。
2. 時間単位年休の日数
前年度繰越分も含めて、上限5日の範囲で決めます。
3. 時間単位年休1日の時間数
1日分の年次有給休暇に対応する時間数を、所定労働時間を基に定めます。前述のとおり、時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。
4. 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
通常は1時間単位ですが、2時間単位や3時間単位とするのも可能です。ただし、1日の所定労働時間を上回るのは不可です。
就業規則の記載例
基本的には、労使協定で定めた事項に従って、就業規則を記載します。
【年次有給休暇の時間単位での付与に関する就業規則の規定(例)】
(年次有給休暇の時間単位での付与)
第〇条 労働者代表との書面による協定に基づき、年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という)を付与する。
(1)時間単位年休の対象者は、すべての労働者とする。
(2)時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
① 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者・・・7時間
② 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者・・・8時間
(3)時間単位年休は2時間単位で付与する。
(4)本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
時間単位の有給休暇と他の有給規定との関係
時間単位の有給休暇の実務を取り扱うには、半休、計画年休、取得義務など、他の有給休暇に関する規定との関係をしっかり押さえる必要があります。
半日単位の有給とどう違う?
半日単位の有給休暇と、時間単位の有給休暇は別制度であるため、両者は併用可能です。
年次有給休暇は一日単位で取得するのが原則です。しかし、労働者が希望して使用者がこれに同意した場合、労使協定が締結されていない場合でも、半日単位の有給休暇取得は可能です。
このように、それぞれ別の制度であるため、半日単位の有給休暇を取得しても、時間単位の有給休暇の残り時間数に影響はありません。
計画年休制度に組み込める?
計画年休の中に時間単位の有給休暇を組み入れることはできません。計画年休は、有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残日数について、労使協定により、会社が計画的に休暇取得日を労働者に割り当てる制度です。
一方、時間単位の有給休暇は、労働者が時間単位で会社に有給休暇を申請して付与されます。つまり、計画年休と時間単位の有給休暇では、有給休暇の取得を決める主体が違うため、計画年休に組み込むことはできません。
取得義務の5日にカウントできる?
年10日以上付与されている労働者に対して取得が義務付けられている5日分について、時間単位の有給休暇の取得分はカウントできません。
そのため、時間単位の有給休暇を導入すると、通常の有給取得日数の管理と時間単位の有給休暇の管理が並行して必要になります。この点は、労務管理上のデメリットと言えます。
時季変更権は認められる?
時間単位の有給休暇でも時季変更権は認められています。時季変更権とは、労働者から申請があった有給休暇取得日を使用者が変更する権利です。
時季変更権は「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」に限り認められ、時間単位年休の場合は、さらに行使できる範囲が限定されます。
なお、行使が認められる場合でも、時間単位の有給休暇を1日単位や半日単位に変更させたり、逆に1日単位の有給申請を時間単位の有給休暇に変更させることはできません。
時間単位の有給休暇を取得した場合の賃金額
労働者が取得した時間単位の有給休暇に応じて、会社は賃金の支払いが必要です。1日単位の有給休暇を取得した場合の賃金額は、以下のいずれかになります。
- 通常賃金
- 平均賃金
- 標準報酬日額
上記の額をもとに、時間単位の有給休暇時間分を求めて賃金を算出します。
1日有給の場合の賃金額×(取得した時間÷労使協定で定めた1日分の時間数)
【例】1日有給を取得したときの賃金が10000円、労使協定で定めた1日分の時間数が8時間で、3時間の時間単位年休を取得した場合、「10000円×(3/8)」で3750円です。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
時間単位の有給休暇についてよくある質問
労働者が有給休暇を取得しやすくするための時間単位年休ですが、導入し実際に運用すると、さまざまな問題・疑問点が生じます。
- Qフレックスタイム制に時間単位の有給休暇を取り入れるには?
- Q休憩時間をまたいで時間単位年休の申請があったら?
- Q時間単位の有給休暇を残したまま未導入の事業場に異動したら?
- Q年度途中で所定労働時間が変更になったら?
- Q時間単位の有給休暇を繰り越す場合は?
時間単位年休の管理は勤怠管理システムで
時間単位年休は労働者にとっても使用者にとってもメリットが大きく魅力的な制度です。
ただし、導入後の運用は労務管理者にとって大きな負担となり、特に残り時間の管理などは、手動管理では無理があります。
勤怠管理システムを導入することで、労使協定の内容に応じた対象者の設定から取得時間の管理まで一括で処理可能です。時間単位年休の有効活用のためにも、勤怠管理システム導入をおすすめします。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。