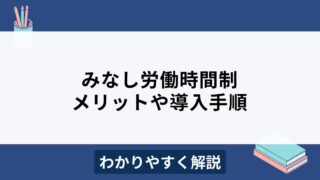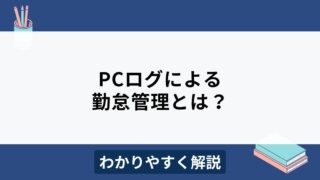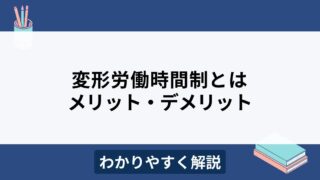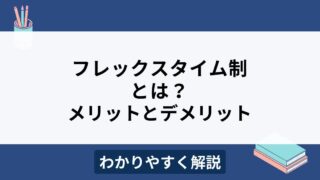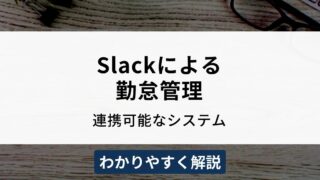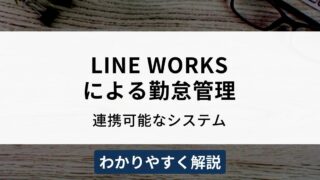- テレワークは、本当の労働時間がわからない
- テレワークだと、コミュニケーションが取りづらい
働き方改革やコロナ禍を受けて、すっかり浸透・定着したテレワーク(リモートワーク)ですが、このような悩みを持つ方も多いのではないでしょうか?
テレワークは、通勤の煩わしさから解放され、柔軟な働き方が実現できる一方で、管理者側からは多くの課題も耳にします。
この記事では、テレワークの勤怠管理に苦心されている事業主や管理者、労務担当者の方向けに、課題に応じた有効な対策やサポートツールの選び方について、わかりやすく解説します。
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
テレワークとは
テレワークとはオフィスに出社せず、遠隔地でICTを活用しながら業務を進める働き方を指します。テレワークは、「離れて(tele)」と「働く(work)」を組み合わせてできた造語です。
テレワークには、内勤型の「在宅勤務」と外勤型の「モバイルワーク」「サテライトオフィス」といった種類があります。主に、以下のようなメリットがあるとされ、コロナ禍なども相まって近年導入する企業が急増しています。
- 通勤ラッシュが回避できる
- 時間を有効活用できる
- ライフスタイルに合わせて柔軟な働き方が可能となる
テレワークの勤怠管理における課題とは
テレワークを導入する企業が増えた一方で、勤怠管理の難しさから早々に廃止したり運用を改めたりする事例も少なくありません。ここでは、以下のような課題について、個別に解説します。
- 実際の勤務状況が見えにくい
- コミュニケーション不足になりがち
- 人事評価が難しくなる
- セキュリティが不安
テレワークは実際の勤務状況が見えにくい
テレワークはオフィスワークと異なり、出退社や休憩といった勤怠の切れ目が見えないため、従業員の勤怠状況を直接確認できません。PCのログイン状況の記録や勤怠管理システムを導入していない限り、出退勤時刻や残業時間は自己申告となります。
結果として、適切な勤怠管理のガイドラインとして示されている「使用者自身が確認・記録を行うこと」「客観的な記録を基礎として確認・記録を行うこと」のいずれもが困難となってしまいます。
テレワークはコミュニケーション不足になりがち
テレワークは、物理的に離れた場所で就業するため、新人研修や全体会議など、同一空間で行うことを前提とした業務が難しくなります。
また、ちょっとした質問や相談などがしづらく、連絡不足から業務に支障を来すことも考えられます。
テレワークは人事評価が難しくなる
実際に勤務している様子が見えないため、働きぶりに対する評価が難しくなります。
エンジニアや営業職であれば、具体的な成果物や営業成績といった判断材料がありますが、事務職などのバックオフィスは業務の成果が見えづらいため、余計に公正な評価がしづらくなります。
テレワークはセキュリティが不安
カフェやコワーキングスペースでの勤務の場合は、他人の覗き見(いわゆる「ショルダーハック」)などによる情報漏洩のリスクが考えられます。
そのため、ノートPCに画面ロックを設定する、離席時はスマートフォンを必ず所持するなど、外出先で作業を行う場合のルール作りが必要となります。
店舗がサービスで提供している無料Wi-Fiは、通信のやりとりが暗号化されていないことが多く、機密情報の流出やサイバー攻撃を受ける可能性が高くなります。
また、在宅勤務の場合も、社外ネットワークに接続することによるデータ流出のおそれがあります。DLPやEDRといったセキュリティツールを導入し、機密情報保護の体制強化に努める必要があります。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
テレワークの勤怠管理への対策
テレワークを導入した場合に有効と考えられる勤怠管理として、以下の4種類をご紹介します。
- 電話やメール、チャットツールによる連絡
- Web会議ツールを常時接続
- みなし労働時間制を採用
- 勤怠管理システムを導入
メリット・デメリットはそれぞれありますが、勤怠管理システムの導入が最も効果的と言えるでしょう。
電話やメール、チャットツールによる連絡
出退勤時や休憩に入るタイミングなど、業務開始や区切りのタイミングで報告を義務付ける方法です。オンとオフの切り替えを図りやすく、メリハリのある働き方につなげられます。
連絡手段としては、チャットツールが最も効果的でしょう。電話は、場所によっては通話そのものが難しく、また始業時間近くに集中して繋がらないということも多いため、現実的ではありません。
また、メールも部署の従業員数×件数をチェックしなければならず、管理者への負担が大きくなります。対して、チャットツールは、履歴を確認する必要はありますが、勤怠打刻が可能なツールもあるため、効率よい勤怠管理が可能となります。
Web会議ツールを常時接続
ZoomやMeetといった、Web会議ツールをカメラオンの状態で、各従業員に常時接続させる方法です。仕事に取り組んでいる状況が把握できるため、管理者にとっては業務の進捗状況を把握しやすくなります。
必要に応じてオンライン会議もスムーズに開催できるため、コミュニケーション不足を解消できる点もメリットです。
一方で、従業員側にとっては、一挙手一投足が監視されているような感覚を覚え、仕事がやりづらくなるといった面もあります。自社勤務以上の緊張感やプレッシャーを与える可能性もあり、歓迎される方法とは言えません。
みなし労働時間制を採用する
事業場外労働のみなし労働時間制を採用することで、実労働時間に関係なく、所定労働時間や業務遂行に必要な時間、労働したとみなすことができるようになります。
ただし、テレワークに対して事業場外労働のみなし労働時間を適用するためには、以下2つの要件を満たす必要があります。
- 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態とされていないこと
- 随時、使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと
要約すると、チャットツールや電話、メールで、使用者から業務に関する具体的な指示を受けていない場合のみ、適用可能ということになります。使用者から指示が送られず、通信のやりとりも遮断する状態にするのは考えにくく、導入は難しいでしょう。
また、同じみなし労働時間制である裁量労働制は、専門業務型と企画業務型のいずれも適用職種や事業場の要件が決まっており、対象となる労働者は限定的と言えます。
勤怠管理システムを導入する
勤怠管理システムの導入は、コスト面さえクリアできるのであれば、非常に効果的な方法と言えます。
スマートフォンアプリ・GPS・生体認証など、多彩な打刻方法を搭載しており、場所を問わずスムーズな打刻が望めます。データコピーが困難な認証方法も多く、不正打刻を心配する必要はありません。
また、労働時間・残業時間・有給休暇の取得状況など、労務管理に必要なデータ集計は、システムへ一任できます。一方、ワークフローを活用すれば、残業や休暇申請をシステム上で行えるため、従業員にとってもメリットが大きいです。
確かに導入コストはかかるものの、現在では低コストで高機能な勤怠管理システムが、市場に多数登場しています。クラウド型のシステムであれば初期費用が不要な製品も多く、無料お試しや利用人数による従量制で、無駄な費用がかからないようになっています。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
テレワークに最適な勤怠管理システムの選び方
テレワークの課題を解決するために求められる要件という観点から、どのようにシステムを選べばよいのかを解説していきます。ポイントは、以下の3点です。
- 勤怠状況が適切に把握できるか
- 様々な勤務形態に対応できるか
- 外部ツールと連携可能か
勤怠状況が適切に把握できるか|作業の記録は?
作業状況の把握が、出退勤、休憩打刻のタイミングだけでなく、どの範囲まで可能かという点です。
具体的な機能要件としては、作業端末のアクティブ時間や操作ログ、作業画面のキャプチャ取得などは可能かという点について、確認することになります。
様々な勤務形態に対応できるか|フレックスタイム制や変形労働時間制は?
テレワークと、変形労働時間制やフレックスタイム制などを併用することは考えられ、こうした多様な勤務形態にどこまで対応しているかといった点も重要となります。
たとえば、フレックスタイム制の場合であれば、従業員が自由に出退勤時間を設定できるため、就業規則上の始業時間に打刻がなくても遅刻扱いにならないか、といった要件が考えられます。
また、変形労働時間制の場合であれば、労働日ごとに所定労働時間が異なるため、管理者はもちろん、従業員側からもいつでも日ごとの所定労働時間の確認できるか、といった要件が求められます。
外部ツールと連携可能か|SlackやLINE WORKSの活用は?
給与計算システムとの連携できる勤怠管理システムは多くありますが、その他にもプロジェクト管理ツールや費用管理ツールとの連携が可能であれば、さらなる業務効率改善を図れます。
また、LINE WORKSやSlackといったビジネスチャットツールと連携していると、勤怠打刻の効率化に加え、コミュニケーションツールとしても活用できます。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
テレワークの勤怠管理についてよくある質問
テレワークの勤怠管理について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
- Qテレワークは長時間労働になりやすい?
- A
「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)や「テレワークに関する調査2020」などにおいて、テレワークが長時間労働につながるおそれがあることが指摘されています。
これは、「使用者と離れた場所で勤務をすることにより、管理が行き届かなくなる」「労働時間とプライベートの時間との境目があいまいになる」などが要因と考えられています。
- Qテレワークの費用負担はどうなる?
- A
オフィスで勤務する場合と異なり、テレワークの場合は労働者に費用負担が生じることになります。そのため、以下のような事項については、あらかじめ労使で協議のうえで、テレワーク勤務規程や就業規則等に定めておきましょう。
- 発生した費用は、労使がどのくらいの割合で負担するのか
- 使用者が負担する場合における限度額
- 発生した費用の請求手続き
対象となる費用の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- ネットワーク通信費
- 情報通信機器・周辺機器・備品等の購入費用
- サテライトオフィス・コワーキングスペース等の利用料
勤怠管理システムでテレワークに相乗効果を
使用者に求められる労働時間の管理義務は、テレワークであっても変わりません。オフィスワークに比べ、勤怠状況の把握が難しいテレワークの勤怠管理は、システムの活用が不可欠です。
また、勤怠管理システムと連携したビジネスチャットツールなどを利用すると、コミュニケーションをスムーズに交わせます。多様な働き方の実現にもつながり、従業員のエンゲージメントも高まります。
「勤怠管理システムの選定・比較ナビ」をご利用いただくと、テレワークに活用できる勤怠管理システムの中から、自社に最もマッチングするシステムが見つかります。テレワークでの勤怠管理にお悩みの方は、勤怠管理システムの選定・比較ナビを是非ご利用ください。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。