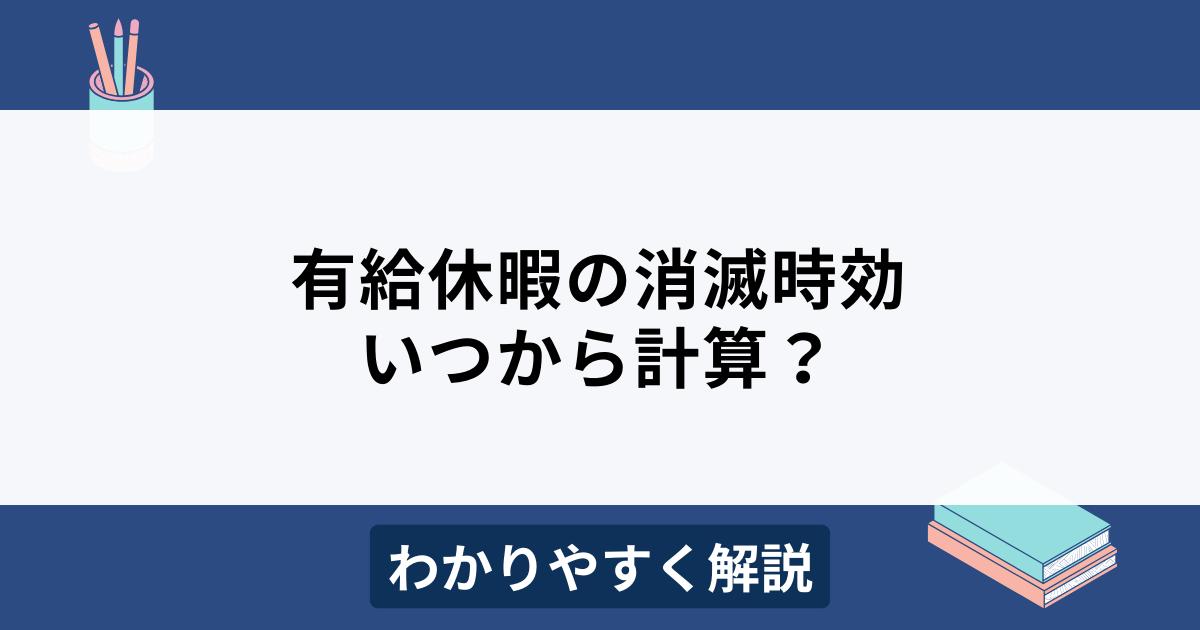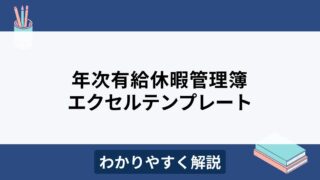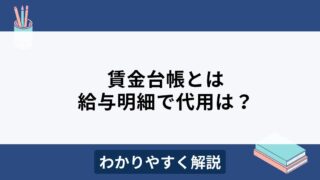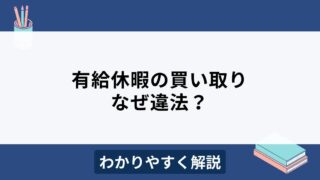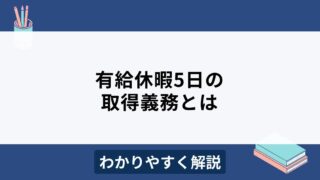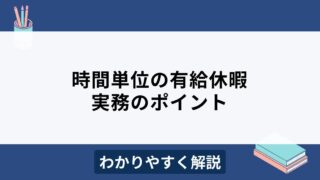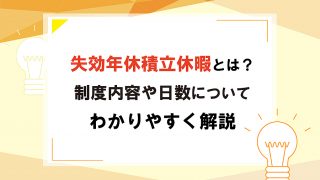年次有給休暇は、付与された日から2年を経過すると時効により消滅します。1年経過時に未消化分として翌年度に繰り越せる日数にも上限があります。前年度繰越分は、当年度付与分と分けて管理する必要があり、人事労務担当者の頭を悩ませる部分でもあります。
この記事では、有給休暇の消滅時効に関する基本的な考えと、繰越計算の方法、実務上の疑問点などについて、わかりやすく解説します。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
有給休暇の消滅時効は2年(労働基準法第115条)
2020年4月1日に施行された改正民法では、消滅時効の規定が改正されて、債権の種類に関係なく原則「事実を知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年」となりました。
これと同じタイミングで、労働基準法でも消滅時効の改正があり、賃金請求権の時効が2年から5年(当面は3年)に引き上げられました。また、賃金台帳などの記録の保存期間も、3年から5年(当面は3年)に引き上げられました。
しかし、有給休暇の消滅時効は変更なく、2年のまま据え置かれています。
(時効)
第百十五条この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
有給休暇の付与日数
有給休暇は、下記2つの要件をクリアしていれば、入社6ヶ月経過後に付与され、それ以降は1年ごとに付与日数が加算されていきます。
- 雇用された日から6ヵ月間継続勤務している
- 全労働日の8割以上出勤している
それぞれ、フルタイム労働者およびパートやアルバイトの有給休暇の付与日数は、下記のとおりです。
フルタイム労働者の有休付与日数
週所定労働日数5日以上または週所定労働時間30時間以上の労働者の付与日数は以下の表になります。
| 継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
短日・短時間労働者の有休付与日数
週所定労働日数4日以下かつ週所定労働時間30時間未満の労働者の付与日数は以下の表になります。
| 週所定 労働日数 | 1年間の 所定労働日数 | 継続勤務年数(年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | ||
| 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
消滅時効はいつから計算?
有給休暇の消滅時効の起算日は、有給休暇が付与された日であり、起算日から2年で消滅します。
たとえば「初年度は原則通り入社6ヶ月で付与、以降は毎年4月1日に付与」と規定している会社において、「2023/8/1入社の労働者に付与された有給休暇の消滅時効」は、以下のとおりになります。
- 入社日(2023/8/1)から6か月経過した2024/2/1に初年度分10日が付与されます。
- その後、2024/4/1に1年6ヶ月付与に相当する日数(11日)、2025/4/1に2年6ヶ月付与に相当する日数(12日)が、それぞれ付与されます。
上記のケースで、1.つまり初年度10日分の消滅時効は、あくまでも付与日(2024/2/1)から2年後の2026/2/1です。また、2回目付与の11日分は2026/4/1、3回目付与の12日分は2027/4/1に時効により消滅します。
有給休暇の買い取りは原則違法
有給休暇の買い取りは、原則認められておらず、会社が有給休暇を買い取って消滅させることは違法となります。
ただし、消滅時効が迫っており消化しきれない有給休暇分については、労働者の有給休暇取得の権利を侵害することにならないため、買い取りは認められています。
なお、労働者などから「有給休暇を買い取って欲しい」との申し出があったとしても、会社は買い取りに応じる義務はありません。ただし、就業規則に「時効や退職により期日までに消化できない有給休暇については、会社がこれを買い取る」と明記されている場合は、会社は有給休暇の買い取る義務が発生します。
労働者と無用なトラブルを防止するためにも、買い取りに関して、就業規則にきちんと盛り込んでおくことをおすすめします。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
有給休暇の繰越計算方法
労働者が消化していない有給休暇は、翌年度に繰り越すことができます。しかし、翌年度に繰り越した有給休暇は、現実に付与された日から起算して2年で消滅するため、その管理は慎重に行う必要があります。
最大付与日数は40日?
当年度に有給休暇を消化しきれずに翌年度に繰り越す場合、繰越可能な日数は最大20日までとなっています。
例えば、継続勤務6年6ヶ月のフルタイム労働者に有給休暇20日分が付与され、これをすべて未消化のまま翌年度に繰り越したとします。この場合、前年度の繰越分20日と当年度に新たに付与された20日を加えて、最大の有給休暇付与日数は40日となります。
ただし、会社が途中で付与基準日(前倒し付与)を変更したケースでは、有給休暇付与日数が最大60日になる可能性があります。
取得日数のカウント方法
取得した有給を、前年度繰越分から差し引くか新規付与分から差し引くかについては、法律上の定めはありません。ただし、一般的には先に時効消滅する前年度繰越分から差し引くことになっています。
たとえば、前年度繰越分5日、当年度付与分11日を所持している労働者が1日有給休暇を取得した場合、先に時効の到来する前年度繰越分5日から1日を差し引きします。よって、繰越分の残日数は4日となります。
また、年次有給休暇の取得義務5日分については、この前年度繰越分として差し引きした休暇についてもカウント可能です。
時間単位年休の繰り越し
時間単位年休も繰り越しの対象となりますが、次年度分の時間単位年休の日数は、繰越分を含めて5日以内となります。
たとえば、所定労働時間8時間の事業場において、ある労働者が通常の有休を2日分、時間単位年休を5時間分、次年度に繰り越す場合、次年度付与日数が11日とすると最終的に付与される有休は13日と5時間ということになります。
そして、このうち時間単位年休として取得できるのは、あくまでも5日分つまり8×5=40時間分までであり、繰り越した5時間分を加算して45時間分取得可能となるわけではない点に注意が必要です。
失効年休積立休暇を利用する
失効年休積立休暇とは、本来であれば時効消滅するはずの有給を積み立てておき、必要なときに使えるようにする制度です。
たとえば、前年度繰越分で消化しきれずに消滅時効を迎える有給を積み立てておくことで、病気などで長期の休業を余儀なくされた場合など、減収を抑えながら休養に専念することができます。
積立休暇は、法律で規定されている制度ではありませんが、労働者への福利厚生の一環として制度に取り入れ、有給の活用を図っている企業も多くみられます。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
有給休暇の時効消滅についてよくある質問
有給休暇の時効消滅について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
- Q会社が消滅時効を短縮することはできる?
- Q時効消滅後に事後申請があった場合は?
有給休暇は消滅する前に取得してもらう
有給休暇は、労働者によって付与タイミングが違っていると管理が煩雑になり、労働者本人も気づかないうちに時効消滅していたという事態になりかねません。
勤怠管理システムを導入することによって、労働者ごとに付与基準日、付与日数、取得日数が一括管理できるため、「思わぬ消滅」を防止することができ、労働者の安心感も高まります。労働者が安心して労務管理を委ねることができる職場づくりのために、勤怠管理システム導入を検討してください。
勤怠管理システムの選定・比較ナビは、多くの勤怠管理システムから自社にマッチした最適なシステムを見つけ出せるサイトです。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。