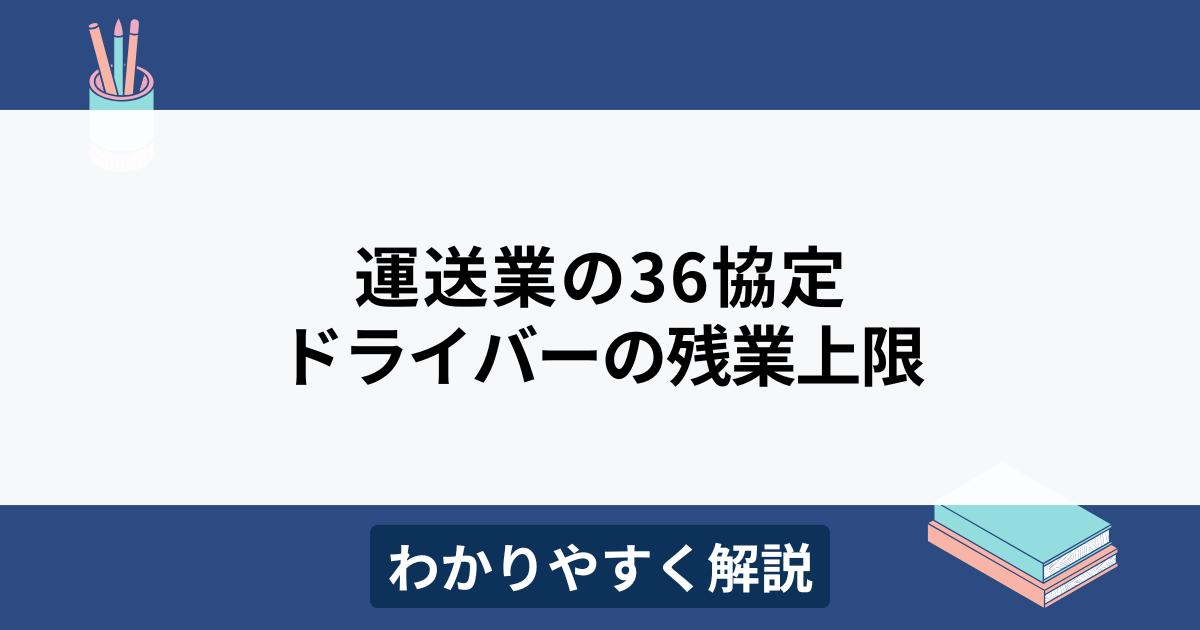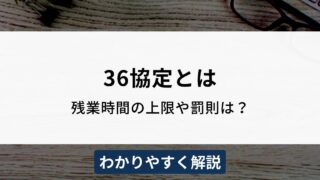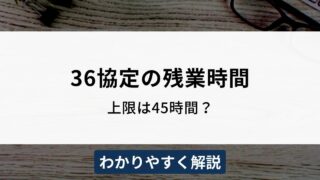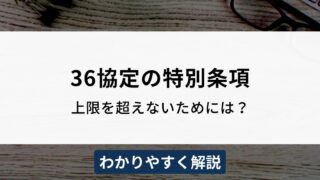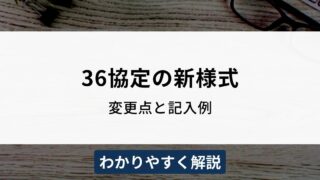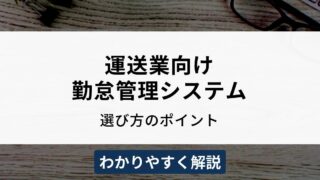2024年4月1日から、36協定による時間外労働の上限規制が、運送業の自動車運転業務にも適用されています。
いわゆる「2024年問題」と言われるこの改正により、具体的な労働時間の上限はどうなったのでしょうか?また、違反した場合はどのような罰則が待っているのでしょうか?
この記事では、2024年度から運送業のドライバー業務に適用されている36協定の上限規制について、わかりやすく解説します。
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
36協定とは?
労働基準法において、労働時間は1日8時間・週40時間までと定められており、これを超える労働を命じるには、「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」を締結し、管轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
この規定が労働基準法第36条に定められていることから、一般的に「36協定」と呼ばれています。また、時間外労働をさせた場合の時間外割増賃金については、36協定の有無に関わらず支払わなければなりません。
ここまで解説した法定労働時間と36協定、割増賃金の規定については、運送業であっても他の業種と同じように適用されます。
特に運送業の自動車運転業務については、現実的に法定労働時間を超えることが避けられないため、ほぼすべての事業場において36協定が締結・届出されているのが実態です。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
2024年4月から、運送業の36協定はどう変わった?
2019年4月に施行された働き方改革関連法に伴い、一般企業には36協定を締結した際の時間外労働時間について、上限が罰則付きで設けられました。
しかし、運送業のうち自動車運転業務に従事する労働者(以下「自動車運転者」)については、以下のような労働形態による事情から改正への早期対応が難しく、適用が5年間猶予されてきました。
- 移動距離や交通事情により労働時間が大幅に変動する
- 労働者自身が移動するため、時間で区切った交代制シフトが不可能である
なお、この猶予措置の対象となるのは、運送業のうち自動車運転者のみです。同じ運送業であっても、事務職や運行管理者などは、一般業種と同様に2019年4月(中小企業は2020年4月)から罰則付き上限規制が適用されている点に注意が必要です。
旧来の運送業(自動車運転者)の36協定は上限規制が適用除外
自動車運転業務に関しては、2024年3月31日まで時間外労働の上限規制対象から外れていたため、法改正前の内容が適用されていました。すなわち、36協定で定める時間外労働については、特に上限基準及び罰則は定められていないという状態でした。
なお、前述したとおり、時間外労働をさせるための36協定の締結・届出は必要であり、自動車運転業務従事者については「様式9号の4」という様式を用いていました。
自動車運転者以外の36協定
自動車運転業務を主たる業務としない労働者は、36協定で定めることのできる時間外労働につき、休日労働を除いて月45時間・年360時間が原則の上限です。なお、1年単位の変形労働時間を導入している場合は、上限が月42時間・年320時間と短くなっています。
また、上限時間を超えて労働させる必要がある臨時的な特別の事情がある場合は、36協定に特別条項を設けることで、さらなる時間外労働が可能となります。ただし、特別条項を適用する場合でも、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 時間外労働(休日労働除く)の合計が年720時間以内
- 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
- 月45時間の上限を超えることができるのは年6回まで
- 時間外労働と休⽇労働の合計が2~6ヶ月平均のいずれも80時間以内
様式は、現在ほかの一般業種に適用されている新様式の「様式9号」(特別条項を設ける場合は「様式9号の2」)を用いることになります。
2024年4月から運送業(自動車運転者)でも36協定の上限が適用されています
2024年4月以降は、自動車運転者についても、36協定で定めることのできる時間外労働の上限が適用されています。
ただし、特別条項を設けた場合の、休日労働を除く時間外労働の合計は年720時間ではなく、960時間となります。また、以下の上限規定については、いずれも適用除外となります。
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 月45時間を超えることのできるのは年6回まで
- 時間外労働と休日労働の合計が2~6ヶ月平均で80時間以内
様式は、一般業種と同じく新様式の「様式9号」(特別条項を設ける場合は「様式9号の2」)を用いることになります。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
運送業の36協定の記入例 ※2024年4月1日以降の36協定には使用不可
運送業のうち自動車運転者についての36協定届は、適用が猶予されていた2023年3月31日までは「様式第9号の4(適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務:自動車運転者、建設業、医師等)」を使用していました。
また、2024年4月1日以降に締結された36協定は、原則的には一般の事業・業務と同じ「様式第9号及び第9号の2(特別条項つき)」を使用します。
2023年3月31日までに締結された36協定(様式第9号の4)
「様式第9号の4」の書式テンプレートは、厚生労働省のサイトの以下のリンクより、ダウンロード可能です。
様式第9号の4(Word形式)
事業場の種類・名称・所在地
事業場の種類、名称(支店、営業所など)や所在地(電話番号を含む)を記載します。36協定は原則、事業場ごとにそれぞれ締結しなければなりません。よって、事業場が複数ある場合は、それぞれ事業場ごとに書面を作成する必要があるため、注意してください。
時間外労働をさせる必要のある具体的事由
使用者が時間外労働を命令しなければならない、具体的な理由を記載します。たとえば自動車運転者であれば「繁忙期への対応」などと記載します。「使用者の判断による」など、抽象的な表現は認められません。
業務の種類
時間外労働を必要とする具体的事由に対応する職務を、なるべく具体的に記載します。たとえば「自動車運転者」「運転手」などと記載します。
労働者数
該当業務に従事するもののうち、満18歳以上の人数を記載します。なお、満18歳未満の労働者は、原則的に時間外労働・休日労働を命じることはできません。ただし、そもそも満18歳未満は自動車運転免許の取得ができないため、この欄に関してはあまり気にする必要はないでしょう。
所定労働時間
会社が就業規則等で定める1日の所定労働時間を記載します。一般事業の様式(様式第9号)ではこの欄は任意記載となっていますが、本様式では「(任意)」の文言がないため、必須項目とされています。
延長することができる時間数(1日)
業務ごとに、1日の延長時間数を記載します。特に上限は設けられておらず、ここに記載した時間数を超えたとしてもただちに違法となるわけではありませんが、次章で解説する「改善基準」に従って、適切な時間を設定しましょう。
1日を超える一定の期間(起算日)
1ヶ月や1年などの一定期間の範囲内で、延長することができる時間数を記載します。自動車運転者の場合は、告示により2週間及び1ヶ月以上3ヶ月以内の期間を設定するものとされており、具体的には「2週間:40時間、1ヶ月:80時間、1年:800時間」のように記載します。
また「起算日」には、期間の始期となる具体的な日付を記載します。
期間
定めた内容が適用される対象期間を記載します。通常は「起算日より1年間」を記載します。
休日労働に関する事項(所定休日)
会社が就業規則等で定める所定休日を記載します。具体的な曜日が特定されている場合はその曜日を、曜日が特定されていない場合は「週休2日」などと記載します。
休日労働に関する事項(労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻)
法定休日(週1日または4週を通じて4日)のうち、休日労働を命じることのできる日数とその日における始業・終業時刻を記載します。具体的には「月に2日、9:00~20:00」などと記載します。告示により自動車運転者の休日労働は、2週間に1回以内とされています。
なお、所定休日における労働は、ここで言う休日労働には該当せず、上段の時間外労働に含まれるため、注意しましょう。
代表者に関する事項
協定の当事者である過半数労働組合の名称、もしくは過半数労働者代表の職名・名前・選出方法などを記載します。なお、管理監督者は過半数労働者代表になれませんが、職名が紛らわしい場合は「(管理監督者ではない)」などと付記しておくと良いでしょう。
チェックボックス ※2箇所
上記で記載した代表者が、「間違いなく過半数労働組合または過半数労働者代表であること」及び「管理監督者でなく、かつ民主的な方法(投票、挙手など)によって選出されたこと」を確認するためのチェックボックスです。
2箇所のチェックボックスのうち、どちらかでもチェックが漏れていると受理されないため、注意しましょう。
2024年4月1日以降に締結された36協定(様式第9号及び第9号の2)
2024年4月1日以降に締結された36協定は、基本的に一般業種と同じ様式第9号(一般条項のみ)及び様式第9号の2(特別条項つき)を使用します。こちらの記載例については、以下の記事にて解説していますので、ぜひご覧ください。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
自動車運転者の労働時間の改善基準とは
自動車運転業務従事者については、36協定の上限規制とは別に、厚生労働省が定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下、「改善基準」)に従って労働時間を管理する必要があります。
1日の拘束時間と休息期間
1日の拘束時間は、原則13時間が上限です。ただし、間に連続8時間以上の休息期間を設けることで最大16時間まで延長できます。
拘束時間とは、労働時間(手待ち時間含む)と休憩時間を合わせた時間を指します。また、休息期間とは、労働基準法が定める休憩時間とは異なり、業務と業務の間における継続8時間以上のインターバルとされています。
拘束時間が1日15時間を超えることができるのは、1週間につき2回までです。
なお、業務の都合上、継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合は、代替措置として、1日における休息期間を分割し、継続4時間以上・合計10時間以上の付与とすることも可能です。
ただし、この分割付与は常に認められる訳ではなく、一定期間(2~4週間程度)における全勤務の1/2までとすることとされています。
1ヶ月及び1年の拘束時間
1ヶ月の拘束時間は、原則293時間が上限です。ただし、労使協定を締結することにより、1年のうち6ヶ月までは月の上限を320時間まで延長可能です。この労使協定は、36協定とは異なるため混同しないよう注意しましょう。
なお、労使協定を締結した場合でも、年間の総拘束時間は3,516時間(293×12か月)を超えてはなりません。
1日及び週の運転時間
1日の運転時間は「2日平均で9時間以内」、週の運転時間は「2週平均で44時間以内」とされています。
連続運転時間は4時間までで、4時間を超えて運転させる場合は連続30分以上(分割する場合は1回につき10分以上)の中断が必要です。運転の中断とは、必ずしも休憩である必要はなく、たとえば4時間運転後に30分の荷積み作業をしても、運転から離脱しているため問題ありません。
2人乗務の特例
同じ車両に2人以上のドライバーが同時に乗務する場合は、交代により休息が取れるため、1日の最大拘束時間を20時間まで延長できます。また、休息期間は4時間まで短縮可能です。
ただしこの特例は、車両内に身体を伸ばして休息できる設備がある、つまりベッド付き車両である場合に限られます。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
運送業の36協定についてよくある質問
運送業の36協定について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
- Q運送業の36協定の新様式は廃止?
- A
2024年4月以降は、運送業(自動車運転業務)の36協定の様式は、一般業種と同じ新様式の「様式9号」(特別条項を設ける場合は「様式9号の2」)に統一されました。
よって、経過措置として暫定的に使用されてきた「様式第9号の4」は、2024年3月31日をもって廃止となっています。
- Q運送業の36協定の上限は?
- A
2024年4月以降は、運送業(自動車運転業務)についても、一般業種と同じく原則月45時間・年360時間(休日労働を除く)の上限規制が適用されます。
ただし、特別条項を設けた場合の上限規制については、一般業種とは以下のような違いがあります。
- 時間外労働(休日労働を除く)の合計は年960時間
- 以下の規制が適用外
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 月45時間を超えることのできるのは年6回まで
- 時間外労働と休日労働の合計が2~6ヶ月平均で80時間以内
勤怠管理システムで運送業の労働時間管理を効率化
運送業は、ドライバーの過重労働という慢性的な課題を抱えており、2024年問題に対する早急な対策が必要です。現時点でも、ドライバーと他の職種に携わる従業員の間で異なる上限規制が混在しており、労働時間の管理は複雑化しています。
GPS打刻やデジタコ連携など、運送業向けの機能を備えた勤怠管理システムを導入することで、適切な勤怠管理が可能になります。労働時間・残業時間・有給休暇の取得状況など、個々のドライバーの勤怠データを正確に管理できる点がメリットです。
勤怠データの集計~反映まで、一連の作業を勤怠管理システムへ一任できるため、ドライバーにも安心感を与えられます。
「勤怠管理システムの選定・比較ナビ」をご利用いただくと、運送業の労務管理をサポートしてくれる勤怠管理システムの中から、自社に最もマッチングする製品を探し出せます。勤怠管理の工数増大にお悩みの方は、勤怠管理システムの選定・比較ナビを是非ご利用ください。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。