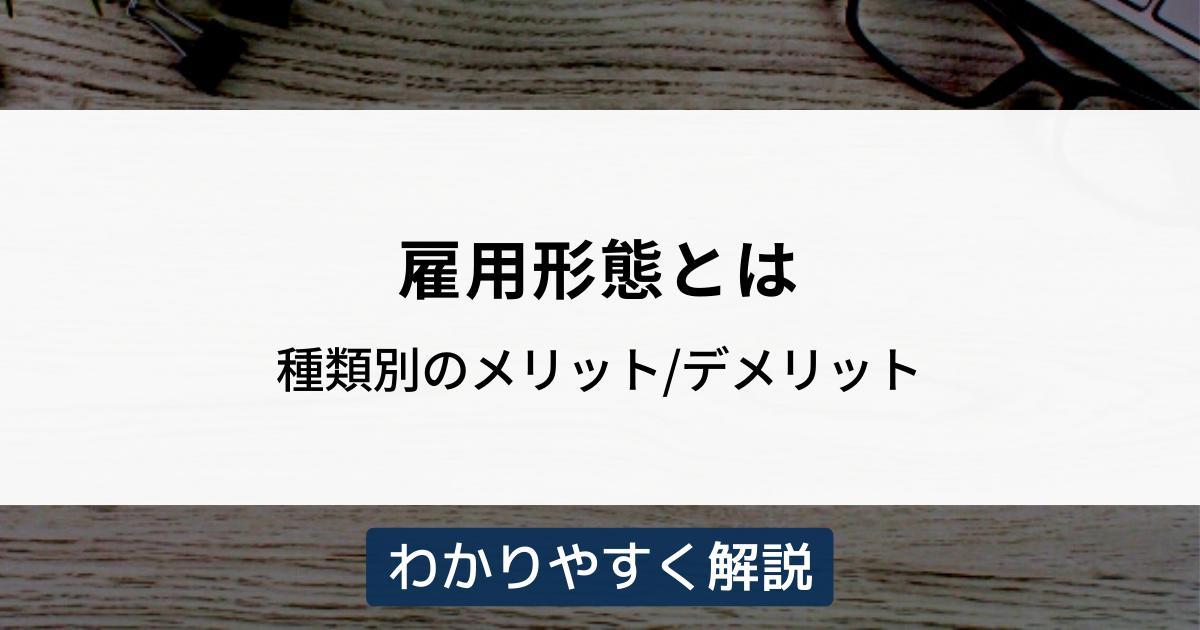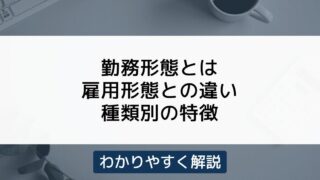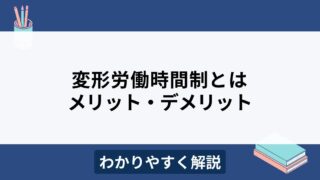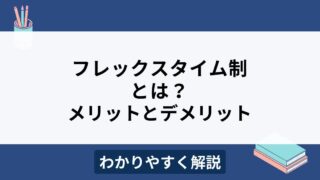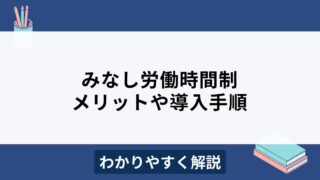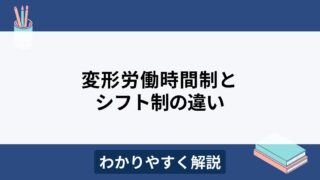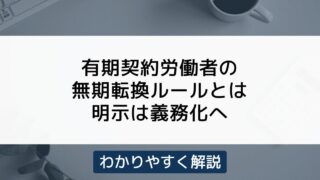雇用形態には、正社員、契約社員、パートタイマー・アルバイト、派遣社員など、さまざまな種類があります。近年では、働き方改革や多様なライフスタイル・ニーズに対応するため、雇用形態も多様化が進んでいます。
それぞれの雇用形態には、メリットとデメリットがあり、事業の規模や業種に応じて適切な雇用形態を設定することが重要です。また、それぞれの雇用形態の管理上の注意点や、雇用形態を変更する場合の手続きなども押さえておく必要があります。
この記事では、雇用形態の種類別のメリット・デメリットや選択のポイント、雇用形態変更の手続きなどについてわかりやすく解説します。
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
雇用形態とは?
雇用形態は、正社員・パート・アルバイト・派遣社員などのように、雇用契約上の社員の身分であり、雇用契約時の労働者の労働条件や待遇の違いをいいます。
雇用形態は主に、「直接雇用もしくは間接雇用」「有期契約もしくは無期契約」「フルタイムもしくは短時間労働」によって分類されます。近年、さまざまな雇用形態による人材の採用活動が活発化しており、それぞれの本質を理解することが採用成功へのカギになっています。
雇用形態の種類と特徴
雇用形態には、正社員、契約社員・嘱託社員、パートタイマー・アルバイト、短時間正社員、派遣社員、業務委託・フリーランス、在宅ワーカーなどがあります。それぞれの雇用形態には、労働条件や待遇に違いがあります。
勤務形態や就業形態とどう違う?
勤務形態は、「どの時間帯に働くか」「どういったペースで働くか」「勤務時間の管理をどうするか」など、労務管理上の具体的な働き方による区分を指します。また、「就業形態」という言葉もありますが、こちらは雇用形態とほぼ同じ意味で使われています。
固定時間制(通常勤務)
固定時間制(通常勤務)とは一般的な勤務形態で、1日8時間・週40時間という法定労働時間で労働する勤務形態です。
変形労働時間制
変形労働時間制とは、月や年単位で労働時間を調整する労働時間制で、一定の期間の中で、総枠が決められた労働時間をやりくりする制度です。
フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、労働時間の設定を労働者に委ねる制度であり、労働者は始業時刻と終業時刻を自由に設定可能です。
みなし労働時間制
みなし労働時間制は、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた労働時間分を働いたとみなす制度です。みなし労働時間制には大きく分けて、「事業場外みなし労働時間制」と「裁量労働制」の2種類があります。
シフト制
シフト制や交替勤務制は、複数の労働者が勤務する曜日や時間帯ごとに異なる勤務形態です。飲食業・小売業・サービス業・介護業などで多く見られます。
事業の状況に合わせた雇用形態の設定
会社の規模や業種によって、適した雇用形態が異なります。大規模で経営的にも安定している会社であれば、正社員を中心とした雇用形態が適しています。一方で、小規模で経営状況が不安定な場合は、契約社員やアルバイトなどの柔軟な雇用形態が多く採用されています。
また、会社の経営状況に応じて、雇用形態を変更したり調整したりすることがあります。会社の利益に対して人件費が相対的に高くなっている場合は、正社員を削減して契約社員やアルバイトに置き換えるなど、よりコストを抑えられる雇用形態を選択することもあります。
ただし、ただ単に「コスト削減」という理由のみで雇用形態を変更することは難しく、また変更できたとしても、長期的には人材確保や組織の安定性に影響を及ぼす可能性があります。雇用形態の変更には、柔軟さとともに慎重さも求められることも意識しておきましょう。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
正社員雇用のポイント
正社員は「正規社員」とも呼ばれており、一般的には就業規則などで所定労働時間が定められている「フルタイム社員」を指します。正社員は、原則、雇用期間(労働期間)に定めがなく、会社との「直接雇用」である点や、収入が安定しているのが特徴です。
正社員の特徴
正社員とは、会社に正式に雇用され、基本的に無期契約・フルタイムを前提に働く労働者を指します。正社員は社会保険や退職金などの福利厚生が充実しており、安定した収入が期待できます。また、会社側も長期的に人材を確保できるメリットがあります。
正社員を雇うメリット
- 企業の安定性が高まる
- スキルアップが期待できる
- 社員のモチベーションが向上する
正社員は会社にとって、長期的な雇用関係を築ける労働者です。そのため、会社の安定性を高めることができ、労働者のスキルアップに長期的な視点でに取り組めます。
また、正社員は、安定した労働条件や福利厚生を受けることができるため、働きがいを感じやすく、モチベーションやエンゲージメントが向上しやすい点もメリットです。
正社員を雇うデメリット
- 人件費が高い
- 雇用形態の柔軟性が低い
- 雇用のリスクが高い
正社員は、無期雇用が前提で待遇も他の雇用形態に比べて良いのが一般的です。そのため、会社が給与や福利厚生などの労働条件を充実させる必要があり、人件費が高くなります。
また、一度正社員として契約すると、あとからミスマッチだったとしても他の雇用形態に転換するのは難しく、柔軟性も乏しいと言えます。解雇となると更に難しく、採用時の検討が不十分な場合、思わぬリスクを抱えることも考えられます。
正社員を雇う上での注意点
正社員を採用する場合、採用時の選考基準を明確し、採用プロセスを透明性を高めることが重要です。
まず、求人票を作成する段階で、正社員で求めるスキルや経験、学歴などを明確にしておきます。採用後に正社員としての適性や能力が足りないとわかっても、簡単に解雇や雇用形態の変更はできません。
採用後には、新入社員教育や社内研修、OJTなどを行い、育成サポートをすることが大切です。特に新卒の場合は、初めての職場や業務に不安を感じることが多いため、フォロー体制の充実度は、採用後の定着率にも影響します。
正社員の労働条件は、他の雇用形態の従業員を雇う際の基準となるため、労働基準法などに沿って、しっかり決めておきましょう。また、正社員は会社にとって主力であるため、キャリアアップ制度や福利厚生を充実させることで、モチベーションや定着率アップに繋がります。
契約社員・嘱託社員雇用のポイント
契約社員は、基本的に雇用期間が定められている労働者を指します。ただし、一定の要件のもとで無期雇用に転換して、無期契約社員となる場合もあります。また、定年後再雇用した社員を嘱託社員と呼びますが、会社によっては契約社員と同じ意味で使っている場合もあります。
期間の定めのある労働契約は、労働者と使用者の合意により契約期間を定めており、契約期間の満了によって労働契約は自動的に終了します。1回あたりの契約期間の上限は、一定の場合を除いて3年です。
契約社員・嘱託社員の特徴
契約社員とは、会社と一定期間の有期雇用契約を締結して雇用される労働者を指します。定年制度や退職金などの福利厚生がない場合が多く、雇用期間が短いため、安定性に欠ける面があります。一方、会社側にとっては業務の増減に合わせた人員調整がしやすいため、柔軟な雇用形態として利用されます。
契約社員・嘱託社員を雇うメリット
契約社員・嘱託社員は、一般的に正社員よりも待遇が低めに設定されるため、人件費の削減が期待できます。また、特定の技能やノウハウを持った人材を一時的に確保できるため、自社の業務拡大に向けた戦略的なリソース配分が可能になります。
契約社員・嘱託社員を雇うデメリット
契約社員や嘱託社員は、契約期間が短いため、業務の継続性や安定性に欠けることがあります。かりに優秀な人材で会社側が永続的な雇用を考えていても、契約更新に応じてくれるとは限らず、貴重な人材を流出させてしまう可能性もあります。
契約社員・嘱託社員を雇う上での注意点
契約社員を雇う上で、契約期間と更新に関する定めは、特に重要です。契約期間は業務内容や需要に合わせて設定するのが基本ですが、短すぎると、採用・研修・退職手続きの負担が増え、コストパフォーマンスが悪くなります。
一方で長すぎると、正社員との待遇格差で不満の声が大きくなったり、業務量が減少しても途中解雇ができなかったりという問題が生じます。
また、契約社員を雇用する場合は「無期転換ルール」についても、しっかり押さえておく必要があります。無期転換ルールは、有期雇用労働者が、契約更新によって同じ会社で5年を超えて働いた場合、本人が希望すれば期間の定めのない無期雇用契約に切り替えられるルールです。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
パートタイマー・アルバイト雇用のポイント
パートタイマーとは、週の所定労働日数や所定労働時間が短く、労働時間が不規則である労働者のことを指します。アルバイトもほぼ同じ意味で使われ、法律上はどちらも「パートタイム労働者」という扱いになります。
パートタイマー・アルバイトの特徴
パートタイマー・アルバイトとは、会社に一定の時間帯や曜日で労働力を提供する労働者を指します。労働時間や勤務日数が少なく、福利厚生は限定的ですが、家庭や学業との両立がしやすいため、主婦や学生などに多く利用されています。
パートタイマー・アルバイトを雇うメリット
- 生産性向上
- コスト削減
- 柔軟な人員配置
繁忙期や時間帯によって、必要な人員が増えた場合、パートタイム・アルバイトを活用することで、比較的容易に人員を確保し、生産性を向上することができます。
また、パートタイム・アルバイトの労働単価は正社員よりも低いのが一般的で、所定労働時間によっては社会保険等の加入義務が無いこともも多いため、人件費の削減が可能です。
さらに、パートタイム・アルバイトは、幅広い時間帯で働けることが多く、スキルや能力に応じて業務を割り振ることができるため、柔軟な人員配置が可能です。
パートタイマー・アルバイトを雇うデメリット
- スキル不足:
- 離職率が高い
パートタイム・アルバイトは、短期間の勤務が多いため、スキルアップや研修の機会が限られます。そのため、正社員に比べ、スキルが不足しがちです。
パートタイム・アルバイトは、労働者の生活環境の変化による離職率が高くなりがちです。典型的な例として、学生アルバイトが卒業を機に別会社に正社員として就職するケースなどが考えられます。そのため、有能な人材であっても、長期的な雇用が難しい面があります。
パートタイマー・アルバイトを雇う上での注意点
パートタイマー・アルバイトは、週の所定労働時間が正社員に比べて短くなることが多く、社会保険の加入条件を満たすことができない場合があります。そのため、雇用契約書などにおいて、労働時間や休暇制度とともに、社会保険の加入可否なども明確にしておくことが重要です。
また、正社員と同じ業務に従事するパートタイマー・アルバイトに対しては、正社員との賃金格差をできる限り無くすことも必要です。差別化を図るのであれば、賃金以外の待遇、たとえば福利厚生や退職金などが考えられます。
パートタイマー・アルバイトは、労働基準法だけでなく、「パートタイム労働法」という法律も適用されるため、通常の就業規則とは別に、パートタイム労働者用の就業規則を別途作成しておくのがおすすめです。
パートタイマーやアルバイトの労務管理は、勤務時間が不規則な場合が多いため、シフト管理が特に重要です。シフト作成前には、従業員の勤務希望を聞いたり、勤務時間を調整することで、シフトの相談に応じることが望ましいでしょう。
また、勤務予定表は事前に作成し、従業員に共有することで、勤務日程の確認や調整が円滑に行えます。これらの業務は、シフト管理機能が充実した勤怠管理システムを活用することで、格段に楽になります。
短時間正社員雇用のポイント
短時間正社員は、所定労働時間がフルタイムより短いこと以外は、基本的に正社員と同じ労働条件や待遇になります。近年の「働き方改革」「働き方の多様化」「ワークライフバランスの向上」など、社会の要請もあり、注目を集めている雇用形態です。
短時間正社員の特徴
短時間正社員とは、フルタイムの正社員(以下、単に「正社員」と呼びます)よりも労働時間が短い正社員を指します。正社員と同様に社会保険や退職金などの福利厚生が充実しており、長期的な雇用が前提となっています。
ただし、労働時間が短いため、給与水準は低めに設定されることが多く、主に育児や介護などの事情によるフルタイム勤務が難しい労働者に適した雇用形態です。
短時間正社員を雇うメリット
- 雇用の安定性が高まる
- スキルアップが期待できる
- フルタイム正社員より人件費を抑えられる
パートタイマーやアルバイトと違い、正社員としての雇用契約を結んでいるため、安定した雇用となります。会社にとって、長期的な視点で有益なスキル取得のための研修・教育などを受けさせることができます。
また、給与がフルタイム正社員に比べて低くなるため、人件費を抑えることも可能です。さらに、短時間正社員制度の導入を社外に発信することで、多様な働き方に対応した会社であることをアピールできます。
短時間正社員を雇うデメリット
- 業務の継続性に課題が生じる
- 退職リスク
- 研修期間や導入期間にかかるコストが高くつく
所定労働時間が少ないため、短時間正社員が担当している業務の引継ぎや連携を工夫する必要があります。また、フルタイム正社員に比べて評価体制やキャリアアップの機会が不十分な場合、モチベーション低下により退職につながる恐れもあります。
短時間正社員を雇う上での注意点
短時間正社員の労働条件については、単に所定労働時間が短いだけでなく、残業や休日出勤も少なくなるため、手当や待遇の調整も検討する必要があります。なお、パートタイマー・アルバイトと異なり、所定労働時間が短くても基本的に社会保険加入義務がある点に注意が必要です。
また、短時間正社員からフルタイム正社員に転換する機会を提供することも大切です。短時間正社員として採用されたものの、フルタイム勤務を希望する場合や、フルタイム正社員から短時間正社員に転じ、再度フルタイム正社員に復帰するケースもあります。
このような場合に備えて、転換の仕組みを整備し、円滑な転換を支援することが求められます。フルタイム正社員に転換することで、それまで加入していなかった社会保険への加入義務が生じることがある点にも留意しておきましょう。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
派遣社員雇用のポイント
派遣社員は、労働者派遣法に基づいた雇用形態の一つで、派遣社員の法律上の雇い主は派遣元(人材派遣会社)です。派遣元は、派遣先との労働者派遣契約に基づいて労働者を派遣し、派遣社員は派遣先の指揮命令下で労働に従事します。
派遣社員には、派遣元との雇用契約が無期限の「常用型」と、派遣先で勤務する間のみ雇用契約が結ばれる「登録型」があります。「常用型」は、派遣先が決まらなくても派遣元との雇用関係があるため、基本的に給与が支払われるのが特徴です。
派遣社員の特徴
派遣社員とは、人材派遣会社に所属して、他社に一定期間労働力として派遣される労働者を指します。一般的に、正社員と比較して待遇面で劣ることが多く、雇用状況も不安定と言えます。一方で会社にとっては、人件費の抑制や人材の迅速な確保ができるメリットがあります。
派遣社員を雇うメリット
- 柔軟な人材配置が可能
- 人事労務の負担軽減
- 余剰人員が出にくい
派遣社員は短期間の雇用が多いため、自社の業務量変動に対応しやすく、すぐに人員の補充が可能です。また、派遣社員の採用、育成、雇用管理等は派遣元にて行われるため、これらの負担やコストが軽減されます。
かりにスキル不足や業務量の減少により、派遣社員が不要となった場合でも、解雇することなく派遣先との調整で済むため、余剰人員を抱えるリスクも減ります。
派遣社員を雇うデメリット
- 人材が育たない
- 派遣元とのトラブルのリスク
派遣社員は自社で直接雇用する労働者でないため、研修や教育が難しく、有能な人材であっても長期的に抱え込むことはできません。また、派遣元との間の派遣契約が不十分だと、時間外労働などを巡って責任の所在があいまいになり、トラブルに発展する可能性もあります。
派遣社員を雇う上での注意点
派遣元と派遣先の関係性は、派遣元が雇用する派遣社員を派遣先に提供する形態の契約です。そのため、派遣元と派遣先双方が労働者派遣契約を交わして、業務内容や賃金、労働時間等について明確に定める必要があります。
派遣社員の派遣期間は、労働者派遣法により原則として最長3年間までと定められています。同じ派遣先で3年を超えて働く場合は、派遣元において「雇用の安定化措置」が取られ、派遣社員の希望に応じて派遣先との直接雇用に切り替える場合もあります。
また、派遣先企業には、派遣社員に対する安全配慮義務があります。具体的には、派遣元に責任を問うことが困難な場合などにおいて、必要な安全教育や指導を行うことが求められます。派遣社員が危険な作業に従事する場合には、必要な安全装置や保護具も提供しなくてはなりません。
業務委託・フリーランスとの契約のポイント
業務委託やフリーランス契約は、自社の事業・業務の一部を他人に委託する契約形態で、民法上の請負契約や委任・準委任契約にあたります。労働者ではなく個人事業主として、特定の業務を委託して成果物に対して報酬を支払います。
業務委託・フリーランスの特徴
業務委託・フリーランスとは、会社などから一定の業務を受託し、自らの責任で遂行する労働形態を指します。雇用契約ではなく、委任契約や請負契約に基づく形態であるため、厳密に言うと雇用形態ではありませんが、本記事では雇用形態の一形態としてご紹介します。
自由度が高く、自分自身のスケジュールに合わせて業務を進めることができる一方で、安定した収入が得られないことも多く、社会保険や損失の補填などはすべて自己責任となるリスクもあります。
業務委託・フリーランスと契約するメリット
・高スキルの人材を短期間で確保できる
・人件費を削減できる
個人で仕事を請け負うには、一定以上の知識やスキルが求められます。よって、必要な業務に対して、即戦力となる専門的なスキルや知識を持っている人材を短期間で確保できます。業務やプロジェクト単位で契約可能なため、解雇リスクなどもありません。
また、雇用契約ではないため、社会保険などは個人事業主が自ら加入する必要があり、会社側は手続きの手間や人件費を削減できます。残業という概念が無いため、割増賃金等も気にする必要がありません。
業務委託・フリーランスと契約するデメリット
- 長期的な戦力にはならない
- コミュニケーション不足の可能性
有能なフリーランスであれば、引く手あまたということもあり、より好条件の案件に乗り換えられる可能性もあります。長期的な戦力としては計算じづらいと言えます。
また、帰属意識が薄い場合が多く、業務の細かな調整・指示といったコミュニケーションが図りにくいおそれもあります。
業務委託・フリーランスと契約する上での注意点
業務委託やフリーランス契約を行う場合には、業務内容、報酬、納期、機密保持、紛争解決方法などについて、契約書に明記することが重要です。特に、業務内容に関しては、細かな作業手順や納品物の形式などを詳細に記載することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
報酬の計算方法や支払いのタイミングについても、明確にしておきましょう。特に支払いのタイミングは、納品物の完成後なのか月末締めなのかといったことの認識が双方で違っていると、トラブルに発展するおそれがあります。
また、残業代や休憩付与の義務がないという理由で、外形だけ業務委託を装い、実態は労働者と変わらない、いわゆる「偽装請負」になってはなりません。時間拘束や業務の具体的指示など、労働者と同じ扱いになっていないか、チェックが必要です。
在宅ワーカーとの契約のポイント
在宅ワーカー(テレワーカー)は、自宅やカフェなどで主に情報通信機器を活用して、業務を行う者を指します。先に挙げた業務委託として成果物を作成または役務を提供します。会社と雇用関係にある労働者が行う「在宅勤務」とは異なるため、混同しないようにしましょう。
ただし、以下のメリット・デメリットや注意点は、在宅勤務者にも当てはまることが多いため、在宅勤務者を抱えている場合は参考にしてみてください。
在宅ワーカーの特徴
在宅ワーカーとは、自宅などで主にパソコンや通信機器を使って業務を行う労働者を指します。高齢者や育児中の女性、身体障がい者など、通勤が困難な人にとって柔軟に働ける形態として注目を集めています。
カフェやコワーキングスペースで業務を行うテレワーカーも、この雇用形態に含まれます。通勤時間や交通費がかからず、自分のペースで仕事を進めることができる一方で、業務内容によっては孤独感を感じやすく、コミュニケーション不足に陥るデメリットもあります。
在宅ワーカーと契約するメリット
- 社内スペースの削減
- 人材確保の幅が広がる
社外で業務を行ってもらうため、オフィススペースやデスクなどのコストを削減できます。また、高度なスキルを持ちながら、身体的理由や家庭の事情などにより通勤が困難な人にアプローチができるため、人材活用の幅が広がります。
在宅ワーカーと契約するデメリット
- コミュニケーションの課題
- 管理が難しい
オフィスで働く労働者と比べて、在宅ワーカーはリアルタイムでコミュニケーションが取りづらいため、情報共有や意思決定の遅延などが発生する可能性があります。また、働いているところを直接確認できないため、業務の進捗状況や品質についての管理が難しくなります。
在宅ワーカーと契約する上での注意点
在宅ワーカーも業務委託の一態様であるため、契約内容の明確化が重要である点は同じですが、特に労働時間の把握に注意が必要です。もちろん、労働者ではないため直接指示や管理はできませんが、在宅ワーカーの健康と安全を確保するため、ある程度把握することは必要です。
在宅ワーカーとの間では、メールやチャットツールなどを活用して、定期的な報告や進捗確認を行い、円滑にコミュニケーションをとることが必要です。また、Web面談やチームビルディングなどのイベントを開催することで、コミュニケーションの機会を増やすことも有効です。
また、在宅ワーカーは、自宅などで業務を行うため、情報漏えいのリスクが高くなります。あらかじめ在宅ワーカーに対し、必要なセキュリティ対策を講じるよう求めるとともに、契約時には秘密保持契約などを締結し、情報漏えいのリスクを最小限に抑えることが重要です。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
雇用形態についてよくある質問
雇用形態の違いについて、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
- Q雇用形態によって、社会保険の取り扱いは違う?
- Q雇用形態を変更したら、有休はリセットされる?
勤怠管理システムで雇用形態の整理を
雇用形態にはさまざまな種類があり、それぞれの会社にとってのメリット・デメリットがあります。雇用形態のバリエーションを増やせばフレキシブルに多様な働き方に対応できる一方で、その分労務管理は複雑になります。
勤怠管理システムを導入することで、雇用形態に応じた労務管理が効率的に実践可能となります。多様な雇用形態の採用に向けて、勤怠管理システム導入をおすすめします。
勤怠管理システムの選定・比較ナビは、多くの勤怠管理システムから自社にマッチした最適なシステムを見つけ出せるサイトです。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。