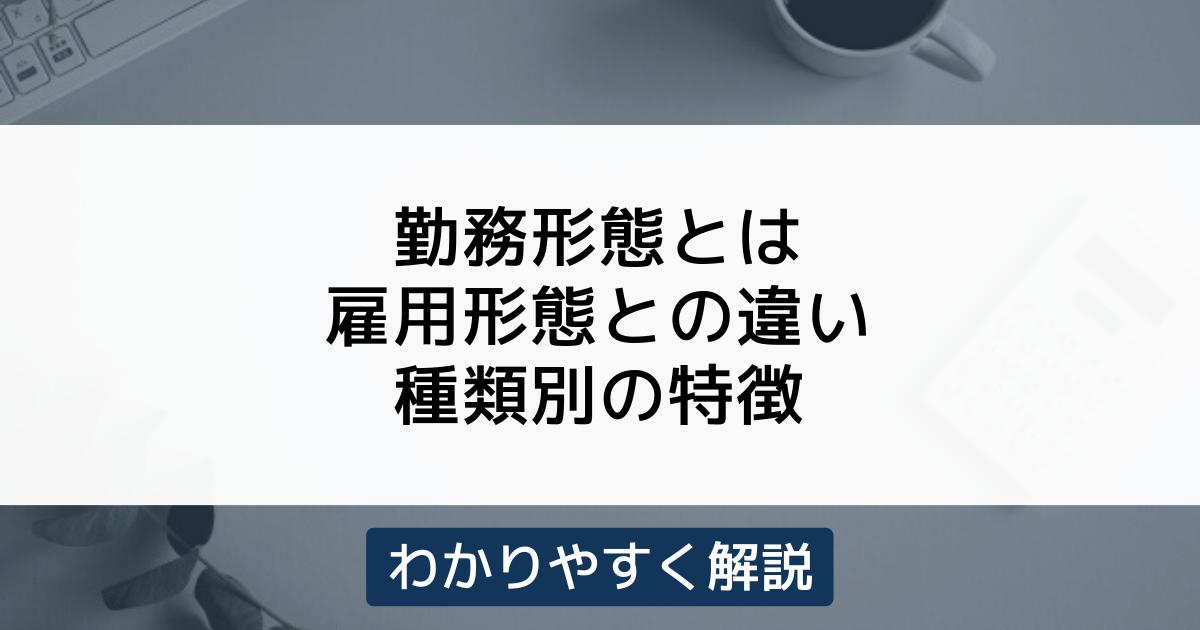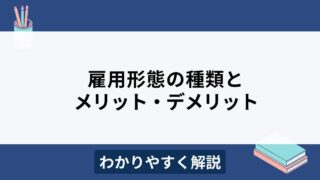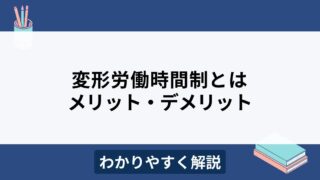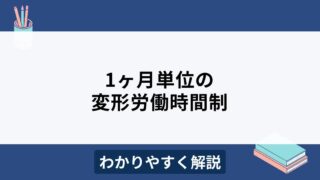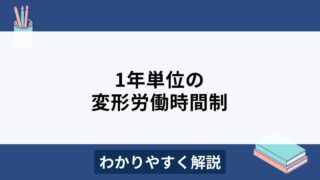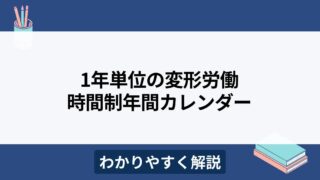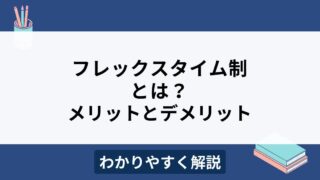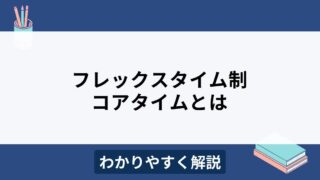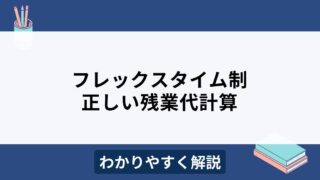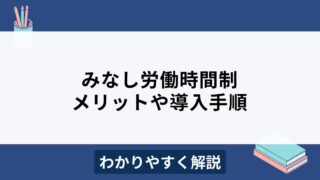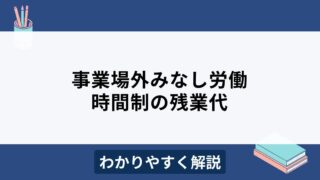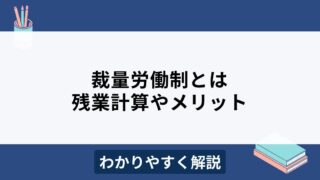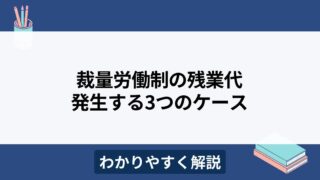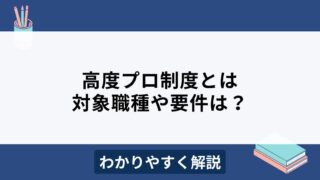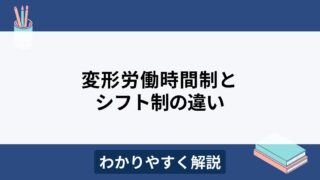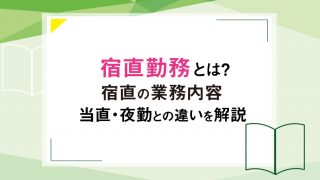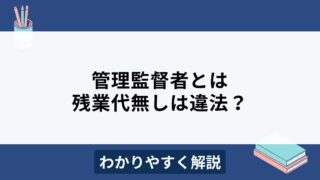事業主や人事労務担当者の方は、「勤務形態」という言葉をよく耳にすると思われます。よく似た言葉に「雇用形態」がありますが、両者はどう違うのでしょうか?また、勤務形態にはどんな種類があるのでしょうか?
この記事では、勤務形態の言葉の定義や、種類ごとの特徴、勤怠管理上の注意点について、わかりやすくまとめました。それぞれの勤務形態の詳細解説記事リンクも掲載していますので、この記事を読むことで、勤務形態の種類がスッキリ整理して理解できます。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
勤務形態は、働く時間や頻度などによる分類
勤務形態とは、「どの時間帯に働くか」「どういったペースで働くか」「労働時間は誰が決めるか」などによって分類した、働き方を指します。
主な勤務形態としては、「固定時間制(通常勤務)」「変形労働時間制」「フレックスタイム制」「みなし労働時間制」「高度プロフェッショナル制度」「シフト制」「宿直勤務制」「管理監督者」などがあります。
企業にとっては、勤務形態に応じた労働者の勤怠管理が必要になるため、それぞれの特徴を注意点も交えて解説します。
よく似た言葉に「勤務体系」がありますが、両者はほぼ同じ意味だと捉えて頂いて差し支えありません。ただし、勤務体系の方は「朝シフト」や「夜勤シフト」のように、シフトの区分も含めて使われることがあります。
雇用形態は、正社員・パート・アルバイト・派遣社員などのように、雇用契約上の社員の身分であり、雇用契約時の労働者の労働条件や待遇の違いをいいます。
| 勤務形態 | 雇用形態 | |
|---|---|---|
| 定義 | 働く時間帯や頻度などによる分類 | 雇用契約上の労働条件や待遇などによる分類 |
| 具体例 | 通常勤務、変形労働時間制、フレックスタイム制、シフト制、 | 正社員、有期契約社員、パートタイマー、派遣社員、 |
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
勤務形態の種類一覧
代表的な勤務形態には、以下のような種類があります。
| 勤務形態 | 所定労働時間 | 休憩付与 | 時間外・休日割増 | 深夜割増 |
|---|---|---|---|---|
| 固定時間制(通常勤務) | 固定 | あり | あり | あり |
| 変形労働時間制 | 変動 | あり | あり | あり |
| フレックスタイム制 | 始業・終業を労働者に委ねる | あり | あり | あり |
| 事業場外みなし労働時間制 | 所定労働時間+みなし労働時間 | あり | あり | あり |
| 裁量労働制 | 労働者に委ね、みなし労働時間で管理 | あり | なし | あり |
| 高度プロフェッショナル制度 | なし | なし | なし | なし |
| シフト制・交代勤務制 | 変動 | あり | あり | あり |
| 宿直勤務制 | なし | なし | なし | あり |
| 管理監督者 | なし | なし | なし | あり |
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
勤務形態の種類ごとの特徴と注意点
それぞれの勤務形態について、特徴と勤怠管理上の注意点を、もう少し詳しく見ていきましょう。
固定時間制(通常勤務)
固定時間制(通常勤務)とは、もっとも一般的な勤務形態で、1日8時間・週40時間(特例措置対象事業場は44時間)という法定労働時間の枠内で設定された所定労働時間に従って労働する勤務形態です。
所定労働時間が月曜日~金曜日の週5日勤務(土日は休日)で、9時から18時までの計8時間労働(途中の休憩1時間)というのが典型例です。時間外労働に対しては、労働基準法に従って25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
労働時間が一定で固定されているため、柔軟性に乏しいものの、スケジュールを立てやすく、また企業側の勤怠管理は非常に楽であるのが特徴です。
まずは固定時間制を軸に据えて、職務経験など労働者の業務能力の違いや、業務の閑散期によって、労働者の業務量に差が出るようであれば、変形労働時間制などの導入も視野に入れましょう。
変形労働時間制
変形労働時間制とは、月や年単位で労働時間を調整する労働時間制で、一定期間の総枠の中で労働時間をやりくりする制度です。
変形労働時間制には、「1ヶ月単位」「1年単位」「1週間単位」「フレックスタイム制」がありますが、フレックスタイム制は異質なため、分けて解説します。
繁閑の差による労働コストのロスを減らせる一方、制度導入のためには一定の手続きが必要で、労働時間の管理も煩雑になります。
1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月以内の対象期間(「変形期間」と呼びます)の中で、特定の日や週の所定労働時間を増減させる制度です。一定の条件のもと、法定労働時間(1日8時間、週40時間または44時間)を超える所定労働時間の設定が可能です。
具体的には、変形期間を通じて、週平均の労働時間が40時間(または44時間)以内となるように、労働日ごとの労働時間を設定します。特定の週や曜日に、どうしても業務が集中する事業場などで有効です。
週平均40時間と期間内の総枠に収まっていれば、任意の週・日ごとの労働時間の上限がなく、大胆な労働時間の設定が可能です。一方、導入するには、就業規則の改定もしくは労使協定の締結が必要で、労働時間の管理や残業代の計算が煩雑になる点には注意が必要です。
1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、1ヶ月を超え1年以内の変形期間の中で、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える所定労働時間の設定が可能な制度です。ハイシーズン・オフシーズンの差がハッキリしている事業場では、年間の時間外労働を削減できます。
また、労働者に対して閑散期の短時間労働や休暇の取得を推進し、リフレッシュしてもらうことで、事業場の生産性やモチベーションアップが可能です。一方、労使協定の締結が必要で、勤務カレンダーの作成や残業代の計算など労務管理の負担が増えるデメリットもあります。
1ヶ月単位との違いとしては、以下のようなことが挙げられます。
- 特例措置対象事業場であっても、週平均所定労働時間は40時間以内に収める必要がある
- 労使協定の締結が必須
- 1日の所定労働時間の上限は10時間
- 週の所定労働時間の上限は52時間
- 1年間の所定労働日数の上限は280日
1週間単位の非定型的変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制は、1週間ごとに日々の所定労働時間を弾力的に設定可能な制度です。
曜日によって繁閑の差が激しい事業場において、1日10時間を上限に所定労働時間の設定ができます。ただし、労使協定の締結が必要であり、対象事業場が「常時30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業」に限られていることから、実際の導入事例は少ないのが現状です。
フレックスタイム制
フレックスタイム制は、日々の始業時間と終業時間の設定を労働者に委ねる制度です。フレックスタイム制は労働基準法では、変形労働時間制の一類型のように定義されていますが、内容は全く別物です。
労働者にとって柔軟な働き方が可能となり、生産性の向上が見込める一方、コミュニケーションロスや勤怠管理が煩雑になるというデメリットもあります。
清算期間によって2パターン
フレックスタイム制は、対象となる期間(「清算期間」と呼びます)によって、「1ヶ月以内のフレックスタイム制」と「1ヶ月を超え3ヶ月以内のフレックスタイム制」の2パターンがあります。
両者にはそれぞれ、以下のような違いがあります。
| 1ヶ月以内 | 1ヶ月を超え3ヶ月以内 | |
|---|---|---|
| 時間外労働のカウント | 清算期間の総枠 | 清算期間の総枠+1ヶ月ごとに算出 |
| 導入に必要な手続き | 就業規則+労使協定締結(届出不要) | 就業規則+労使協定締結・届出 |
コアタイムとフレキシブルタイム
フレックスタイム制において、就業時間のうち必ず出勤しなければならない時間帯として指定された時間を「コアタイム」と言います。一方、労働者が自由に出退勤を決められる時間帯を「フレキシブルタイム」と言います。
コアタイムに出勤していない場合は、遅刻・早退として扱うことができますが、所定労働時間の大半をコアタイムが占めるような設定は認められません。また、コアタイムやフレキシブルタイムは、必ずしも設けなくても差し支えありません。
フレックスタイム制においては、残業代の計算が複雑になりがちなため、労働者への制度の周知説明を徹底し、誤解を生じさせないことも大切です。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
みなし労働時間制
みなし労働時間制は、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた「みなし労働時間」分を働いたとして扱う制度です。大きく「事業場外労働のみなし労働時間制」と「裁量労働制」に分かれ、さらに裁量労働制には「専門業務型」と「企画業務型」があります。
日々の労働時間の管理が楽になり、残業代削減効果も見込めます。一方で、恣意的に運用されるとサービス残業の温床になるため、導入のための要件や手続きは厳しく定められています。
事業場外労働のみなし労働時間制
事業場外労働みなし労働時間制とは、外まわりの営業職やバスガイドなど、事業場外の労働で労働時間の算出が困難な場合に、決められて時間だけ労働したとして扱う制度です。
具体的には、所定労働時間に加えて業務上通常必要とされる時間を、みなし労働時間としてカウントします。裁量労働制のように対象業務や事業場による制限はありませんが、通信手段の発達した現在では認められる余地は非常に少なくなっています。
専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制は、「業務の性質上、遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難な19の業種」に限って適用できます。
対象になる業務としては、研究開発やデザイナーなどがあり、対象者が限定的である一方、導入手続きは企画業務型裁量労働制よりもハードルが低めです。
一方、企画業務型裁量労働制は、「企業全体に影響を及ぼす事業運営上の重要な決定が行われる事業場において、対象業務に従事する労働者」が対象で、労使委員会による決議が必要です。
裁量労働制を導入する場合は、複雑な要件や手続きを押さえることが必要です。また、残業代が発生するケースもあることを認識して、労使トラブルにならないように注意しましょう。
高度プロフェッショナル制度
高度プロフェッショナル制度は、高度な専門的知識を持つ労働者を対象に、労働時間に基づく制限を撤廃した、完全成果報酬型の制度です。通常の時間外労働や休日労働、深夜労働に対する割増賃金が発生せず、休憩の付与義務もないなど、労働基準法の多くが適用されません。
よって、裁量労働制よりもさらに適用範囲が狭く、高度な専門的知識等を要する4業務に限定され、一定の年収要件を満たすことも必要です。
シフト制・交代勤務制
シフト制や交替勤務制は、曜日や時間帯ごとに勤務する労働者が異なる勤務形態です。
コンビニ店員や病院の看護師などにみられる交替制ですが、労働基準法に定められている制度ではありません。シフト制・交替勤務制は、2交替制もしくは3交替制の2種類が採用されるケースが多いです。
労働者個々の労働時間を抑えることができる一方で、曜日、時期、勤務時間帯によっては、人員の確保が難しくなるケースがあります。
宿直勤務制
宿直勤務制とは、たとえば通常労働者の勤務時間終了後から翌日の業務が開始されるまで、事業所で待機しておくような勤務をいいます。
労働基準法第41条において、「監視または断続的労働に従事する者で労働基準監督署長の許可を受けた者」については、労働時間、休憩および休日に関する規定が適用されないと規定されています。
また、宿直については、1日8時間を超える労働や休日労働をさせる場合でも、36協定の締結は必要ありません。宿直手当については、通常勤務労働者の賃金の1/3を下回らない額となります。
管理監督者
管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にある者をいいます。
管理監督者には、労働基準法の労働時間や休憩、休日の規定が適用されません。ただし、深夜労働に対しては深夜割増賃金が発生し、また有給休暇は、通常の労働者と同じように付与する必要があります。
なお、残業代などのコストカットを目的に、単なる役職名だけで「管理監督者」として扱うことは認められません。管理監督者は、職務内容、責任と職務権限、勤務実態によって判断しなければならず、「名ばかり管理監督者」とならないように注意しなければなりません。
勤怠管理システムで、多様な勤務形態を楽に管理しましょう
通常の固定時間制はもちろんのこと、変形労働時間制やフレックスタイム制でも時間外労働の計算は必要です。複数の勤務形態が混在している場合は、どの勤務形態にどの規定が適用されるのか、整理することも必要です。
また、どのような勤務形態を導入・運用するにしても、個々の従業員の労働時間を把握・管理することは、使用者の義務です。
勤怠管理システムを導入することで、勤務形態に応じた適切な設定や計算を自動化できるため、労務管理の負担が激減します。結果的に、事業場全体としての生産性向上につながることが期待できます。
「勤怠管理システムの選定・比較ナビ」をご利用いただくと、複数の勤務形態を一括管理できる勤怠管理システムの中から、自社に最もマッチングする製品を探し出せます。多様な勤務形態の導入をご検討されている方は、勤怠管理システムの選定・比較ナビを是非ご利用ください。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。