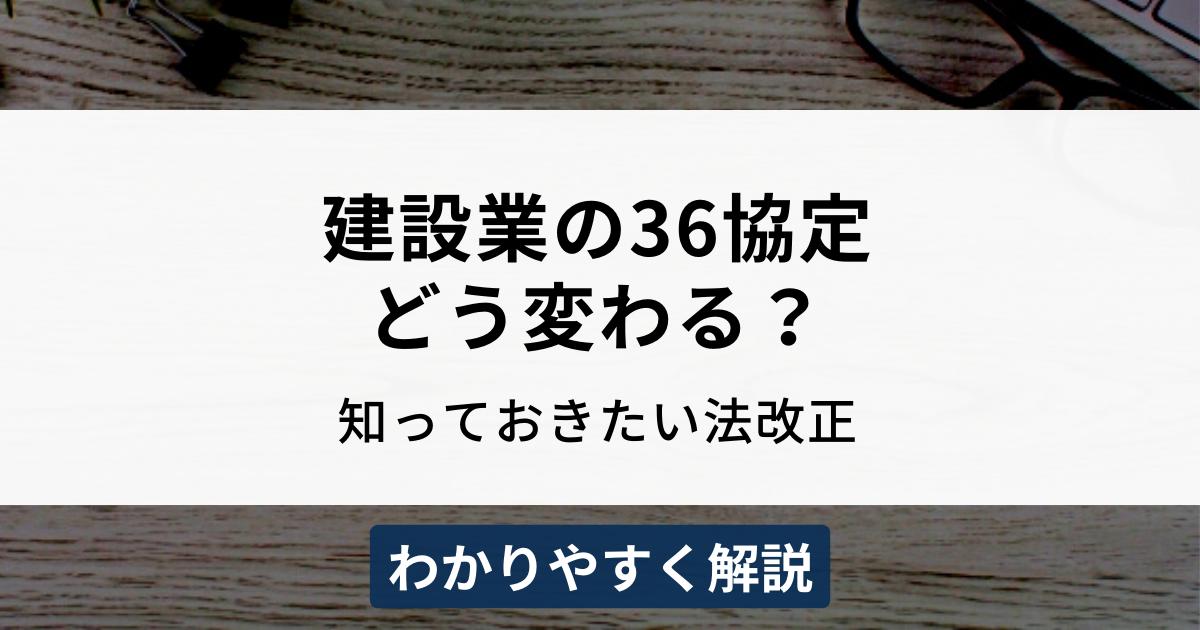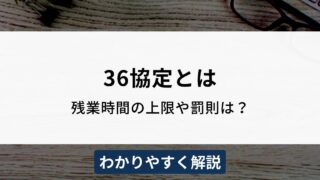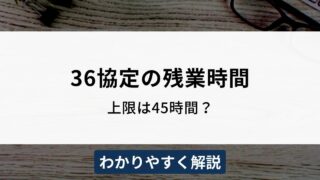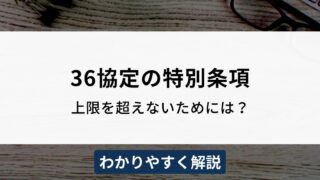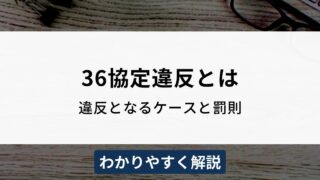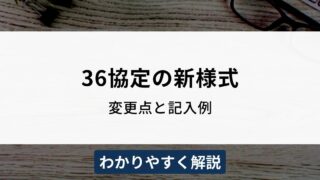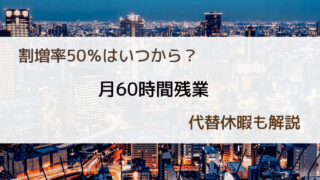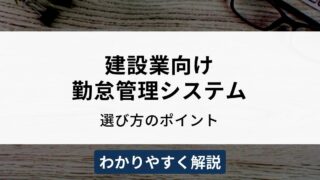2019年4月の働き方改革関連法施行に伴い、それまで告示レベルに留まっていた36協定の上限時間に、罰則付きで規制が設けられました。
建設業においては、その業態の特殊性から5年間の適用猶予期間が設けられてきましたが、2024年4月からはいよいよ本適用となることが決まっています。
適用により、具体的な労働時間の上限はどうなるのでしょうか?また、違反した場合はどのような罰則が待っているのでしょうか?
この記事では、2024年4月から建設業に適用される36協定の上限規制について、わかりやすく解説します。また、2024年3月までの適用猶予期間中の36協定の記載例も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
36協定とは?
労働基準法において、労働時間は1日8時間・週40時間までと定められており、これを法定労働時間と呼びます。法定労働時間を超える労働を命じるには、「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」を締結し、管轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
この労使協定の根拠条文が労働基準法第36条であることから、一般的に「36協定」と呼ばれています。また、36協定の締結・届出の有無に関わらず、現実に発生した法定時間外労働に対しては、25%以上の時間外割増賃金が必要となります。
ここまで解説した法定労働時間と36協定、割増賃金の規定については、建設業であっても他の業種と同じように適用されます。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
2024年4月から、建設業の36協定はどう変わる?
2019年4月から、一般企業には36協定を締結した際の時間外労働時間について、罰則付きで上限が設けられました。
しかし、建設業においては、以下のような特殊な業界事情により改正への早期対応が難しく、適用が5年間猶予されることとなりました。
- 天候や資材の調達などにより、納期が左右される
- 下請けは、元請けからの受注を受け続けるために長時間労働を余儀なくされる傾向にある
現在の建設業における36協定上限は適用除外
現在の建設業界においては、改正前の36協定の規定がそのまま適用されています。つまり、36協定で定める時間外労働については、特に上限基準及び罰則は定められていないということになります。
なお、前述したとおり、時間外労働をさせるための36協定の締結・届出は必要であり、協定届には「様式9号の4」という様式を用います。
2024年4月からの建設業における36協定の上限
36協定で定めることのできる時間外労働につき、休日労働を除いて月45時間・年360時間が上限となります。なお、1年単位の変形労働時間を導入している場合は、上限が月42時間・年320時間となります。
また、上限時間を超えて労働させる必要がある臨時的な特別の事情がある場合は、36協定に特別条項を設けることで、さらなる時間外労働が可能となります。ただし、特別条項を適用する場合でも、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 時間外労働(休日労働除く)の合計が年720時間以内
- 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
- 月45時間の上限を超えることができるのは年6回まで
- 時間外労働と休⽇労働の合計が2~6ヶ月平均のいずれも80時間以内
様式は、現在ほかの一般業種に適用されている新様式の「様式9号」(特別条項を設ける場合は「様式9号の2」)を用いることになります。
災害時の復旧・復興の事業の例外
災害時の復旧・復興の事業については、2024年4月以降も以下の規定は対象外となります。
- 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
- 時間外労働と休⽇労働の合計が2~6ヶ月平均のいずれも80時間以内
なお、ここで言う「災害時」は、「通常予見できない災害」と定義されています。復旧・復興の事業が、すべて一律に適用除外とされるわけではありません。
2024年4月以降は36協定違反の罰則も適用
特別条項を設けることなく36協定で定めた時間を超過したり、特別条項で定めた上限時間を超過したりした場合は、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
また、違反内容が悪質であると判断された場合には、企業名公表の対象となり、企業イメージの失墜、大量離職につながる恐れもあります。
なお、36協定を締結することなく時間外労働をさせたり、時間外労働に対して適切な割増賃金を支払っていなかったりする場合は、現在でも罰則の対象となっているため、混同しないよう注意しましょう。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
建設業の36協定記載例
建設業の36協定届は、適用が猶予されている2023年3月31日までは「様式第9号の4(適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務:自動車運転者、建設業、医師等)」を使用します。
また、2024年4月以降は、原則的には一般の事業と同じ「様式第9号及び第9号の2(特別条項つき)」を使用しますが、「災害時における復旧及び復興の事業」については、「様式第9号の3の2及び様式第9号の3の3(特別条項つき)」を使用します。
2024年3月31日まで(様式第9号の4)
「様式第9号の4」の書式テンプレートは、厚生労働省のサイトの以下のリンクより、ダウンロード可能です。
なお、建設業の場合は現場作業従事者だけでなく、内勤の事務職や営業職の従業員についても、すべて同じ様式を使用します。以下、各項目について記入例を解説します。
事業場の種類・名称・所在地
事業場の種類、名称(工場、支店、営業所など)や所在地(電話番号を含む)を記載します。36協定は原則、事業場ごとにそれぞれ締結しなければなりません。よって、事業場が複数ある場合は、それぞれ事業場ごとに書面を作成する必要がありますので、注意してください。
時間外労働をさせる必要のある具体的事由
使用者が時間外労働を命令しなければならない、具体的な理由を記載します。たとえば現場作業員であれば「工期変更への対応」、事務職であれば「決算業務」などと記載します。「使用者の判断による」など、抽象的な表現は認められません。
業務の種類
時間外労働を必要とする具体的事由に対応する職務を、なるべく具体的に記載します。たとえば「現場作業」「営業」「事務」などと記載します。
労働者数
該当業務に従事するもののうち、満18歳以上の人数を記載します。なお、満18歳未満の労働者は、原則的に時間外労働・休日労働を命じることはできません。
所定労働時間
会社が就業規則等で定める1日の所定労働時間を記載します。一般事業の様式(様式第9号)ではこの欄は任意記載となっていますが、本様式では「(任意)」の文言がないため、必須項目とされています。
延長することができる時間数(1日)
業務ごとに、1日の延長時間数を記載します。特に上限は設けられておらず、ここに記載した時間数を超えたとしてもただちに違法となるわけではありませんが、労働者の健康に配慮した現実的な時間を設定しましょう。
1日を超える一定の期間(起算日)
1ヶ月や1年などの一定期間の範囲内で、延長することができる時間数を記載します。具体的には、「1ヶ月:80時間、1年:800時間」のように記載します。また「起算日」には、期間の始期となる具体的な日付を記載します。
期間
定めた内容が適用される対象期間を記載します。通常は「起算日より1年間」を記載します。
休日労働に関する事項(所定休日)
会社が就業規則等で定める所定休日を記載します。具体的な曜日が特定されている場合はその曜日を、曜日が特定されていない場合は「週休2日」などと記載します。
休日労働に関する事項(労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻)
法定休日(週1日または4週を通じて4日)のうち、休日労働を命じることのできる日数とその日における始業・終業時刻を記載します。具体的には「月に2日、9:00~20:00」などと記載します。
なお、所定休日における労働は、ここで言う休日労働には該当せず、上段の時間外労働に含まれるため、注意しましょう。
代表者に関する事項
協定の当事者である過半数労働組合の名称、もしくは過半数労働者代表の職名・名前・選出方法などを記載します。なお、管理監督者は過半数労働者代表になれませんが、職名が紛らわしい場合は「(管理監督者ではない)」などと付記しておくと良いでしょう。
チェックボックス ※2箇所
上記で記載した代表者が、「間違いなく過半数労働組合または過半数労働者代表であること」及び「管理監督者でなく、かつ民主的な方法(投票、挙手など)によって選出されたこと」を確認するためのチェックボックスです。
2箇所のチェックボックスのうち、どちらかでもチェックが漏れていると受理されないため、注意しましょう。
2024年4月1日以降(様式第9号及び第9号の2、または第9号の3の2及び第9号の3の3)
2024年4月1日以降は、基本的に一般業種と同じ様式第9号(一般条項のみ)及び様式第9号の2(特別条項つき)を使用します。こちらの記載例については、以下の記事にて解説していますので、ぜひご覧ください。
また、建設業のうち「災害時における復旧及び復興の事業」については、2024年4月1日以降も以下の上限規定が適用除外となります。
- 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満であること
- 時間外労働と休日労働の合計について、2~6ヶ月平均80時間以内であること
よって、36協定届は様式第9号の3の2(一般条項のみ)及び第9号の3の3(特別条項つき)を使用します。書式テンプレートは、厚生労働省のサイトの以下のリンクより、ダウンロード可能です。
様式第9号の3の2(Word形式)
様式第9号の3の3(Word形式)
一般の第9号及び第9号の2との違いとしては、特に第9号の3の3の記載欄が「工作物の建設の事業 に従事する場合」と「災害時における復旧及び復興の事業に従事する場合」に分けられている以外は、大きな違いはないため、一般業種の記載例に倣って記載するのが良いでしょう。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
36協定以外の建設業に対する規制の動き
慢性化する長時間労働問題やいびつな労働環境の改善に向けて、36協定の上限規制以外にも、建設業の労働環境是正に向けた取り組みが行われています。
週休二日制の導入
2024年4月から始まる時間外労働の上限適用に合わせ、「週休2日制」の導入が推奨されています。他の業種と比べて休日数が十分に確保されていない点が、建設業界の人手不足や離職率の高さを招いている要因の一つです。
柔軟な働き方の実現や価値観の多様化に伴い、ワークライフバランスを重視する労働者が増えています。週休2日制の導入によって、建設業界へのネガティブなイメージを払しょくするのが狙いです。
国も積極的に動いており、国土交通省が「公共工事における週休二日制の推進」を発表しました。義務化とまではいかないものの、影響力の大きい公共事業から週休2日制の導入を後押し、業界全体の意識改革や週休2日制の普及率向上を目指しています。
同一労働同一賃金
同一労働同一賃金は、同じ業務内容を遂行している場合、雇用形態の違いを理由とした不合理な待遇格差を是正するという考え方です。待遇には賃金だけでなく、休日や福利厚生の適用範囲、教育機会も含まれます。
特に建設業に限った制度というわけではありませんが、2020年4月(中小企業は2021年4月)から、上記原則に則った「同一労働同一賃金制度」が開始されています。
建設業には「有期契約労働者」や「派遣労働者」も多いため、これらの労働者と正規雇用の労働者との不合理な待遇格差の解消が求められています。
月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金の引き上げ
こちらも建設業に限った話ではありませんが、2019年4月から大企業に対して、月60時間を超える時間外労働につき、通常25%以上とされている割増賃金率を50]%以上とすることが義務付けられました。
2023年4月からは、それまで適用が猶予されていた中小企業においてもこの割増賃金の引き上げが適用され、建設業の中小企業にも本適用は及んでいます。
これまで以上に、長時間労働の是正、業務効率化、人件費以外のコスト削減など、多方面に渡る対応が求められていると言えるでしょう。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
建設業の2024年問題対応には勤怠管理システムがおすすめ
建設業は、長時間労働が常態化している状況です。何も手を打たないままでは労働者は職場を離れ、ますます人手不足が加速する悪循環に陥ります。残業時間の上限規制が適用される時期は2024年4月と決定しており、適用開始時期を動かすことはできません。
残された時間は決して多くなく、今のうちから長時間労働是正に向けた対応が必要です。そこで、モバイル打刻やシフト管理など、建設業向けの機能を備えた勤怠管理システムを導入することで、労働時間を正確に管理できるようになります。
労働時間・残業時間・有給休暇の取得状況の集計~分析まで、勤怠管理システムに一任できるため、人事担当者が作業をおこなう必要はありません。
「勤怠管理システムの選定・比較ナビ」をご利用いただくと、建設業の労務管理問題是正をサポートしてくれる勤怠管理システムの中から、自社に最もマッチングする製品を探し出せます。勤怠管理の工数増大にお悩みの方は、勤怠管理システムの選定・比較ナビを是非ご利用ください。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。